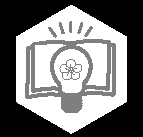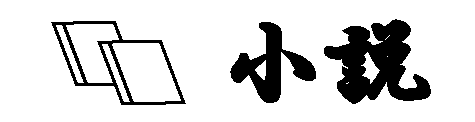|
夜のギター。
失望の 世田谷区を後にして、制服、
食事、 住居つきの、江東区の「給食センターの、寮」に入った。 一年ほど
住み込みで懸命に働いて、少しお金を貯めた。
隣のベッドの下には、角崖という 飯炊きの大きな老人と、上には 吾妻という 冗談好きで、酒好きの
厨房の先輩と 三人部屋になり、家族的な寮だった。
寮の傍には 川が流れていて 風通しが良く、夕暮れには
休憩室のギターを 屋上に持ち出して、ベンチで 切ない曲を いつまでも ひいて 夜を過ごした。
詳細はこちらへ 、東京。
省略。
--------------------------
孤立。
だが、一年半後には、色々 有って、この「給食センター」の弁当屋を辞めてからは、亀戸四丁目の 「くにみ
そう」という、古い アパートの二階に
住むようになった。
--------------------------
自閉症。
衣食住、 三食 昼寝つきの 「弁当屋の寮」の集団生活は
気ままな一面、気が散って落ち着けずに、一人で 静かに暮らしたくなった。
自分の部屋だとホッとするが、毎月の高い家賃と 毎日の食事代で、貯金が あっという間に消えていった。 子供の頃からの「自閉症」の障害を 隠して、バレないように、人との関わりを避けながら生きる、「まこと」には、自立して生きる事の 厳しさを 再び 噛み締めていた。
--------------------------
自立心。
家賃を稼がなきゃ、孤独で気ままな一人暮らしも許されなくなる。まことは、アルバイトニュースの小冊子を買って来て、付録についている履歴書に、これまでの学歴と職歴を書き始めた。
(とりあえず、近く?の飲食店を当たってみよう。)と考えた。(少しは経験があるほうが、採用して頂けるだろうか?。)と 考えて、旅行会館では、ウェイターとパーラー喫茶のカウンターの経歴を。その後は、給食センターの弁当屋の厨房にいた
と経歴に書いた。
自転車に乗って、近くの商店街をゆっくりと見て回った。だが、駅から離れた商店街には、募集している店は、ほとんど無く、気落ちして戻って来た。
--------------------------
喫茶店。
「さあ、いつまでも、のんびりしてはいられない。どこか、いい働き口を見つけなきゃ。」と考えて、亀戸駅前の商店街をうろついていると、角にある「靴屋」の店の 横の壁に、「バイト募集中!。」という、二階の 見晴らしのいい喫茶店の「貼り紙」が
目に入った。
--------------------------
「あ、ここは 働きやすそうだなあ。」 おいしそうな フルーツパフェなどの、サンプルを並べた ガラスケースを横目に見ながら、階段を上がり、右横のドアを引いた。
「あのー、募集の件で 来ました。」 「あ、じゃあ
どうぞ、その席に 座って待っててね。」と案内してくれた。
--------------------------
面接。
まことは、左の壁側の席に座って待った。お姉さんは、カウンターの中に入って、お客が注文したホットコーヒーを温めると、お盆にセットした、カップに注いだ。 すぐに表側に廻って、砂糖とミルクを添えて、窓側のお客に運び終えてから、まことの前にもコーヒーを差し出して「どうぞ。」と一言、言って座った。「あ、すみません。」「いえ。」 お盆を横に置いた。「履歴書、見せて下さいね。」「はい。」「あー、ご出身は福岡から?。」「はい。」「‥‥。」座った。
--------------------------
経営者らしい お姉さんが、一人で忙しく接客しながら、面接も受け付けていた。提出した履歴書を ひととおり見終わると、「じゃあ、すぐに 明日から 働いて貰えますか?。」と、簡単に採用が決まった。「明日の朝の七時半に、この下の 店の前で、待っていて下さいね。」「はい。分かりました。」
--------------------------
翌朝になった。時間前に 早めに出て 店の前で待っていると、見知らぬ女性がやって来て 少し離れて足を止めた。
チラチラと、「まこと」の顔を見て、視線が合うので
気になったが、(誰かと ここで待ち合わせだろうか…?。)と思って、無視して経営者を待っていた。
--------------------------
出逢い。
しばらく、気まずい思いで待っていたら、経営者が現れた。「ああ、遅れて、ご免なさいねー。」急いでシャッターの鍵穴に鍵を差し込んで、ガラガラと持ち上げた。「あ、貴方も、待たせてご免なさいね。」と、離れて立つ 女性にも声をかけた。「いいえ。」彼女も 私が 同じバイトの募集で来た人だと、理解したのか、安心して、そばに近づいて来た。
--------------------------
「さあ、二人とも上がって。あなた達は、今日から一緒に働いて貰う、バイト仲間ですよ。」「ああ、そうだったんですか?。」「フフフ。」二人は、互いに
顔を合わせ、ニッコリと微笑んだ。「よろしくお願いします。」「こちらこそ。」 同じ日に、同じ職場で、一緒に働く立場になった事が 嬉しかった。
さっきまでの不安が 一気に消えていた。
--------------------------
シャッターをあけると、急にお客さんが、次々と入って来た。二人とも喫茶店の仕事は初めてで、何をどうしたらいいのか
さっぱり分からず、初日は てんやわんやで あわただしく過ぎた。
--------------------------
カウンターの中の仕事は、たくさんあり、一つ一つ 教えて貰いながら、(どんなメニューでも、覚えてお客様に出せるまで、頑張るしかない…。)と思った。
--------------------------
彼女も、喫茶店の仕事は 初めてらしく、ぶっつけ本番で、戸惑いばかりの初日だったようだ。しかし、そのせいか、すぐに仕事を覚えて、テキパキとこなして、さばけるようになった。
--------------------------
「ウェイトレス」の仕事は、お客様の 注文のオーダーを正確に受けて、テーブル番号を間違えないように覚えて、お待たせしない様に、無事に運び終えるまでは、気が抜けない接客業である。
--------------------------
朝いちと 昼の2時間ほどは、目まぐるしい忙しさで、お客が殺到するが、 3時も過ぎると、少し落ち着いて来た。余裕が出来て
お互いに慣れてきて、次第に話が出来るようになった。(仕事が終わってから、一度
ゆっくり 話しをしてみたいな…。)と思った。
--------------------------
オーナー。
ときどき、下の靴屋の社長が、お客さんを連れて上がってきた。一番眺めの良いテーブルに着いて、コーヒーを頼んで接待し、取引の打ち合わせをした。
この靴屋の社長は、ここの二階の、喫茶店「トロン」の
オーナーでもあった。
--------------------------
まだ、新人の、ウェイトレスの かおるが、おひやと おしぼりを運ぶと、社長が 大声で話しかけてきた。「あんたの彼氏は、歯科技師の仕事しよると?。」「えっ。」「はーあ、彼氏が
そんな いい技術を持ってるなら、将来は 有望だ。立派な お金持ちの奥さんになるねー。」「え…。」「そらー
良かったー。 うーん。」
--------------------------
妄想。
一方的な話の内容に、「まこと」は、少しショックを受けた。(え、かおるさんには 彼氏がいるの…?。しかも、なんで 社長が、個人の情報を勝手に バラしてるんだ?。)「まこと」は内心 彼氏と社長に 怒りに近い ジェラシーを感じていた。
--------------------------
(ああ、遅かったか…。もう 既に、将来を約束した 立派な相手がいたのか?。 あー、聞かなきゃ良かった。 知らなきゃ、気軽に誘えたのに。社長めー!…。)
--------------------------
「この子には、社長公認の 相手が、ちゃんといるんだぞ。だから、下手に手を出すなよ!。」と、(わざと大声で、「まこと」に 聞こえるように警告された?のだ。)と思い込み、「まこと」は、だいじにされる かおるに
気安く近づく事をおそれ、早くもその迫力に負けて、諦めてしまった。
--------------------------
「まこと」は、思想や 宗教に かぶれてばかりで、この世で身につけるべき、何の技術も無い。男としての魅力も、生活力も無い 自分を痛感し、自己卑下ばかりしていた。喫茶店の仕事も、ウロ覚えで
まだ半人前で 得意でもない。
一生を貫く 「天職」の仕事を、まだ見つけてすらもいない。何一つ、自分に自信が持てない
ダメな 「落伍者」に 感じた。
--------------------------
妄想。
(もう駄目だ。僕には勝ち目が無い。
彼女に 近づく資格など僕には無い…。)「まこと」は、切ない想いに 封印した。 (いいんだ。僕には、勿体無いほど素晴らしい、尽くしてくれる
年上のお姉さんの弘子さんが 既にいるもの…。これ以上、何を望むというのか?。)
--------------------------
「まこと」は、それからは、恋人がいる と分かった かおるとは、見えない一線を引いて、距離を置くように心がけるようにした。全く興味が無いかのようにふるまった。
決して自分から何か、求めるような 誘いを一切しなかった。
--------------------------
かおるが、親しげに何か話しかけても、消極的にクールに短く対応した。 仲良く何でも話しをしていると、(恋人に申し訳ない。)という気持ちが湧いて、
かおるに 深入りするのを抑えた。仕事に関する やり取りだけに限ってしか、あえて
話さないように ふるまった。
--------------------------
かおるは、自分に「彼氏」がいる事を聞いた「まこと」が、心の距離を置いて、深入りしない様にしてる事に
感づいて、すごく寂しい気持ちになっていた。
--------------------------
(私に そんなに気を使って、控えなくてもいいのに…。)「まこと」の心の中に、何か
拘束された 不自由な 身動きが取れない 「底知れない
暗闇」が 潜んでいる事に気づいていた。(何とかして まことさんの窮屈な 心の鎖を 解放してあげて、親しくなる 方法がないかなあ?。)と色々と
考えていた。
--------------------------
ある日、かおるが
食材の買い出しから帰って来ると、買い物カゴを抱えたまま 呟いた。「ちょっとカウンターに入らせてね。」「え、なに?。」「たまには 私にも 料理を作らせてね。」「ああ。」
--------------------------
「まこと」が立っている、狭いカウンターに回って、かおるが入って来た。「まこと」の後ろをすりぬけようとして、すれ違う瞬間に、初めて 二人の体が接近し接触した。
--------------------------
妄想。
「まこと」は、背中越しに、柔らかい かおるの 暖かい胸と、やわ肌の感触を
洋服とスカートの布を通して感じた。(ああ、いいかおりがする…。) 一瞬で脳裏に、いけない妄想がよぎった。
--------------------------
入れ替わった 「まこと」は、ウェイターに気持ちを切り替えた。彼女が、鍋を火にかけ、何かをバターで
炒め出した。その様子を しばらくながめた。やがて、美味しそうな香り がしてきた。
--------------------------
おたまでスープをすくって味見をして、「うん。いい…。」 と頷き、皿に盛り付けて差し出した。「はい、できたよ。」「あー、ありがとう。頂きます。」見ると、それは
ハマグリのスープだった。一口すすると、今まで食べたことも無いような、深い 味わいだった。
--------------------------
妄想。
(ああ、こんなに美味しい 味付けが出来る 女性なのか…。)と 驚いた。「まこと」は、完全に かおるのファンになり
すっかり、好きになってしまった。
(ああ、こんなに 料理が上手な 女性がお嫁さんだったら、幸せだろうなあー。 あ、いや、不埒な想いは いけない。) かおる が、「どう?、お味は?。」と尋ねた。「まこと」は ときめく胸の 高鳴りをおさえて、慌てて やっと 答えた。
--------------------------
「ご免、僕は 実は …貝が嫌いなんだ。」「え?、そうなの…。」「ごめん。」と謝った。かおるは、意外な感想に、がっかりした。「まあ…。」と 少し
怒った顔になった。
--------------------------
「まこと」は、「貝が嫌いなんだ。」と答えた瞬間に、激しく後悔していた。(せっかく、真心を尽くして
作ってくれたのに、その行為を 台無しにしてしまった。)「冗談だよ。」と、すぐに謝ろうとしたが、何故か そのまま 言葉を失い、本音を隠して 感謝もせず、放置してしまった。
--------------------------
その時、社長が入ってきた。いつも立っている
可憐な かおるの姿ではなく、華のない 「まこと」が 応対したので、急に社長の笑顔が 消えていた。何か 美味しそうな香りがしていた。
--------------------------
「なんだ。入れ替わっちゃ、ダメだよ。あんたは
中じゃなくて こちらにきなさい!。」カウンターの中にいる
かおるを見て、手招きしながら怒った。かおるは
怒られて 仕方なく戻った。
--------------------------
そんなことがあってから、かおるは、急によそよそしい対応をするようになった。何か話しかけても、うつろで、憂鬱そうな顔になった。
いつもの笑顔の表情が消えていた。すぐに会話が途切れてしまい、やりとりが続かず、つれなく他の方向を向いて、全くぎこちない 関係になってしまった。
--------------------------
店内には、いつも 有線放送のBGMが流れていた。「山口百恵」の歌う、ある曲がかかると、「この曲は、今の私の気持ちと同じだわー。」と、ポツリと
つぶやいた。
--------------------------
その曲とは、当時、ヒットしていた「イミテーション ゴールド」という曲だった。偽物の金?。メッキの金?。
「若いと思うー。今年のひとよー。ごめんねー、去年のひとにー 、まだ しばられているー。」という内容だった。これが、今の気持ちだ と彼女は 伝えていたが 「まこと」は、その意味に、全く気がつかなかった。
--------------------------
「まこと」は、カウンターの仕事を完璧に覚えようと考えて、(夜の時間から 交代する、カウンターの人の「指南」を受けよう。)と、定時が過ぎても
上がらずに 引き続き 夜の部も手伝う事になった。
--------------------------
かおるは、定時で上がって帰る支度を済ませていたが、帰らずに、ドアの前で、「まこと」の様子を見るように立っていた。「まこと」は、(あれ?。)と気づいた。
--------------------------
「僕、仕事を完璧に覚える為に、しばらく指南を受けるからね、僕の事は、気にしないで、先に上がっていいよ。はい!、早く帰ってね!。」と声をかけた。かおるは、何か話しをしたそうな仕草でじっと見つめたが、諦めて帰っていった。
--------------------------
それから、しばらくすると、かおるは、「まこと」には、一切、理由も何も言わずに、突然、店を辞めてしまった。
--------------------------
後編。
かおるが、急に来なくなって、しばらく、休んだ理由も全く考えないで、(あれ、どうしたんだろう?。)と思いつつ、代わりの人が決まって、来てくれるまで、社長の娘さん達が、入れ替わり 立ち替わりで、手伝ってくれた。これがきっかけで、韓国の家族たちがやっている
お店だという事を知っていく。
--------------------------
プロのカウンターの、しなんを受けて、完璧に仕事をマスターした、「まこと」は毎日、忙しく
コーヒーをたて、あらゆる食材を手早く処理して 準備して仕込んだ。
いつ 大勢の客が来ても、全てのメニューを
すぐに作って 出せるように 、毎朝、早でして万全の仕込みをした。責任感で、忙殺される日々を送った。
--------------------------
新しい、ウェイトレスが、次々と変わる度に、どこかに問題のある人ばかりが、入れ替わっていった。ゆがんだ性格や、態度の悪い不適格な人が多く、かおるの 存在が、「まこと」には いかに心地よく
とても大切で 大きな存在だったかを 思い知らされる様になっていった。
--------------------------
レジの操作も覚えられない、ウェイトレスには、ほとほと困り果て、「鮫島」という「靴屋」の従業員にグチをこぼした。「前にいた「かおるさん」みたいな子が 入ってこないかなあー。あの子が 一番 優秀だったねー。」 すると、靴の箱を抱えながら言った。
「バーカ!。誰のせいで辞めたのか、分かってるのか!。アンタのせいじゃないか!。」「えっ。」まことは、あまりの強い決めつけの言葉に、絶句した。 実は、まことは 少し前に
従業員割引で、女性用のブーツを買った事があった。その時、彼に相談して 安くして貰った。その事を 彼が
かおるに話すと、すごくショックを受けていたという。「彼には ブーツをプレゼントする彼女がいるんだよ。」「え、そうなの‥。」と ガッカリした様子だった。
(あれ、みんなも、僕のせいで辞めたと思っているのか…?。) お店の人達の、まことを見る目が、何だか 軽蔑の白い目で見られている事に、初めて気づいた。
--------------------------
(なんで 辞めてしまったの?。僕のせいで
辞めたの?。ああ、もう一度、叶うならば、かおるさんを連れ戻して、一緒に仕事をしたかった。そして、冷たくした事を
心から謝って、出来れば、取り違いした つれない対応を 全てやり直しを させて欲しい…。)
--------------------------
「まこと」の心は、取り返しのつかない失敗をした、愚かな自分の若さと、未熟さを憎み、軽蔑して、どうにもならない喪失感に襲われていた。(もっと、広い、おおらかな心で、優しく包んであげれば良かったのに、僕は一体、何を取り違いして、何を見間違えたのだろうか?。) 後悔ばかりの日々が続いた。
--------------------------
社長が、弁護士の 中年のおじさんを連れて入って来た。いつもの眺めのいい席に座ると、チラッと、「まこと」の顔を見ながら、「はぁあーあー…。」と、深くて長い、大きな「ため息」をついた。 それから、何やらヒソヒソと、弁護士に話しをしていた。弁護士は 「まこと」の顔を 時々見ながら 心配そうに頷いた。
--------------------------
「まこと」は、かおるが いなくなる前は、社長の機嫌が、すこぶる良かったのを覚えていた。それが、今では、不機嫌そうな
顔をした 社長の、深い ため息ばかりを 聞くようになった。 かおるが、「私、お店を辞めます。」と言った時に、(急に辞める理由が 一体なんなのか? を社長は 聞いて知っているのだろうか…?。)と気になった。
--------------------------
もしかして、その理由を 社長にしつこく聞かれて、かおるは、仕方なく、 「私、今井さんと、仲良くなろうと努めたけど、社長に怒られてから、もう他に方法が無くて、何だか
疲れちゃって。心がしおれて つらくて 苦しくて、もう 辞めます。」
--------------------------
社長は 何やら、思い当たるような話を聞いていた。彼女が、懸命に考えて、「まこと」と仲良くなる為に
苦心していた事を、社長は
全く知らずにいきなり怒って、二度とカウンターに入れないようにして、追い詰めてしまった事に
あとから話を聞いて、せっかちな判断した事に 気がついたのだった。
--------------------------
それで、こんなにも 落胆した、深い ため息を つくように
なったようだ。 (可愛い娘に、変な虫がつかないように。)と、牽制した 社長の思惑は、見事に当たり過ぎて、完全に「裏目」に出てしまった。
好みのタイプで、溺愛が過ぎた社長の失敗であり、また、純粋で潔白過ぎた
若い 「まこと」の失敗でもあった。
--------------------------
社長は、まるで 自分の娘かのように、かおるの姿を見ては、可愛がって、いつも
笑顔で話しかけていた。 (同じ日に、働く事になったのに、「まこと」には 一度も声をかけてくれないで、なに?、この差は なんなのだろうか?。)と 「まこと」は ヤキモチを焼いていた。
--------------------------
下の 「靴屋」の社員のみんなからも、愛され、可愛がられる、かおるの存在が、とても 羨ましかった。(それに引き換え、口ベタで 不器用な 自分なんて、人としての
魅力が 全く欠けているのかな?。)と、ますます、いじけて
すねてしまう、ひねくれた性格が 潜んでいた。
--------------------------
妄想。
(社長!。すみません。僕のせいです。かおるさんが辞めたのは、僕が彼女に、冷たくしたせいです。連絡先を教えて下さい。必ず 連れ戻して来ますから。)と言おうとしたが、喉に何かが絡まって、なにも言えなくなった。
--------------------------
酔い潰れ。
翌日、夜勤の仕事帰りに 商店街の道を歩いていると、何か女性の泣く声が聞こえて来た。何やら 酔い潰れて 道の横の石にもたれ掛かり、激しく泣いていた。「どうしたの?、何があったの?。」と
まことは 近づいて聞いた。
--------------------------
若い女性は、「ほっといてよ!。」と
強く怒鳴り返して 崩れ落ちるように 道に座り込んで また激しく泣き出した。
まことは 心配して しばらく様子を見ていた。長い髪に ジーパン姿から見て、まだ未成年の学生のように思えた。「ひょっとして 彼氏にフラれたの?。」と聞くと、図星だったのか、素直に認めて、「そうみたいね!。」と呟き、「まこと」の顔を 睨んで 答えた。
--------------------------
気の弱い まことは、これ以上
何も聞けなくなった。「今は
思い切り泣いたらいいよ、そして いつか 必ず立ち直ってね。じゃあ、元気出すんだよ。」と、軽く肩を叩いて、その場を去った。
まことは この時、いなくなった かおるの事を思い出していた。「ああ、こんなにも 酔い潰れて、惨めな気持ちで、泣き崩れてしまいたくなる時が 女性でもあるのか?。」と
胸が痛くなった。
--------------------------
(かおるさん。ごめんよ。勇気が無かった 僕の事を許してね。社長には色々と意見をしたかったのに、いつも 喉元までで止まり、言葉を飲み込むばかりで、守ってあげられなくて
ご免よ。) 闇夜の道に 何度も呟いていた。(叱られた彼女を、どうしたら守れたのだろうか?。)と 色々と 考えて歩いていた。
--------------------------
妄想。
「社長、彼女こそ、カウンターに入るべき人です。彼女が作ってくれた 賄いのスープを少し お裾分けしますから、試しに 味みして下さい。」「ほお、どれ。」「どうですか?、奥深い 素晴らしい味付けでしょう?。僕も かおるさんの味付けを参考にして、更に美味しい料理が出せるように精進します。裏技が
すごく勉強になるので、時には彼女が カウンターに入って 作るのを大目に見てくれませんか?。」「おおー‥。」
「僕の為に 自腹で買って来た食材で作ってくれたんです。社長にも 従業員の方々にも
味わい深い 賄い料理を 少しでも お裾分けして、仕事の励みにして頂けたら、とても嬉しい事です。」「おお そうか、うん、分かった。」(そんなふうに うまく展開してあげられなかったのか?。)と 悔やむばかりだった。
|