ポチよ、
泣かないで!。

----------------------------
祖母の遺志。
ゼンは、80歳まで、ほとんど病気知らずだったが、信(まこと)が、「左翼」に洗脳された頃から、次第に元気が無くなっていった。そして、今度は、「宗教」にかぶれた「まこと」を、みんなが寄ってたかってけなして、「できそこない!。」と、馬鹿にするので、ゼンは、これ以上、「まこと」のことを擁護することができなくなり、次第に言葉が少なくなった。
どんなことがあっても、ゼンだけは、最後まで、かばっていたが、家族のみんなに理解して貰えない、もどかしい思いが膨らみ、腹の中に、苦いものがあふれていった。 次第にゼンの腹には、黒い影が差していた。体調が悪くなり、お腹が少し膨れるようになった。 「まこと」が、教会に入って1年過ぎた頃、ゼンは、畑仕事も出来なくなった。
ある日、ゼンは、自分の余命があと幾ばくもない事を悟り、ある重大な覚悟を決めていった。そして、どうにかやっと、その準備が整い終わった時、急激に力が抜けていった。 もう、立っているだけで、つらくなり、やっとの思いで、病院にゆくことにした。
診察の結果、「即、入院」という事になり、すぐ「大手術」を施されたが、それから、急激に容態が悪化していった。
チカと「かづえ」が、交代で、ゼンの付き添いに通っていた。「おれは、今までチカさんに好きなことばかりさせて貰うて来て、ほんに幸せもんぞ…。もう、なーんも思い残す事は無かー。」 付き添いに来ていた「かづえ」に、ゼンは、しみじみと覚悟したように話すのだった。
ある日、チカは、ゼンに着替えを持って行ってあげようと思って、二階の姑のタンスを開けた。 だが、あれほどたくさんあった着物が一枚もなく、空っぽであった。 驚いて他の引き出しも次々に開けていったが、何も入ってなかった。 そして最後の引き出しに、ポツンと一つだけ、風呂敷に包まれたものが現われた。
胸騒ぎを感じて、急いで結びをほどくと、そこには喪服を着たゼンの遺影写真と、白い「死装束」がきれいにたたんで入れてあった。ゼンは、自分自身の死期が近いのを、既に予感して、何かの「願」をかけるように、きれいに身辺整理をしていたのだ。チカは姑のゼンの、死を迎える準備と覚悟に驚いてしまった。
やがて、「まこと」のもとに「祖母の危篤」の知らせがあった。「直方伝道所」に派遣されていた「まこと」は、かなりの時間が経ってから、その知らせを聞き、慌てて見舞いに行った。
だが、ゼンは、既に「抗ガン剤」を打たれて、激しい痛みで、体を「ガタガタ」と痙攣させて、苦しみもがいていた。
ゼンは、親族のみんなに見守られながら、何かを託すようにチカの名前を呼びながら亡くなっていった。「チカさん。…後のことは、頼みましたばい…。」
お通夜の夜、姉の「かづえ」が、遺体にすがり「ばあちゃん!ばあちゃん!。」と、激しく泣いていた。 「まこと」は、身を切られるように悲しかったが、自分のせいで、祖母が心を痛め、急速に体を病んでいった気がしていた。体を張って、「まこと」を逃がしてくれたゼンの姿を思い出していた。冷たく動かなくなった、ゼンの遺体を見ながら、とうとう恩返しも出来なかったことを、申し訳なく思った。
(ばあちゃん、ごめんよ、ごめんよ…。)と、心の中でつぶやいていた。 自分が「祖母」を死に追いつめた気がして、泣くわけにはいかなかった。(泣いちゃいけない!。泣くもんか…。)「まこと」は、平静を装い、涙をじっとこらえた。
横で、静かに立っている弟に気がつき、「かづえ」は、涙を拭きながら聞いた。「「まこと」は悲しくないの?。」 「まこと」は、強気で答えた。「人間は、…みんな、…いつか死んでゆくのさ…。」 その時、姉の表情が険しくなった。「何よ!「まこと」が、ばあちゃんに一番可愛がって貰っていたくせに!。」 「かづえ」は、「まこと」を激しくなじった。

「まこと」は、信仰するようになってから、(人間は、死んだら肉体を脱いで、魂は霊界に行くもの…。)と思い、肉身の別れが永遠の別れだとは思わなくなっていた。 ゼンの魂は、いつも自分の心に語りかけ、見守ってくれている感覚があった。そこに在るのは、ゼンの「抜け殻」だけだった。(ごめんよ、ごめんよ、おばあちゃん!今、何処にいるの…?。) 「まこと」は、目を閉じて、祖母の魂が、どこにいるのか捜した。
その時、ゼンの霊が、「まこと」を包み込んだ気配がした。脳裏に、ゼンの顔が現われた。(「まことー」…。よかよか、泣かんでよか。おれの事はもういいけん、自分の道をゆきなさい…。いつも見守ってあげるけんね。ばあちゃんは、もう地上では、お前のことを守れないことが判ったよ。これからは、霊界から、いつでも何処でも、飛んでいって、守ってあげるからね…。)心にそう語りかけると、「まこと」を包み込むように、背中に消えていった。
翌朝、ゼンの遺体には、「死に化粧」が施され、生前、大切にしていた物と一緒に、「棺」に入れられた。ゼンが良く唱えていた「般若心経」の「経本」も、ゼンの枕元に入れられた。やがて「棺」は、「火葬場」に運ばれ、火が点けられた。 みんなは、控え室に移動したが、「まこと」は、外に出て、煙突から上がる「煙」を、しばらく見ていた。だが、急に何かを感じて、一人だけ元の場所に戻って来た。
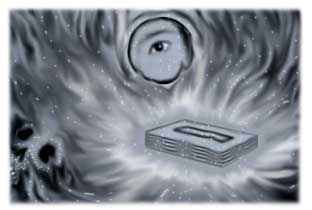
覗き穴から、ゴーと燃える「棺」の中を覗くと、下の方に「お経の本」がチラリと見えた。「お経」の周りだけ、「炎」が、よけて燃えていた。見えない力が「お経」から出ているのを、「まこと」は、不思議な思いで、しばらく見ていた。
1時間後、焼けた骨が出て来たが、あれだけの、強い炎の中でも、「経本」の周りが少し焦げただけで、「お経」の「文字」は、しっかりと燃えずに残っていた。みんなは、「不思議だね…。何かの念が入ってたんやろうね。」と話した。
「まこと」は一人、祖母の事を考えていた。あまりにも、あっけなく亡くなったゼンの、「死に際」の見事さに、何かを感じた。幼い主君に、最後まで忠誠を尽くして散った、「武士道精神」の、見事な心得のようなものを、見た思いがしていた。
----------------------------
東 京。
「まこと」が、教会に入って二年目、急に、「東京」への「人事移動」の話が持ち上がって来た。(これは、いい機会が出来たぞ…。) 「まこと」は、密かにそう思った。というのも、東京に行ったまま帰らない兄の「のりお」の消息を探すためにも(いずれ「東京」にゆかなければ…。)と、思っていたからだった。
「渋谷支部」に、ゆくことに決まったので、新たな「東京」の環境に移るのを機会に、そのまま、この組織から静かに抜け出す計画をたくらんでいた。 かすかな不安と希望を、胸に抱きながら、「東京」ゆきの汽車に乗った。
----------------------------
浮浪者。
初めて見た「東京」は、やたらに人が多く、高いビルが果てしなく立ち並ぶ、大都会だった。

省略。
密かに、教会を抜け出した「まこと」は、渋谷、池袋、新宿と、ゆく当てもなく、転々と移動した。ポケットには、わずか500円しかなかった。パン屋さんで、10円で紙袋一杯に入った「パンの耳」を買って、近くのビルの屋上でかじった。サンドイッチの「卵」が少し付いていて有り難かった。(さて、これからどうしようか…。)
夕方になると、雨が降って来た。 「まこと」は、近くのビルの屋上の階段の所で、寝袋に入って野宿した。 真夜中に、爆睡して眠っている「まこと」の足を、ポンポンと叩く人がいた。顔を出すと、二人の警察官が見下ろしていた。住人の誰かが、「不審な者が寝ている。死体かも知れない。」と、怖がって通報したらしい。
そのまま、派出所に連れていかれ、持ち物や、身元などを調べられた。 寝袋の他には、「教義の本」と、「数枚の写真」だけだった。 本籍地を調べあげると、「家に連絡していいかね?。」と、若い警官が聞いた。「家には、電話しないでください!。」 「まこと」は、母が心配することを恐れた。
「うーむ…、教会の青年なら、真面目な青年に違いない…。何か深い事情があって抜け出したのだろう…。」と、年配の人が心配して言った。「実は…、教会に疑問を感じて、抜け出す決意をしたんです。」 「まこと」は、正直に、ありのままを話した。
「君、このままじゃ、薄汚れて浮浪者になってしまうよ。アルバイトニュースでも買って、すぐ職を探して働きなさい。」 警官は「まこと」に5,000円を渡して解放してくれた。
(もっともだ…。) 「まこと」は、言われた通り、すぐ駅の売店でアルバイトニュースを買った。
パラパラとめくると、寮付きの比較的大きな旅行会館のホテルを見つけた。すぐに、その足で面接に行き、即決で、その寮に入ることになった。
----------------------------
10年の空白。
昼間は、ウエイター。夜は、喫茶店のカウンター。と、毎日、忙しく働いた。チーフに、中華料理の作り方を教えて貰い、いつしか、簡単な料理ぐらいは、作れるようになった。
寮には、九州出身の、学生達が何人かいて、次第に仲良くなり、色々なことを話したり、遊んだりして、楽しい2年間が、あっという間に過ぎていった。
教会の事は、すっかり忘れてしまおうとしていた。流される自分を感じていた時、(今のうちに、何かを身に付けなきゃ…。)と、次第にあせりを感じていった。
「まこと」は、久しぶりに「実家」に、音信のつもりで、年賀状を出した。
それから、何日かして、突然、姉の信子や、「かづえ」から、電話があった。「行方不明になっていた兄貴が、東京にいることが判ったよ。」
しばらくして、当の兄貴本人からの電話が入った。「世田谷の方で、独立してサッシの会社を自営している。」とのことだった。 「まこと」は、10年ぶりに兄の、「のりお」に逢って、ただ、ただ、懐かしかった。小学生の頃に別れたきりだった。
広い東京で、血のつながった兄弟が、薄暗いバス停の前で再会した。大きかった兄貴の体が、以外に小さく見えた。
しばらくして、「まこと」は、ホテルを辞め、兄の、「のりお」のいる街のほうに引っ越した。兄の仕事を手伝ったりしたが、次第に「10年の空白」が、いかに大きいかを感じていった。血を分けた兄弟なのに、判り合えない、他人のような、冷たい関係があった。
心の通わない、悲しさの中で、仕事を手伝いながらも、失望していった。(サッシ業は、自分に合う仕事ではない。ここは、自分の安住する場所ではない…。)と、感じると、やがて、ゆくのをやめた。
東京に来て、はや、3年が流れていた。自分に向く、職業が判らず、相変わらず、会社を転々としていた。 何処に行っても長続きせず、金がなくて、キャベツと、インスタントラーメンばかり食べていた。 いつしか、家賃も払えなくなり、再び、食事付きの職を探そう。と、なけなしのお金で、アルバイトニュースを買った。
偶然にも、下町の方に、「住み込みの、厨房の調理師見習い募集」の広告に目が止まった。「まこと」は、すぐ、そこに面接に行った。
----------------------------
仕事と恋愛。
小さな弁当屋だったが、「まこと」は、寮に入って、住み込みで働くことにした。人員が足らなかったのか、その日から、すぐ包丁を持たせてくれた。
毎日、大量の野菜や、魚などを切ったり、焼いたり、何百人分の量の、下ごしらえする調理場の仕事は、忙しかった。だが、食材を扱う手触りが、何とも言えない快感だった。
手が空くと、弁当箱にご飯をよそおう、「盛りつけ」の仕事を手伝った。そこでの、テキパキと、段取りをする訓練は、仕事に対する心構えと、「食材」を手で触れて、処理していく楽しさを、充分に味合うことができた。
今までに、感じたことのない、不思議な充実感があった。包丁使いも、めし盛りも、神技のように、素早くなっていた。 いつしか、「のろまの「まこと」が、「スピードの「まこと」。」と、呼ばれるようになっていた。

「ご飯盛り」を手伝うようになった時、そこに、長年勤めていた、「ひろこ」という、一回り年上の女性と、向かい合って、初めて言葉を交わした。彼女は「まこと」が入社してきてから、だんだんと慣れていく様子を、少し離れた所から、ずうーっと静かに見ていたのだった。
「まこと」は、すばやい速さで、ご飯を盛りながらも、冗談半分で、「今度、飲みに行きませんか…?。」と、誘って、そのまま忘れていた。
それから、何か月か経った。「ねえ、あんた、一体、いつになったら、私を飲みに連れて行ってくれるんだよー!。」 彼女は、しびれを切らしたのか、ふざけたふりして、ウインクして催促して来た。「まこと」は、彼女が本気で待っていたことを知って慌てた。
初めてのデートは、スナックだった。ほんのりと、酔いがまわった頃。「自分には、ある使命があって、いつか時が来たら、帰らなければならないんだ。」「へえー…。」 だが、彼女は、その意味が、何のことか判らなかった。
「まこと」は、ひろこの中に、だんだんと、母親のような、ぬくもりを覚えていった。今まで生きて来て、初めて人間同士の暖かさと、安らぎを感じていた。
ひろこは、母親と二人暮らしだった。彼女は、「まこと」の中に底知れぬ、深い孤独な影を感じとっていた。遠慮がちの「まこと」を、ある日、自分の住まいに連れて来て、まるで、昔から居た弟のように自然に導き入れてくれた。
その日を境に、砂漠のようだった、「まこと」の心を癒す愛の水が潤い、バラ色に輝く夢のような日々に変わっていった。
ある日、職場のおばさんが、「二人の相性は、ピッタリだよ。」と言った。男勝りのひろこと、内気でおとなしい、「まこと」とは、確かに、心が惹かれあっていた。
しばらくして、「まこと」は、弁当屋を辞めた。アパートを借りて、亀戸駅前の「喫茶店」に勤めるようになった。
コーヒーや、サンドイッチを作る、カウンターの仕事は、結構忙しかった。 午前中は、めまぐるしく忙しかったが、午後には客足が、パッタリと止まった。
何とか、お客の目を引こうと、湯気の立ったコーヒーカップの絵を描いて店の入口に貼った。 ポスターを工夫して描いているうちに、文字や絵を書くことが、とても面白いことに気がついた。(自分のやりたかった仕事はこれだ…。この仕事こそ、自分の「天職」だ…。) そう直感した、「まこと」は、本格的に、「レタリング」の通信教育を習い始めた。
時間を忘れて、文字やイラストを練習して描く夜が、毎日続いた。筆を持って熱中している時、何もかも忘れられる、充実した時間が流れていた。
東京に来て、ひろこに出逢ったことと、自分の「天職」を見つけたこと。この二つつが、「大きな恵みと、収穫」だった。 味気ない人間関係を、さまよって来た「まこと」が、ひろことの出逢いによって、ようやく生きる「勇気と自信」を取り戻そうとしていた。
----------------------------
小
説。
「ポチよ、
泣かないで!。」
青春編。 第2話。 おわり。
|