|
پ@
 پ@پ@‡Uپ@ پ@پ@‡Uپ@  پ@پ@ پ@پ@
‘و‚P•”پBپ@پ|پ@ƒ`ƒJڈC—ûژ‘مپBپ@
‘و‚Q•”پBپ|پ@ƒ`ƒJ’è’…ژ‘مپBپ@
پ@‘و‚R•”پBپ@پ|پ@ƒ`ƒJŒƒ“¬ژ‘مپBپ@
پ@پ@پ@
پ@‚¨‰ظژq‰®‚¾‚ء‚½گrژµ‚جٹè–]‚حپAé\“ھ‰®‚ج‘§ژq‚ج‚à‚ئ‚ة‰إ‚¢‚إچs‚ء‚½ƒ`ƒJ‚ة‚و‚ء‚ؤ‰ت‚½‚³‚ê‚é‚©‚ةŒ©‚¦‚½پB‚¾‚ھپA‚»‚جچ،ˆن‰ئ‚ج‚Q‘م–عپiگ³ٹىپj‚حپA“SچHڈٹ‚جژdژ–‚ةڈA‚¢‚ؤ‚¢‚ؤپAٹù‚ةژ«‚ك‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پué\“ھ‰®پv‚ج‰ئ‹ئ‚ة‚حپA‘S‚ٹضگS‚ھ–³‚©‚ء‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپA—¼‰ئ‚ج‚P‘م–ع‚ھ–³‚‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‰ئ‹ئ‚ً—§‚ؤ’¼‚·ڈd—v‚بˆت’u‚ة‚¢‚½‚ھپA‚»‚ج‚±‚ئ‚ة‹C‚ھ•t‚©‚¸‚ة‚¢‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚à•sژv‹c‚ئپA‰ئ‹ئ‚ًŒp‚®‹C‚ھ‘S‚–³‚©‚ء‚½پBپ@‚à‚ح‚âپA‰ئ‹ئ‚ًŒp‚®‚à‚ج‚حپAگي’n‚ةچs‚ء‚½ژں’jپi–Fٹىپj‚µ‚©‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@نn‚جٹى•½‚حپA–Fٹى‚ةٹْ‘ز‚ً‚©‚¯‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپA–Fٹى‚حگي’n‚©‚ç•a‹C‚ة‚ب‚ء‚ؤ“ْ–{‚ة‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚à‘©‚جٹشپA•a‰@‚إ‘§‚ًˆّ‚«ژو‚ء‚ؤژ€‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚¤پB
پ@‚à‚ح‚âپA’N‚à‰ئ‹ئ‚ًŒp‚®ژز‚ھ‹ڈ‚ب‚‚ب‚ء‚½’†‚إپAپué\“ھپv‚ًچى‚铹‹ï‚¾‚¯‚ھپAڑ؛‚ً‚©‚ش‚ء‚ؤ–°‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ج•”‰®‚ج‰،‚ة‚حپA‚»‚ê‚ً”ك‚µ‚°‚ةŒ©‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚بپAپu–Fٹىپv‚جˆâ‰e‚جژتگ^‚ھ‚ذ‚ء‚»‚è‚ئ’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚ ‚é“ْپAنn‚جٹى•½‚حپAپuŒp‚®‹C‚ھ‚ ‚é‚ب‚çپA‹³‚¦‚ؤ‚â‚é‚©‚çپA‚â‚ء‚ؤ‚ف‚ب‚¢‚©پHپBپv‚ئپA‰ئ‹ئ‚جچؤŒڑ‚جٹè‚¢‚ًپAƒ`ƒJ‚ة‘ُ‚»‚¤‚ئ‚·‚é‚ھپAƒ`ƒJ‚حپA‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚à‹C‚ھگi‚ـ‚ب‚©‚ء‚½پBپ@پu‚¤‚؟‚ح‚â‚é‹C‚ح‘S‚‚ب‚¢‚إ‚·پBپv‚ئپA‚«‚ء‚د‚è‚ئ’f‚ي‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB
پ@’I‚©‚çگU‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚و‚¤‚بپAپi‚ع‚½ƒ‚ƒ`پj‚ج‚و‚¤‚ةپA“ث‘RپA—^‚¦‚ç‚ꂽژg–½‚ًپA‚¤‚©‚آ‚ة‚à‹‘”غ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½ژپAƒ`ƒJ‚ج‘O‚ة‹P‚±‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پA–¢—ˆ‚جŒُ‚ح—ح‚ًژ¸‚¢پA‚ف‚é‚ف‚邤‚؟‚ةˆأˆإ‚ة‘ض‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پBپ@‚»‚جژ‚©‚çپAƒ`ƒJ‚حپAپuژR‚إ‚ج‹êکJپv‚ئپAپuٹُ‚ـ‚ي‚µ‚¢“¬‚¢پv‚ً‹‚¢‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ@پuŒُ‚ج“¹‚ً”ُ‚¦‚وپIپBپv‚ئ‚¢‚¤ˆê‘م–ع‚ج‰ئŒP‚ً—§‚ؤ’¼‚·‚½‚ك‚ة—ˆ‚½ƒ`ƒJ‚ھپA–°‚ء‚ؤ‚¢‚½ڈغ’¥‚جپu‰ئ•َپv‚ةپAŒُ‚è‚ً“–‚ؤ‚邱‚ئ‚ًپAژ©‚ç‚جˆسژu‚إ‹‘‚فپA‚»‚جژg–½‚ًڈ°‰؛‚ة–°‚点‚½‚ـ‚ـپA••ˆَ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پBŒ‹‰ت“I‚ةپA‚±‚جƒ`ƒJ‚جپu’è’…ژ‘مپBپv‚حپAژ…“‡‚ج’n‚ةپA’|‚ج‚و‚¤‚ةگ[‚چھ‚ً’£‚ء‚ؤ‚ن‚«پA–³‚‚µ‚½پuŒُ‚ج“¹پBپv‚ًپAچؤ‚ر—§‚ؤ’¼‚µ‚ب‚ھ‚çپAژO‘م–ع‚جپuژہ‘ج“IکH’ِپv‚ةپA‚آ‚ب‚®‚½‚ك‚جپAپu’†ٹشکH’ِپBپv‚ة‚à‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚پB
پ@’·•ز پu پu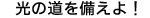 پv پv
پ@پ@پ@پ@‡AپA پ@ پ@
پ@پ@پ›‘و“ٌ•”پBپiƒ`ƒJ’è’…ژ‘مپBپj
پ@پ@پ@‚ ‚ç‚·‚¶پB
پ@ˆأچ•‚ج’n‚©‚甲‚¯ڈo‚µپA—خ‚ئŒُˆى‚ê‚éپuژ…“‡پv‚ج’n‚ة‰إ‚¢‚إ—ˆ‚½ƒ`ƒJ‚¾‚ء‚½‚ھپAŒ‹چ¥ژ®‚جژ‚©‚çپA‚»‚جŒم‚جگlگ¶‚ًˆأژ¦‚·‚é‚©‚ج‚و‚¤‚بپA”g—گ‚أ‚‚ك‚جڈo”‚ھژn‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚پB
پ@ƒ`ƒJ‚ھپAچ،ˆن‰ئ‚ج‰إ‚ئ‚µ‚ؤ‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚½ژپA•v‚ج’يپi–Fٹىپj‚جژp‚حŒ©‚¦‚ب‚©‚ء‚½پBپ@ٹù‚ةڈ\کZچخ‚إپAپu‹`—EŒRپv‚ج•؛ژm‚ئ‚µ‚ؤپu–ڈBپv‚ةڈoگھ‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½Œم‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤپA•a‹C‚ة‚ب‚ء‚ؤ“ْ–{‚ة‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ھپAپiŒ³‹C‚ة‰ٌ•œ‚µ‚½‚çپA‰ئ‚ة‹A‚ء‚ؤپA‰ئ‹ئ‚جپué\“ھ‰®پv‚ًŒp‚¬‚½‚¢پcپBپj‚ئپA‰÷‚â‚ف‚ب‚ھ‚ç‚àپA‹}‘¬‚ة•aڈَ‚حˆ«‰»‚µ‚ؤ‚ن‚«پA‚»‚جٹè‚¢‚ًژc‚µ‚½‚ـ‚ـپA‰“‚¢—¤ŒR•a‰@‚جˆêژ؛‚إپA‚ئ‚¤‚ئ‚¤—حگs‚«پA–½‰ت‚ؤ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB
پ@‚»‚جپA–Fٹى‚ج–³”O‚جچ¦‚ف‚حپAچ،ˆن‰ئ‚ة‰إ‚¢‚إ—ˆ‚½ƒ`ƒJ‚ئپA‚»‚ج‚ ‚ئگ¶‚ـ‚ꂽژq‹ں‚½‚؟‚ة”w•‰‚ي‚³‚ê‚ؤ‚¢‚پB‚»‚ج”Oٹè‚حپAŒ³پAپu‚¨‰ظژq‰®‚ج–؛پv‚¾‚ء‚½پAƒ`ƒJ‚ة‚و‚ء‚ؤژہŒ»‚³‚ê‚é‚©‚ةŒ©‚¦‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپAنn‚©‚çپAپué\“ھ‰®‚جژdژ–‚ً‚·‚é‹C‚ھ‚ ‚é‚ب‚狳‚¦‚ؤ‚â‚é‚©‚çژn‚ك‚ب‚¢‚©پHپBپv‚ئŒ¾‚ي‚ê‚é‚ھپA’f‚ي‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پBپ@پ@ƒ`ƒJ‚ة‚ئ‚ء‚ؤپAپu‚¨‰ظژq‰®پv‚àپAپué\“ھ‰®پv‚àپA“¯‚¶—l‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@‹êکJ‚جٹ„‚ة‚حپA–ׂ©‚ç‚ب‚¢ڈ¤”„‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًپAٹù‚ةŒ™‚ئ‚¢‚¤‚ظ‚اپA‘جŒ±‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB‚¾‚ھپAƒ`ƒJ‚حپA‚»‚ê‚ً’f‚ي‚ء‚½ڈuٹش‚©‚çپAچذ‚¢‚ئ‹ê‚µ‚ف‚ج“¹‚ً•à‚¢‚ؤ‚ن‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB
پ@‚»‚ê‚حپAƒ`ƒJ‚ھ—§‚ؤ’¼‚³‚ث‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پAپu“¬‚¢پv‚جژn‚ـ‚è‚إ‚à‚ ‚ء‚½پB
پ@نn‚àŒئ‚àپA‰ئ‹ئ‚جپué\“ھ‰®پv‚ھ‚¤‚ـ‚‚¢‚©‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚©‚ç‚حپAگeگت‚©‚çژR‚ً”ƒ‚ء‚ؤˆîچى‚ًڈ‰‚ك‚½‚خ‚©‚è‚إ‚ ‚ء‚½پB‚ف‚ٌ‚بˆîچى‚جژdژ–‚حپA•t‚¯ڈؤ‚«گn‚ف‚½‚¢‚ب‚à‚ج‚إپA‚ب‚©‚ب‚©“éگُ‚ك‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@”ژ‘½‚جپAژG“¥‚إ‚جگ¶ٹˆ‹ê‚ًپA‘جŒ±‚µ‚ؤ—ˆ‚½ƒ`ƒJ‚ة‚ئ‚ء‚ؤپA‰¸‚â‚©‚بژR‚ئٹC‚ةˆح‚ـ‚êپA‚ا‚±‚©پA‚ج‚ٌ‚ر‚肵‚½“cژة‚ج•é‚炵‚حپAˆظژںŒ³‚جگ¢ٹE‚ة“ü‚èچ‚ٌ‚¾‚و‚¤‚بپA‘u‚â‚©‚بٹ´ٹo‚ھ‚ ‚ء‚½پBپ@•v‚ھپAپu“SچHڈٹپv‚ةڈo‚©‚¯‚½ŒمپAˆêگlژو‚èژc‚³‚ꂽƒ`ƒJ‚ةپAگV‚µ‚¢“¬‚¢‚ھژn‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚پB
پ@ˆîچى‚ج‘جŒ±‚ج‚ب‚¢ƒ`ƒJ‚ة‚حپAژR‚إ‚جژdژ–‚حپA‰½‚à‚©‚àŒثکf‚¤‚±‚ئ‚خ‚©‚è‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@‚»‚ٌ‚ب—lژq‚ًپAŒ©‚ؤ‚¢‚½Œئ‚حپAپi‚ا‚¤‚¹”ژ‘½‚©‚ç—ˆ‚½‰إ‚³‚ٌ‚â‚©‚çپcپBپj‚ئپA“–‚ؤ‚ة‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@‚و‚»ژزˆµ‚¢‚ً‚³‚ê‚ب‚ھ‚ç‚àپA–ظپX‚ئ”_‰ئ‚جژdژ–‚ًˆêگ¶Œœ–½‚ةٹo‚¦‚ؤ‚¢‚ء‚½پBچ،ˆن‰ئ‚جگl‚ة‚àپA‹كڈٹ‚âژü‚è‚جگl‚½‚؟‚ة‚àپAژn‚ك‚حپAپu“s‰ï‚©‚ç—ˆ‚½‚¨‚ئ‚ب‚µ‚¢‰إپBپv‚ئ‚µ‚ؤŒ©‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
پ@“s‰ï‚جگl‚ئپA“cژة‚جگl‚ئ‚جپA•¨‚جچl‚¦•û‚جˆل‚¢‚©‚ç—ˆ‚éپAŒë‰ً‚âپAگS‚ج”÷–‚ب‚·‚êˆل‚¢‚ًٹ´‚¶‚½‚ـ‚ـپA‰إ‚ئŒئ‚جپAگأ‚©‚ب‚铬‚¢‚àژn‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@ڈoژYپAˆçژ™پA‚»‚µ‚ؤپAˆîچى‚جپAگh‚‚«‚آ‚¢ژdژ–پAŒƒ‚µ‚¢ƒXƒgƒŒƒX‚ج’†‚إپAپiچ،ˆن‰ئ‚ة“éگُ‚ٌ‚إ‚¢‚±‚¤پcپBپj‚ئپA–³—‚ًڈd‚ث‚ؤ‚ن‚‚ھپAˆêژٹْپAگS‚ئگg‘ج‚جƒoƒ‰ƒ“ƒX‚ًپA‚·‚ء‚©‚èژ¸‚¢پAگQچ‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚¤پB
پ@
پ@‚¾‚ھپAنn‚½‚؟‚ھژھ‚¢‚½ژي‚ھپA‚â‚ھ‚ؤƒ`ƒJ‚½‚؟‚ج‘م‚ةپA‘ه‚«‚ب–â‘è‚ئ‚ب‚ء‚ؤگU‚è‚©‚©‚éژپAƒ`ƒJ‚ح‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚àپAˆê‰ئ‚ج–î–ت‚ة—§‚½‚³‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚پB
پ@ژںپX‚ئڈP‚¢‚©‚©‚éپA“ï‘è‚ً‰ًŒˆ‚µ‚ؤ‚¢‚“x‚ةپA”é‚ك‚ؤ‚¢‚½پAƒ`ƒJ‚ج–{—ج‚ھ”ٹِ‚³‚ê‚éپB
پ@‚â‚ھ‚ؤپAژq‹ں‚ھˆç‚ء‚ؤ‚¢‚‚ة‚آ‚ê‚ؤپA‰إ‚ئ‚µ‚ؤ‚جپAژ©•ھ‚جژg–½‚ة–عٹo‚كپAژں‘و‚ة”_‰ئ‚ج‰إ‚ئ‚µ‚ؤ‚جژ©گM‚ًڈں‚؟ژو‚ء‚ؤ‚¢‚پBپ@پ@‚»‚ج’n‚ةگج‚©‚ç“`‚ي‚éچص‚âپA“cژة‚ج‚µ‚«‚½‚è‚â“`“‚ئ•—ڈKپA‚»‚µ‚ؤپAˆîچى‚جژdژ–‚ب‚ا‚àپA‚ظ‚عپAٹ®‘S‚ةٹo‚¦‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@–ˆ“ْپAژR‚ة“o‚èپA‚«‚آ‚¢ˆîچى‚جژdژ–‚ً‘±‚¯‚ؤ‚¢‚‚¤‚؟پAƒ`ƒJ‚جگg‘ج‚حپA•a‹C‚ة•‰‚¯‚ب‚¢پAڈن•v‚ب‘ج‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚پBپ@‹C‚ھ•t‚‚ئپAƒ`ƒJ‚حپA‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©پA‚ا‚ٌ‚بن…“ï‚ھ–K‚ê‚ؤ‚à•‰‚¯‚ب‚¢پA‹گx‚بگ¸گ_—ح‚ئپAç—‚µ‚¢“x‹¹‚ً‚àگg‚ة•t‚¯پAچX‚ةˆê‘wپA–پ‚«‚ھ‚©‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
پ@—َ•—‚ھ‰½“x‚àگپ‚¢‚ؤ—ˆ‚ؤ‚àپA’|‚ج‚و‚¤‚ةƒTƒ‰ƒTƒ‰‚ئ‰¹‚ً‚½‚ؤ‚ؤپA‚µ‚ب‚â‚©‚ة—h‚ê‚ب‚ھ‚çپA‚³‚ء‚د‚è‚ئ‚µ‚½گ«ٹi‚إپAگأ‚©‚ةپA’n’†گ[‚پAچھ‚ً’£‚è‚ب‚ھ‚çپA’è’…‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@پiژE‹غچى—p‚ًژ‚آ’|‚حپA‚»‚ج’†‚ةگ´‚ك‚ç‚ꂽگ¹‚ب‚é‹َٹش‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚éپBپj
پ@
پ@ƒ`ƒJ‚حپAچ،ˆن‰ئ‚ة‰إ‚¬پA’|‚ج‚و‚¤‚ةگ¹•ت‚³‚ꂽ‹َٹش‚ًچى‚éژg–½‚ھ‚ ‚ء‚½پB‚»‚جچ ‚©‚çپAƒ`ƒJ‚ًچX‚ةژژ—û‚ً‚·‚é‚©‚ج‚و‚¤‚ةپA•sژv‹c‚بƒgƒ‰ƒuƒ‹‚ھ‰½Œج‚©پA‚½‚ر‚½‚ر”گ¶‚µ‚ؤ—ˆ‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ@‚¾‚ھپAƒ`ƒJ‚حپAگU‚èٹ|‚©‚éچذ‚¢‚©‚çپAژR‚ج–ط‚âپA‰ئ‘°‚½‚؟‚ًژç‚邽‚ك‚ةپAپu“cŒû‰ئپv‚©‚çژَ‚¯Œp‚¢‚¾پA’q—ھ‚ًڈ\•ھ‚ة”ٹِ‚µ‚ب‚ھ‚çپA‘Sگg‘S—ى‚ج‹C—ح‚ئپA’mŒb‚ً‚©‚¯‚ؤپAپuڈh–½‚ج“¬‚¢‚ج“¹پBپv‚ة’§‚ٌ‚إ‚ن‚‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ@‚»‚جپA‘وˆê‚ج“¬‚¢‚حپAپuچ،ˆن‰ئپv‚ة—^‚¦‚ç‚ꂽپA‚¨ژ›‚جڈم‚ةˆت’u‚·‚éژR‚جپiˆîپA–طپAگ…پA‹«ٹEپj‚ةٹض‚·‚鑈‚¢‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@‘و‚Q•”پ@پiƒ`ƒJ’è’…ژ‘م‚ج‚ ‚ç‚·‚¶پBپj
’†پ@پ@—ھپB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@‚»‚جŒمپAˆâچœ‚حٹC‚جŒ©‚¦‚é”[چœ“°‚ة”[‚ك‚ç‚êپAگي‘ˆ‚ھڈI‚ي‚ء‚ؤ‚©‚ç‚إ‚ ‚é‚ھپAپu‰p—ىپv‚ًگأ‚ك‚éپu’‰—ى“ƒپv‚ھپAپuچ،ˆن‰ئپv‚ج‚·‚®— ‚جپAژR‚ةŒڑ‚ؤ‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚پB
پ@پu–Fٹىپv‚جˆâ‰e‚حپA‚QٹK‚ة’u‚©‚ꂽپB‚»‚جژتگ^‚ج–ع‚حپAڑ؛‚ً”ي‚ء‚½پué\“ھپv‚ًچى‚铹‹ï‚ًپA”ك‚µ‚°‚ةŒ©‚آ‚ك‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ة‚ف‚¦‚½پBپ@پu–Fٹىپv‚ج—ى‚حپAگي‘ˆ‚ھڈI‚ي‚ء‚ؤ‚©‚ç‚àپAپu’‰—ى“ƒپv‚ئپAپu”[چœ“°پv‚ئپAپuچ،ˆن‰ئپv‚جپA‚R“_‚ًŒ‹‚ش‹َٹش‚ًپA‚¢‚آ‚ـ‚إ‚àپA‚³‚ـ‚و‚¢•Y‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚»‚µ‚ؤپAپi‚QٹK‚جپuڈ°‚جٹشپv‚ة’u‚¢‚ؤ‚ ‚éژتگ^پBپj‚©‚çپA‚¶‚ء‚ئƒ`ƒJ‚جژq‹ں‚½‚؟‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›‚¹‚ء‚©‚؟پB
پ@ژv‚¢چ‚ف‚جŒƒ‚µ‚¢ƒ[ƒ“‚حپAپiƒ`ƒJ‚ھپAژ©•ھ‚ً“Vچ‘‚©‚ç’nچ–‚ةپA‚آ‚«—ژ‚ئ‚·‚½‚ك‚ةپAپu–Fٹى‚³‚ٌ‚ھ‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پBپv‚ئˆ«ˆس‚ًژ‚ء‚ؤŒ¾‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پBپj‚ئژv‚¢چ‚فپA‰½‚©‚ئŒ¾‚¤‚ئپAگh‚“–‚½‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@ƒ[ƒ“‚حپAƒ`ƒJ‚ًپuچ،ˆن‰ئپv‚جگlٹش‚ئژv‚ي‚¸پA‚و‚»ژزˆµ‚¢‚ة‚µ‚ؤژَ‚¯“ü‚ê‚ب‚©‚ء‚½پB‰½‚©ˆسŒ©‚ھˆل‚ء‚ؤŒ–‰ـ‚·‚é‚ئپAپu‚ا‚¤‚¹‚ ‚ٌ‚½‚ح‚و‚»‚جگlٹش‚½‚¢پIپvپu‚¤‚؟‚ج‹Cژ‚؟‚ب‚ٌ‚ؤ”»‚ç‚ٌپIپBپv‚ئ• ‚ً—§‚ؤ‚é‚ج‚¾‚ء‚½پB
پ@Œû•ب‚ج‚و‚¤‚ة‚¢‚¤ƒ[ƒ“‚جŒ¾—t‚ةپAƒ`ƒJ‚ح‚µ‚خ‚µ‚خ“–کf‚³‚¹‚ç‚ꂽپBپ@‚»‚ê‚إ‚àƒ`ƒJ‚حŒئ‚جƒ[ƒ“‚ة‚حŒˆ‚µ‚ؤ”½چR‚µ‚ب‚©‚ء‚½پBپ@‚ا‚ٌ‚ب—•sگs‚ب‚±‚ئ‚ًŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚àپA–ظ‚ء‚ؤ‰½‚àŒ¾‚ي‚ب‚©‚ء‚½پB–ع‚ًگ^‚ءگش‚ةژ‚ب‚ھ‚çپA‰A‚إ—ـ‚®‚ف‚ب‚ھ‚ç‘د‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚»‚جŒمپA‚»‚ٌ‚ب•ê‚ج‹ƒ‚«ژî‚炵‚½ٹç‚ًپA‚â‚ھ‚ؤگ¶‚ـ‚ê‚ؤ—ˆ‚éŒZ‚ج‹I’j‚ح‰½“x‚àŒ©‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚پBپ@’ي‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚àپA•ê‚ھŒئ‚ج‚±‚ئ‚إپA•ƒ‚ة‰½‚©‘ٹ’k‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚«پAپu‚¨‘O‚ھˆ«‚©‚ء‚؟‚ل‚낤‚à‚ٌپIپBپv‚ئ•ƒ‚ةŒ¾‚ي‚ê‚ؤپAژ‚ء‚ؤچs‚ڈêڈٹ‚ً–³‚‚µپAŒ¾—t‚ًژ¸‚ء‚ؤ‹ƒ‚«‚¾‚µ‚»‚¤‚بٹç‚ج•ê‚ًٹo‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@ƒ[ƒ“‚حپA‚µ‚خ‚µ‚خ‘پ‚ئ‚؟‚è‚ً‚µ‚ؤ‚حپA‘ه•د‚بژv‚¢ˆل‚¢‚ً‚·‚é‚ئ‚±‚ë‚ھ‚ ‚ء‚½پBˆê“xƒ[ƒ“‚ھ‚©‚ٌ‚µ‚ل‚‚ً‹N‚±‚·‚ئپAƒ`ƒJ‚جŒ¾‚¢–َ‚ب‚ا‘S‚ژ¨‚ة“ü‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB‚³‚ٌ‚´‚ٌƒ`ƒJ‚ةŒ¾‚¢‚½‚¢‚±‚ئ‚ً‚ح‚«ژج‚ؤ‚ؤپAپuƒvƒCƒbپv‚ئٹO‚ة”ٍ‚رڈo‚µ‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤ”¨ژdژ–‚ً‚µ‚ؤ‹A‚ء‚ؤ‚‚é‚ئپAƒ[ƒ“‚حپA‚à‚¤Œ–‰ـ‚µ‚½‚±‚ئ‚ب‚ا‚·‚ء‚©‚è–Y‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپAپuƒ`ƒJ‚³‚ٌپI‘هچھ‚ھ‘ه‚«‚ˆç‚ء‚ئ‚ء‚½‚خ‚¢پIپv‚ئ–¾‚é‚پA‚‚ء‚½‚‚ب‚¢’²ژq‚إکb‚µ‚©‚¯‚ؤ—ˆ‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚ج•û‚ح‚³‚ٌ‚´‚ٌŒ¾‚ي‚ê‚ء‚د‚ب‚µ‚إپA‰÷‚µ‚¢‹Cژ‚؟‚ً‰½‚ئ‚©‚µ‚و‚¤‚ئپAŒë‰ً‚ً‰ً‚‚½‚ك‚جŒ¾—t‚ًˆêگ¶Œœ–½‚ةچl‚¦پAپi‚ا‚¤Œ¾‚ء‚½‚ç”»‚ء‚ؤ–ل‚¦‚é‚ج‚¾‚낤‚©پHپcپBپj‚ئگS‚ًچس‚¢‚ؤپAڈ€”ُ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚ةپA‚¢‚ئ‚àٹب’P‚ةŒ¨“§‚©‚µ‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚¾‚ء‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپA‚ ‚ء‚¯‚ç‚©‚ٌ‚ئکb‚·ƒ[ƒ“‚ًŒ©‚ب‚ھ‚çپAپi’{گ¶پ\پcپj‚ئ“àگSژv‚¢‚ب‚ھ‚ç‚àپAŒ¾‚¢‚½‚¢‚±‚ئ‚ًŒ¾‚ء‚ؤپA‚·‚®–Y‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پA‚¢‚آ‚ـ‚إ‚àچھ‚ةژ‚½‚ب‚¢“Vگ^ࣖں‚بŒئ‚ھ‘A‚ـ‚µ‚‚à‚ ‚ء‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤƒ`ƒJ‚حپAŒئ‚جƒ[ƒ“‚ئ‚¢‚¤گl‚حپAژv‚¢چ‚ف‚ھŒƒ‚µ‚¢‚ئ‚±‚ë‚ھ‚ ‚é‚ھپAڈƒگˆ‚ب“cژة‚جگS‚ًژ‚ء‚½گl‚إپAڈç’k‚إŒ¾‚ء‚½گl‚جŒ¾—t‚à‚»‚ج‚ـ‚ـگM‚¶‚ؤگ^‚ةژَ‚¯‚éپAگ^‚ء’¼‚®‚بگl‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ً’m‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ@پu‹ى‚¯ˆّ‚«‚ب‚µ‚إپA‚»‚جڈê‚»‚جڈê‚إژ©•ھ‚جٹ´ڈî‚ًڈo‚µ‚ؤ”ژU‚·‚éپA• ‚ة— ‚ج–³‚¢ƒJƒ‰ƒb‚ئ‚µ‚½گ«ٹi‚ب‚ج‚¾پv‚ئپAژں‘و‚ة‚¨”k‚؟‚ل‚ٌ‚ج‘f–p‚³‚ة‹C‚ھ•t‚«ژn‚ك‚ؤ‚¢‚پB
پ@‚»‚µ‚ؤƒ`ƒJ‚حپA‚»‚ٌ‚ب“TŒ^“I‚ب“cژةگl‚إ‚ ‚éپAŒئ‚ة‘خ‚·‚é‘خڈˆ‚جژd•û‚ًپAژں‘و‚ةڈو‚èگط‚é’mŒb‚ً—{‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–S‚‚µ‚½ژq‹ںپ@
پ@نn‚جٹى•½‚ح‰ئ‹ئ‚ًŒp‚®”¤‚¾‚ء‚½‘§ژq‚جژ€‚ًٹإژو‚ء‚ؤ‚©‚çپA‹}‘¬‚ةکV‚¯چ‚ٌ‚إ‚¢‚ء‚½پB
ژ©•ھ‚جŒمŒpژز‚ًŒ©‚邱‚ئ‚ب‚پA–³”O‚جژv‚¢‚ًژc‚µ‚½‚ـ‚ـپA‚â‚ھ‚ؤگأ‚©‚ةژR‚جڈم‚إژ€‚ٌ‚إ‚¢‚ء‚½پB
پ@‚»‚ê‚©‚çپA•¶ژq‚⃀ƒcژq‚½‚؟ڈ¬Œئ‚½‚؟‚àپA‰ڈ’k‚ھŒˆ‚ـ‚ء‚ؤپAژںپX‚ئ”ژ‘½‚ج•û‚ة‰إ‚¢‚إ‚¢‚ء‚½پB‹C‚ھ•t‚‚ئƒ[ƒ“‚ئƒ`ƒJ‚ئ“ٌگl‚¾‚¯‚إ”_چى‹ئ‚ً‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚حپA‚»‚ٌ‚ب’†‚إگ³ژq‚ئ‹I’jپAژ ژq‚ئژںپX‚ةژq‹ں‚ًگ¶‚ٌ‚¾پBنn‚ھ‚¢‚ب‚‚ب‚ء‚ؤپA’jژè‚ھ–³‚‚ب‚ء‚½•ھپAˆêگl‚إ”_چى‹ئ‚ً‚·‚éƒ[ƒ“‚ًژx‚¦‚邽‚ك‚ةپA—حژdژ–‚àژل‚¢ƒ`ƒJ‚ھ‘م‚ي‚ء‚ؤ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚‚ب‚ء‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپAژR‚ج‚ ‚؛“¹‚ةپA‚ق‚µ‚ë‚ً•~‚«پA‚ـ‚¾ڈ¬‚³‚¢گ³ژq‚½‚؟‚ًچہ‚点‚ؤپA‚¢‚آ‚à’ا‚ي‚ê‚é‚و‚¤‚ة“‚¢‚ؤ‚¢‚½پB‚ـ‚¾‚ ‚ا‚¯‚ب‚¢ژq‹ں‚½‚؟‚ةپA‚©‚ـ‚ء‚ؤ‚ ‚°‚ç‚ê‚ب‚¢ڈَ‘ش‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@گيژ‘جگ§‚إپAگH—؟‚àڈ[•ھگH‚ׂç‚ê‚ب‚¢پA•n‚µ‚¢گ¶ٹˆ‚ج’†‚إپAژq‹ں‚½‚؟‚حŒ³‹C‚ة—V‚ٌ‚إ‚¢‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚½پB‚¾‚ھپAƒ`ƒJ‚ج–ع‚ھچs‚«“ح‚©‚¸پA–û’f‚µ‚½Œ„‚ةپA‰h—{ژ¸’²‚ئپA—¬چs•a‚إگ³ژq‚àژ ژq‚àپAژںپX‚ئژ€‚ٌ‚إ‚¢‚ء‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپA‚±‚ج“ٌگl‚جڈ—‚جژq‚ج‰آˆ¤‚炵‚©‚ء‚½‚µ‚®‚³‚ً‚¢‚آ‚ـ‚إ‚à–Y‚ê‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@–Z‚µ‚¢•êگe‚ً‹C‚أ‚©‚ء‚ؤپAˆêگl‚إ‹ڈ‚ؤ‚à‚¨‚ئ‚ب‚µ‚—V‚ٌ‚إ‚¢‚½پAژè‚ج‚©‚©‚ç‚ب‚¢Œ«‚¢ژq‚¾‚ء‚½پBƒ`ƒJ‚ھ‹C‚ھ‚آ‚¢‚½ژپAڈ¬‚³‚ب–؛‚جگg‘ج‚ھ—₽‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚»‚جژp‚ًŒ©‚½ژپA‚ ‚ـ‚è‚à•sœà‚إ‚©‚ي‚¢‚»‚¤‚إ‚ب‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB•êگe‚ئ‚µ‚ؤپA‰½‚à‚µ‚ؤ‚ ‚°‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‰÷‚µ‚‚ؤپA—ـ‚ھ—¬‚ê‚ؤژ~‚ـ‚ç‚ب‚©‚ء‚½پBپu‚²‚ك‚ٌ‚وپAگ³ژqپA‚²‚ك‚ٌ‚وپ[پBپvپ@‚¢‚آ‚ـ‚إ‚àژ©•ھ‚ًگس‚ك‚ؤ‚خ‚©‚è‚¢‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚حپAˆêژٹْپAژq‹ں‚ًˆç‚ؤ‚邱‚ئ‚ةپAژ©گM‚ً‚·‚ء‚©‚è–³‚‚µ‚©‚¯‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤپAگي‘ˆ‚ھڈI‚ي‚èپAچ‘–¯‚حپuŒRچ‘ژه‹`پv‚ج–S—ى‚©‚çٹJ•ْ‚³‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB‚¾‚ھپAƒAƒپƒٹƒJ‚ة‚و‚éپu‰ً•ْگچôپv‚إپA•½کa‚بژ‘م‚ھ–K‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚جپA‘½‚‚جچ‘–¯‚حپA•n‚µ‚³‚ج‚ا‚ٌ’ê‚ةڑb‚¬‚ب‚ھ‚çپA‚·‚®‚ة‚ح—§‚؟’¼‚ꂸپAˆêŒü‚ة•é‚炵‚حپAٹy‚ة‚ح‚ب‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@‚و‚¤‚â‚پAگيŒم‚ج‹‡–Rڈَ‘ش‚©‚çپA”²‚¯ڈo‚»‚¤‚ئ‚·‚éژپA‚â‚ء‚ئژq‹ں‚½‚؟‚àپA‰½‚ئ‚©–³ژ–‚ةˆç‚آ‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پBپ@’·’j‚ج‹I’j‚ج‚ ‚ئپAگMژq‚ئکaچ]‚ھگ¶‚ـ‚êپA‚»‚µ‚ؤچإŒم‚ةپA––‚ءژq‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚ھگ¶‚ـ‚ꂽپB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒX‚¢‚½ژRڈ¬‰®پB
پ@ٹى•½‚ھپA–S‚‚ب‚ء‚ؤ‚©‚çپAƒ[ƒ“‚حپAˆêگlژc‚³‚ꂽپB‚»‚ê‚إ‚àˆêگl‚إپAژR‚ج‰ئ‚ةڈZ‚ٌ‚إ‚¢‚½پB
پ@ٹى•½‚ھگ¶‚«‚ؤ‹ڈ‚½چ ‚حپA‚»‚ٌ‚ب‚ةٹ´‚¶‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA’N‚à‚¢‚ب‚¢پAگأ‚©‚ب–é‚جژR‚حپA‰½‚©ƒIƒoƒP‚إ‚àڈo‚ؤ—ˆ‚»‚¤‚إپA•s‹C–،‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@ٹش–é’†‚ةپuƒKƒTƒbپAƒKƒTƒbپIپv‚ئپAگl‚ج‹C”z‚ھ‚·‚é‚ئپAچ،‚ة‚àڈP‚ي‚ê‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئپA‹°‚낵‚‚ؤگQ‚ؤ‚¢‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½پBپ@ƒ[ƒ“‚حپA•|‚‚ب‚ء‚ؤپAˆêگl•é‚µ‚ً‚·‚éپA—c“éگُ‚ف‚ج—F’B‚ًŒؤ‚ٌ‚إ‚حپA‚µ‚خ‚炈êڈڈ‚ة•é‚炵‚ؤ‚¢‚½پB
پ@ٹR‚ء•£‚ةŒڑ‚ؤ‚½پAژR‚ج‰ئ‚حپAŒڑ‚ؤ‚½‚خ‚©‚è‚جچ ‚حپA‚µ‚ء‚©‚肵‚ؤ‚¢‚½‚ھپA— ‚ج’Œ‚ج“y‘ن‚ئ‚ب‚éپA’n”ص‚ھ‚ن‚é‚‚ؤپAƒoƒ‰ƒoƒ‰‚ئ“y‚ھ•ِ‚ê—ژ‚؟‚ؤ‚¢‚½پBپ@‹‚¢•—‚ھگپ‚¢‚ؤ—ˆ‚é‚ئپAپuƒ~ƒVپAƒ~ƒVپv‚ئپA‚«‚µ‚فپAچ،‚ة‚à“|‚ê‚é‚©‚ج‚و‚¤‚ة‰¹‚ھ‚µ‚ؤپA—h‚ê‚é‚ج‚¾‚ء‚½پBپ@
پ@ƒ`ƒJ‚حپA•v‚ً‘—‚èڈo‚µ‚½ŒمپA–ˆ“ْپAˆêژٹش‚©‚¯‚ؤژR‚ة“o‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‚¢‚½پBƒ`ƒJ‚حپAƒ[ƒ“‚جکb‚ً•·‚‚ئپAپu‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌپA‚»‚ٌ‚ب•|‚¢ژv‚¢‚ً‚µ‚ؤپAˆêگl‚إڈZ‚ٌ‚إ‚¢‚ب‚¢‚إپAژR‚ًچ~‚è‚ؤپA‚¤‚؟‚ç‚ئˆêڈڈ‚ة•é‚炵‚ـ‚¹‚ٌ‚©پHپBپv‚ئ‰½“x‚àŒ¾‚ء‚½‚ھپAƒ[ƒ“‚حپA‚»‚ê‚إ‚àŒ¾‚¤‚±‚ئ‚ً•·‚©‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@‚ئ‚±‚ë‚ھپA‚ ‚é”NپA‹مڈB•û–ت‚ة‘هŒ^‘ن•—‚ھ‹ك‚أ‚¢‚ؤ—ˆ‚ؤ‚¢‚½پBپ@ƒ[ƒ“‚ج‚±‚ئ‚ھپAگS”z‚ة‚ب‚ء‚½ƒ`ƒJ‚حپAژR‚ة“o‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ—lژq‚ًŒ©‚ة—ˆ‚½پBپu‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌپA‘ه‚«‚ب‘ن•—‚ھ‹ك‚أ‚¢‚ؤ‚‚é‚»‚¤‚إ‚·‚وپB‘هڈن•v‚إ‚·‚©پHپBپvپ@پ@ژR‚ج‰ئ‚حپA‚à‚¤‚·‚ء‚©‚èڈ‚ٌ‚إپA‚ ‚؟‚炱‚؟‚ç‚ة‰JکR‚è‚ھ‚µ‚ؤ‚¢‚ؤپA•—‚ھگپ‚‚½‚ر‚ةپA“Vˆن‚ھƒMƒVƒMƒV‚ئ•s‹C–،‚ب‰¹‚ھ‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپi‚±‚ج‰ئ‚حپA‚à‚¤“|‚ê‚é‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢پcپBپj
پ@ƒ`ƒJ‚حپAŒ™‚ب—\ٹ´‚ھ‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپu‚ ‚ پ[پA‚¦‚¸‚©‚خ‚¢پBپvپu‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌپA‘پ‚‚±‚±‚ًڈo‚ؤپA‚¤‚؟‚ç‚ج‰ئ‚ة—ˆ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پBپvپu‚ ‚ پ[پA‚¦‚¸‚©پBپvپu‚à‚¤ٹë‚ب‚¢‚©‚çژR‚©‚çچ~‚è‚ؤپA‚¤‚؟‚½‚؟‚ج‰ئ‚ة—ˆ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پBپvپ@ƒ[ƒ“‚àپAچ،‚ة‚à•ِ‚ê‚»‚¤‚ب‹°•|‚ًٹ´‚¶‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚ء‚½پBƒ[ƒ“‚حپA‚â‚ء‚ئپAƒ`ƒJ‚جŒ¾‚¤’ت‚è‚ة‚·‚邵‚©‚ب‚¢‚ئٹد”O‚µ‚ؤ‚µ‚½پB
پ@‹}‚¢‚إگgژx“x‚µ‚ؤ‰ئ‚ًڈo‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پBپ@‰ئ‚ج’†‚ة‚حپA•ؤ‚ج“ü‚ء‚½•U‚ھ‚¢‚‚آ‚©گد‚ٌ‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@پu‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌپA‰ئچà“¹‹ï‚ح‚»‚ج‚ـ‚ـ‚ة‚·‚邵‚©‚ب‚¢‚¯‚اپA‚±‚±‚ة‚ ‚é•ؤ‚¾‚¯‚إ‚àپA‰^‚ٌ‚إچs‚«‚ـ‚µ‚ه‚¤پB•ؤ‚ھ‰J‚ة”G‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚çپAژg‚¢•¨‚ة‚ب‚ç‚ب‚‚ب‚è‚ـ‚·‚وپBپvپu‚ ‚ پA‚»‚¤‚â‚بپ[پBپv
پ@‚±‚¤‚µ‚ؤپAƒ`ƒJ‚ئƒ[ƒ“‚حپAژR‚ج‰ئ‚ة’u‚¢‚ؤ‚ ‚ء‚½•ؤ•U‚ً’S‚¢‚إچ⓹‚ًچ~‚è‚ؤچs‚ء‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤپA‚ئ‚ؤ‚آ‚à‚ب‚¢‘ه‚«‚ب‘ن•—‚ھپAژ…“‡‚ج’n‚ًڈP‚ء‚½پB‹ك‚‚جŒأ‚¢”_‰ئ‚جڈ¬‰®‚ب‚ا‚حپA‚½‚؟‚ـ‚؟گپ‚«”ٍ‚خ‚³‚êپA•ِ‚ê‚ؤ‚¢‚ء‚½پB‚±‚ج‘ن•—‚حپA“O’ê“I‚ةŒأ‚¢‚à‚ج‚ً”j‰َ‚µگs‚‚µ‚ؤپA’ت‚è‰ك‚¬‚ؤ‚¢‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB‘ن•—‚ھچs‚«‰ك‚¬‚½“ٌ“ْŒمپAژR‚ةچs‚ء‚ؤŒ©‚é‚ئپAƒ`ƒJ‚ج—\ٹ´‚ا‚¨‚èپAپuژR‚ج‰ئپv‚حŒ©ژ–‚ة’ׂê‚ؤ‚¢‚½پBٹR‘¤‚ج“y‘ن‚ج’n”ص‚ھ•ِ‚ê—ژ‚؟پA’Œ‚ھ“|‚ê‚ؤ”¼‰َ‚µ‚½ڈَ‘ش‚إŒX‚¢‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
پ@ƒ`ƒJ‚حپA•sژv‹c‚بپu‘وکZٹ´پv‚إپAڈP‚¢‚©‚©‚éٹë‹@‚ًژ–‘O‚ةژ@’m‚µ‚ؤپAژR‚ة‹ڈ‚½ƒ[ƒ“‚ج–½‚ئپA•ؤ‚ً‹~‚ء‚½پBپ@‚±‚¤‚µ‚ؤپAƒ[ƒ“‚جژR‚ج•é‚炵‚ھڈI‚ي‚ء‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ٌژشژ–ŒجپB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚ھپAگ¶‚ـ‚ê‚ؤٹش‚à‚ب‚¢چ پA“ث‘RپA•sچK‚بژ–Œج‚ج’m‚点‚ھ•‘‚¢چ‚ٌ‚إ—ˆ‚½پB
پ@پu”ژ‘½‚إپAگ³ٹى‚³‚ٌ‚ھ‹Dژش‚ة‚ح‚ث‚ç‚ꂽپIپBپv‚ئ‚¢‚¤’m‚点‚¾‚ء‚½پBƒ`ƒJ‚àƒ[ƒ“‚àپA‚»‚ê‚ً•·‚¢‚½ڈuٹشپAپu‹Dژش‚ةˆّ‚©‚ꂽ‚ب‚ç‚à‚¤ڈ•‚©‚ç‚ب‚¢پBپc‚à‚¤ژ€‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ةˆل‚¢‚ب‚¢پBپv‚ئپAگâ–]“I‚ة‚ب‚ء‚½پB‚¾‚ھپA‚و‚•·‚¢‚ؤ‚ف‚é‚ئپAگ³ٹى‚حپA‘«‚ً‰ِ‰ن‚µ‚ؤپA•a‰@‚ة‰^‚خ‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾‚ء‚½پBپ›
پ@ƒ`ƒJ‚حپA’m‚点‚ً•·‚‚ئپAڈم‚جژq‹ں’B‚ًŒئ‚جƒ[ƒ“‚ة‘ُ‚µ‚ؤپA‚·‚®•a‰@‚ةچs‚ژ–‚ة‚µ‚½پB‚ ‚ي‚½‚¾‚µ‚––‚ءژq‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚ً”w’†‚ة‚¨‚ش‚ء‚ؤپA‹}‚¢‚إ‹Dژش‚ة”ٍ‚رڈو‚ء‚½پBƒ`ƒJ‚حپAپiٹش‚ةچ‡‚¤‚¾‚낤‚©پcپBپj‚ئƒWƒٹƒWƒٹ‚·‚é‚و‚¤‚ب•sˆہ‚°‚ب‹Cژ‚؟‚ً•ّ‚«‚ب‚ھ‚çپAˆêژٹش‚ظ‚ا‹Dژش‚ة—h‚ç‚ê‚â‚ء‚ئ”ژ‘½‰w‚ة’…‚¢‚½پBپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚ً”w•‰‚¢‚ب‚ھ‚ç•v‚ھ“ü‰@‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤•a‰@‚ةŒü‚©‚ء‚ؤپA‹}‚¬‘«‚إڈ¬‘–‚è‚ة‘–‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚â‚ھ‚ؤƒ`ƒJ‚ح•a‰@‚جŒ؛ٹض‚ة‚â‚ء‚ئ’H‚è’…‚¢‚½پB
پ@•v‚جگ³ٹى‚حپA“Vگ_‚جچدگ¶‰ï•a‰@‚ة‰^‚خ‚êپA‹ظ‹}ژèڈp’†‚¾‚ء‚½پB‘«‚ً•²پX‚ةچس‚©‚ꌌ“h‚ê‚ة‚ب‚ء‚ؤ‰^‚خ‚ꂽ‚ھپAˆسژ¯•s–¾‚جڈd‘ج‚¾‚ء‚½پB
پ@ژèڈpژ؛‚©‚çڈo‚ؤ—ˆ‚½گوگ¶‚حپAپuچ،ˆن‚³‚ٌ‚ج‰œ‚³‚ٌ‚إ‚·‚©پHپAچإ‘P‚ًگs‚‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپAچ،‚ھ“»‚إپA‰½‚ئ‚©‚±‚ج‚ـ‚ـپAژ‚؟‚±‚½‚¦‚ؤ‚‚ê‚ê‚خ‚¢‚¢‚إ‚·‚ھپcپBپv‚ئŒ¾‚ء‚½پBپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚ح”w’†‚ة”w•‰‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ھپA•a‰@‚ج’†‚جƒUƒڈƒUƒڈ‚µ‚½‹C”z‚ة‹ء‚¢‚ؤپAپu‹A‚낤پA‹A‚낤‚وپ[پv‚ئ‚®‚¸‚ء‚ؤ‹ƒ‚¢‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپu‚ـ‚±‚ئپv‚ً‚ ‚₵‚ب‚ھ‚çپAپi‚à‚µپA‚±‚ج‚ـ‚ـژهگl‚ھ–S‚‚ب‚ء‚½‚ç‚ا‚¤‚ب‚é‚ج‚¾‚낤پcپHپBپj‚ئ’ê’m‚ê‚ت•sˆہ‚بژv‚¢‚ئگي‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپi•v‚ج–½‚ھ–S‚‚ب‚ê‚خچ،ˆن‰ئ‚حˆê‰ئ—£ژU‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚¾‚낤پcپBپjپiگ_—lپIپA‚ا‚¤‚©ژهگl‚ج–½‚ًڈ•‚¯‚ؤ‰؛‚³‚¢پB‚»‚جˆّ‚«‚©‚¦‚جˆ×‚ب‚çپAژ„‚ح‚ا‚ٌ‚ب‹êکJ‚ً”w•‰‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚àچ\‚¢‚ـ‚¹‚ٌپIپcپBپj‚ـ‚ٌ‚¶‚è‚ئ‚à‚µ‚ب‚¢‚إپAˆأˆإ‚ج’†‚إ•Kژ€‚ة‹F‚葱‚¯‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA•ê‚ج”w’†‚إ‚±‚جˆإ–é‚جگ¾‚¢‚ً‚·‚éƒ`ƒJ‚جŒم‚ëژp‚ًپA‰½‚à’m‚炸‚ة‚¤‚آ‚ë‚ب–ع‚إŒ©‚ؤ‚¢‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚ج•Kژ€‚ج‹F‚è‚ھ’ت‚¶‚½‚ج‚©پAڈء‚¦‚©‚¯‚½–½‚ج‰خ‚ھژں‘و‚ةلS‚èژn‚ك‚½پBگ³ٹى‚ج–½‚حپuƒ`ƒJ‚جˆإ–é‚جگ¾‚¢پv‚ئ‚جˆّ‚«‘ض‚¦‚ة‚و‚ء‚ؤٹïگص“I‚ةڈ•‚©‚ء‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚ح‹F‚è‚ة‚و‚ء‚ؤ•v‚ج–½‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAچ،ˆن‰ئ‚جژq‹ں‚½‚؟‚ج‹P‚–¢—ˆ‚ً‹~‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پBپ@‚â‚ھ‚ؤ‰ٌ•œ‚ةŒü‚©‚¤گ³ٹى‚حپAژ–Œج‚جژ‚ج‚±‚ئ‚ًڈ‚µ‚¸‚آƒ`ƒJ‚ةکb‚µ‚ؤ•·‚©‚¹‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³ٹى‚جŒ©‚½’nچ–پB
پ@‚»‚ج“ْ‚حپAچ÷‚ھ–ٹJ‚ةچç‚‹Gگك‚¾‚ء‚½پB
گ³ٹى‚حپAژdژ–‚ھڈI‚ي‚ء‚ؤ‚©‚çپAپuڈZ‹gگ_ژذ‚ة‰شŒ©‚ةچs‚±‚¤پBپv‚ئگEڈê‚ج’‡ٹش‚ة—U‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚¾‚ھپA‹}‚ةگù”ص‚ج’²ژq‚ھˆ«‚¢‚ج‚إŒ©‚ؤ‚‚ê‚ب‚¢‚©‚ئ‚¢‚¤پAŒ»ڈê‚جژdژ–‚ھ“ü‚ء‚ؤ—ˆ‚½پBگ³ٹى‚حپAچH‹ï” ‚ًژ©“]ژش‚ةگد‚ٌ‚إپAپu‚؟‚ه‚ء‚ئ’¼‚µ‚ؤ‚‚éپA‚·‚®ڈI‚ي‚é‚©‚çپvپA‚ئ‚ف‚ٌ‚ب‚ً‘ز‚½‚¹‚½‚ـ‚ـڈo‚©‚¯‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@‚¢‚آ‚àپA‹@ٹB–û‚جڈإ‚°‚éڈL‚¢‚ج‚·‚éچHڈê‚ج’†‚إپA”–‰ک‚ꂽ‹َ‹C‚خ‚©‚è‹z‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA‹v‚µ‚ش‚è‚ةٹO‚ةڈo‚ؤپAگV‘N‚ب‹َ‹C‚ً‹z‚¢پAپiچ،“ْ‚حژdژ–‚ھڈI‚ي‚ء‚½‚çپA‰شŒ©‚¾پcپBپj‚ئ”ü‚µ‚¢چ÷‚ج‰؛‚إ‚ج‰ƒ‰ï‚ًژv‚¢‚ب‚ھ‚çپAچK‚¹‚ب‹C•ھ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤŒ»ڈê‚جژdژ–‚ھڈI‚ي‚ء‚ؤپA‰ïژذ‚ةŒü‚©‚ء‚ؤژ©“]ژش‚إ‹A‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@ڈZ‹gگ_ژذ‚ج‹ك‚‚ةپAگMچ†‹@‚ج‚ب‚¢Œ©’ت‚µ‚جˆ«‚¢“¥گط‚ھ‚ ‚èپA‚»‚±‚جٹp‚إچ·‚µٹ|‚©‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپuƒJƒ^ƒJƒ^پcپEپv‚ئگüکH‚ً“`‚¤‹Dژش‚ج‰¹‚ھ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA‚µ‚خ‚ç‚ژ©“]ژش‚ًچ~‚è‚ؤ‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚¾‚ھپAگ³ٹى‚ةپA’m‚èچ‡‚¢‚جگl‚ھکb‚µ‚©‚¯‚ؤ—ˆ‚ؤپA‚¢‚آ‚ـ‚إ‚à–T‚ً—£‚ê‚ب‚©‚ء‚½پB‚â‚ھ‚ؤپAڈم‚è‚ج‹Dژش‚ھ’ت‚è‰ك‚¬‚ؤچs‚ء‚½پB
پ@‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©پAژٹش‚ھŒo‚آ‚ج‚ً–Y‚ê‚ؤ—§‚؟کb‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپ@پi‘پ‚‹A‚ç‚ث‚خ‚ف‚ٌ‚ب‚ھ‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ةˆل‚¢‚ب‚¢پBپj‚â‚ء‚ئکb‚ة‹وگط‚è‚ھ‚آ‚¢‚ؤپA•ت‚ꂽ‚ ‚ئپA‚»‚ج‚ـ‚ـژ©“]ژش‚ً‰ں‚µ‚ؤپA‚¢‚ء‚«‚ة“¥گط‚ً“n‚낤‚ئ‚µ‚½پB
پ@‚»‚جڈuٹشپA”½‘خ•ûŒü‚©‚ç“ü‚êˆل‚¢‚ةپA‰؛‚è‚ج—ٌژش‚ھ‚·‚®–ع‚ج‘O‚ةŒ»‚ي‚ꂽپB•ƒ‚جگ³ٹى‚ح™ٍڑl‚ةژ©“]ژش‚ً•ْ‚è“ٹ‚°‚ؤ‘ج‚ً•ڑ‚¹‚½‚ھپA‰E‘«‚ً‰½‚©“S‚جƒnƒ“ƒ}پ[‚إ‘إ‚؟چس‚©‚ꂽ‚و‚¤‚بŒƒ’ة‚ھ‚ح‚µ‚ء‚½ڈuٹشپA‚»‚ج‚ـ‚ـ‹C‚ًژ¸‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤پB
پ@‚»‚ê‚©‚çگو‚جژ–‚حپA‘c•êƒ[ƒ“‚ھپA‹@ٹضژm‚جگl‚©‚ç•·‚¢‚½کb‚ً‘·‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚ة•·‚©‚¹‚ؤ‚‚ꂽ“à—e‚إ‚ ‚éپB
پ@‚»‚ج“ْپA‘ز‚؟چ‡‚¢‚ج‹Dژش‚ھ“’…‚µ‚½‚ج‚ًٹm”F‚µ‚ؤپA”ژ‘½‰w‚©‚ç“®‚«ڈo‚µ‚½‹Dژش‚حپA‰ء‘¬‚µ‚¾‚µ‚ؤ‚¢‚½پBڈZ‹g‚ج“¥گط‚ة—ˆ‚½ژپA‘O•û‚ة‚¢‚«‚ب‚èگl‚ھŒ»‚ي‚êپA‹ء‚¢‚ؤ‹}ƒuƒŒپ[ƒL‚ً‚©‚¯‚½‚ھپA‚ ‚ء‚ئŒ¾‚¤ٹش‚جڈo—ˆژ–‚إپA‚à‚¤ٹش‚ةچ‡‚ي‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@چ~‚è‚ؤŒ©‚ؤ‚ف‚é‚ئپA‘«‚©‚猌‚ً—¬‚µ‚ؤ•ƒ‚ھ“|‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤پB‚»‚جگl‚حپAگ³ٹى‚جŒûŒ³‚ةژè‚ً“–‚ؤ‚ؤ‚ف‚½پBپu‚ـ‚¾پA‘§‚ھ‚ ‚éپIپB‹}‚¢‚إ•a‰@‚ةکA‚ê‚ؤ‚¢‚¯‚خڈ•‚©‚é‚©‚à’m‚ê‚ٌ‚¼پIپvگ³ٹى‚ج‘«‚©‚ç‚حپA‚½‚‚³‚ٌ‚جŒŒ‚ھگپ‚«ڈo‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‹}‚¢‚إ‰½ڈˆ‚©‚ç‚©پA“ê•R‚ً’T‚µ‚ؤ—ˆ‚é‚ئپA•G‚جڈم‚ً‚®‚é‚®‚é‚ئٹھ‚«•t‚¯‚ؤ‹‚”›‚ء‚½پB‚»‚µ‚ؤپA‚·‚®‹}‚¢‚إ•a‰@‚ة‰^‚ٌ‚¾‚ئ‚¢‚¤پB
پ@ƒ[ƒ“‚حپA‚»‚جگl‚©‚çپA‘§ژq‚جژ–Œج‚ج‚¢‚«‚³‚آ‚ًڈع‚µ‚•·‚¢‚½پBگ³ٹى‚ًڈ•‚¯‚ؤ‚‚ꂽ–½‚ج‰¶گl‚ةپA—ـ‚ً—¬‚µ‚ب‚ھ‚çپAگS‚©‚çٹ´ژس‚ج‚¨—ç‚ًŒ¾‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤پB
پ@گ³ٹى‚حپA‘«‚ة”R‚¦‚é‚و‚¤‚بŒƒ‚µ‚¢’ة‚ف‚ًٹ´‚¶‚ؤ–ع‚ًگء‚µ‚½پBپ@‹C‚ھ•t‚‚ئ•a‰@‚جƒxƒbƒh‚ةگQ‚©‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB’ة‚ق‘«‚ًگG‚낤‚ئ‚ـ‚³‚®‚낤‚ئ‚µ‚½‚ئ‚«پA‚»‚جژè‚ح‹•‚µ‚‹َ‚ً’ح‚ٌ‚إœfœr‚ء‚½پB“r’†‚©‚çگط’f‚³‚ꂽ‘«‚حپA•ï‘ر‚ھŒْ‚ٹھ‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپAˆظ—l‚ة”M‚¢ٹ´ٹo‚ة‚ ‚ء‚½پB
پ@گ³ٹى‚حپA™ٍڑl‚ة‚ ‚ج‹°•|‚جڈuٹش‚ًژv‚¢ڈo‚µ‚½پBپi‚ ‚جژ‚جژ–Œج‚إپAژ©•ھ‚ح‹Dژش‚ة•~‚©‚ꂽ‚ٌ‚¾پBپcپEپjگط’f‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½ژ©•ھ‚ج‘«‚ًŒ©‚ؤپA‹}‚ةگâ–]‚جژv‚¢‚ھڈP‚ء‚ؤ—ˆ‚½پBپ@Œ’چN‘ج‚إ‚ ‚ء‚½ژپAٹ´‚¶‚½‚±‚ئ‚ج–³‚¢پAŒ¾‚¢’m‚ê‚ت–³”O‚جژv‚¢‚ھ‚و‚¬‚ء‚ؤ—ˆ‚é‚ج‚¾‚ء‚½پBپi‚ ‚جژپA‘پ‚‹A‚ء‚ؤ‚¢‚ê‚خپA‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ة‚ح‚ب‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚ةپcپcپj
پ@ژ©•ھ‚جگg‘ج‚جˆê•”‚ھ–³‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½”ك‚µ‚³‚ًٹڑ‚ف‚µ‚ك‚ب‚ھ‚çپAژ©•ھ‚ج•s’چˆس‚ئ•sچK‚ب‰^–½‚ًژô‚ء‚ؤ–³Œ¾‚ج‚ـ‚ـچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پBپ@‚¾‚ھگ³ٹى‚حپA•ذ‘«‚ً–³‚‚µ‚ؤپAٹm‚©‚ة‘ه‚«‚بƒVƒ‡ƒbƒN‚ًژَ‚¯‚½‚ھپA‚»‚جگS‚جڈصŒ‚‚ً’N‚ة‚à‘إ‚؟–¾‚¯‚¸پAŒˆ‚µ‚ؤژم‰¹‚ً“f‚©‚ب‚©‚ء‚½پBپi–½‚ھڈ•‚©‚ء‚½‚¾‚¯‚إ–ׂ¯•¨‚ئٹ´ژس‚µ‚ب‚‚ؤ‚ح‚¢‚©‚ٌپcپj‚ئگS‚ًگط‚è‘ض‚¦‚ؤپA—JںT‚بژv‚¢‚ًگU‚èگط‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚»‚ê‚©‚çپA‰i‚¢‰i‚¢“ü‰@گ¶ٹˆ‚ھ‘±‚¢‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA•ƒ‚جٹç‚ًŒ©‚邱‚ئ‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا–³‚©‚ء‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@–³‚‚µ‚½‚à‚جپB
پ@•vگ³ٹى‚حپA•ذ‘«‚ً‚©‚خ‚¢‚ب‚ھ‚çپA‚µ‚خ‚ç‚ڈ¼—tڈٌ‚إƒٹƒnƒrƒٹ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
‚â‚ھ‚ؤ’ة‚ف‚à”–‚êپAژں‘و‚ة‰ٌ•œ‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½پB–³ژ–‚ة‘ق‰@‚µ‚ؤ‰ئ‚ة‹A‚ء‚ؤ‚«‚½پBپ@ژdژ–‚ة‘خ‚·‚éگس”Cٹ´‚ج‹‚¢گ³ٹى‚حپAپu‚¢‚آ‚ـ‚إ‚àژdژ–‚ً‹x‚ٌ‚إ‚¢‚é–َ‚ة‚ح‚¢‚©‚ب‚¢پcپv‚ئ‚ ‚¹‚èڈo‚µ‚ؤ‚¢‚½پBژ{گف‚©‚ç‘—‚ç‚ê‚ؤ‚«‚½‹`‘«‚ً‚ح‚«پA‚ر‚ء‚±‚ًˆّ‚«‚ب‚ھ‚ç•à‚«ڈo‚µ‚½پB‚¾‚ھپA‚»‚ج‹`‘«‚حپAڈ‚µ•à‚‚ئ‚·‚®‘«‚ھ’ة‚‚ب‚ء‚½پB
پ@ٹي—p‚بگ³ٹى‚حپA‘«‚ة‚µ‚ء‚‚肱‚ب‚¢‹`‘«‚ةپA•z‚ً“ü‚ꂽ‚肵‚ؤژ©•ھ‚إگFپX‚ئچH•v‚ً‚µ‚ب‚ھ‚çپA’ة‚‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‰ü—ا‚µ‚ؤ‚ح‚¢‚ؤ‚¢‚½پBپ@‚â‚ھ‚ؤگ³ٹى‚حپA‹`‘«‚ً’…‚¯‚ê‚خپAŒ©‚½–ع‚ة‚ح•پ’ت‚جگl‚ئ•د‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‚ة•à‚¯‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚èپA‚»‚ج‚±‚ئ‚ةژ©گM‚ھڈo‚ؤ—ˆ‚½پB
پ@ژdژ–‚ً‚·‚éˆس—~‚ھڈo‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚©پAڈٌ‚ً‚آ‚«‚ب‚ھ‚çپA–ˆ“ْˆêژٹش”¼‚©‚¯‚ؤ”ژ‘½‚ج“SچHڈٹ‚ة’ت‚ء‚½پB•پ’ت‚جگl‚ئ•د‚炸پAچؤ‚رگù”ص‚ج—§‚؟ژdژ–‚ة–ك‚ء‚ؤ“‚¢‚½پB
پ@‘«‚ً•ذ•û–³‚‚µ‚ؤگEڈê‚ة–ك‚ء‚ؤ—ˆ‚½گ³ٹى‚حپAڈd‚¢چ|چق‚ًژ‚؟‚ ‚°‚é‚ج‚àˆê‹êکJ‚إ‚ ‚ء‚½پB‚»‚ٌ‚بگ³ٹى‚ھ‹`‘«‚ج‘«‚إپAڈd‚¢“S’Œ‚ً’S‚¢‚إگù”ص‚ةگف’u‚·‚éژ‚ة‚حپA•”‰؛‚½‚؟‚ھ‚·‚®‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‚ح‰½‹C‚ب‚¢ژd‘گ‚إژè“`‚ء‚ؤ‚‚ꂽپBپ@گ³ٹى‚حپA‚»‚ٌ‚ب•”‰؛‚½‚؟‚ج‚³‚è‹C‚ب‚¢گS”z‚è‚ةٹ´ژس‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚¢‚آ‚à‹A‚蓹‚ة‚ح”ق‚ç‚ً‰®‘ن‚ة—U‚ء‚ؤ‚حپAڈ‚ب‚¢‹‹—؟‚ج’†‚©‚çپAژً‚ً‚¨‚²‚ء‚ؤ‚س‚é‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚½‚¾‚إ‚³‚ضڈ‚ب‚¢‹‹—؟‚ب‚ج‚ةپA‚¢‚آ‚à••‚ھگط‚ç‚ê‚ؤڈ‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپAƒ`ƒJ‚ح•sژv‹c‚ةژv‚¢پA‚ ‚é“ْپAپu‚¢‚آ‚à‰½‚ةژg‚¤‚جپHپv‚ئ•·‚¢‚ؤ‚ف‚½پBپu‚ٌپcپE–ˆ“ْپA‰´‚حژü‚è‚ج‚ف‚ٌ‚ب‚ةگFپX‚ئڈ•‚¯‚ؤ–ل‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚çپAژً‚جˆê”t‚®‚ç‚¢‚¨‚²‚ء‚ؤ‚ ‚°‚ب‚¢‚ئگ\‚µ–َ‚ب‚©‚낤‚ھپcپv‚ئ‚آ‚ش‚â‚‚و‚¤‚ةŒ¾‚ء‚½پB
پ@گl‚ةڈ‚ً‚©‚¯‚ç‚ꂽ‚è‚·‚é‚ج‚ھŒ™‚بگ³ٹى‚حپAژn‚ك‚حˆêگl‚إ‰½‚ئ‚©‚â‚ê‚é‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپAژc”O‚ب‚ھ‚çپA‚¢‚آ‚à‚ف‚ٌ‚ب‚ةڈ•‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚µ‚©ژdژ–‚ھڈo—ˆ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ً’ةٹ´‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپ@‰÷‚µ‚¢ژv‚¢‚ً‚µ‚ب‚ھ‚ç‚àپAپi‚ف‚ٌ‚بپA‚¢‚آ‚à‹C”z‚肵‚ؤ‚‚ê‚ؤپA‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤پcپBپj‚ئگ¸ˆê”t‚جٹ´ژس‚ج‹Cژ‚؟‚ً‚»‚ج‚آ‚اپAژً‚إ•ش‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚ء‚½پB
پ@گ³ٹى‚حپA‚µ‚خ‚ç‚‚حڈٌ‚ً‚آ‚«‚ب‚ھ‚ç’ت‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‰J‚ج“ْ‚ح‚»‚جڈٌ‚ًژP‚ةژ‚؟‘ض‚¦‚½پBگ³ٹى‚حپAڈٌ‚ً‚آ‚¢‚ؤٹO‚ةڈo‚é‚ئپA‚¢‚آ‚àگl‚ھ“ء•تˆµ‚¢‚·‚é‚ج‚ھŒ™‚¾‚ء‚½پB‚ب‚é‚ׂپAگl’ت‚è‚ج’†‚إ‚حپA•پ’ت‚جŒ’ڈيژز‚ئ‘م‚ي‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‚ةگU‚é•‘‚¢‚½‚©‚ء‚½‚ج‚¾پB
پ@––‚ءژq‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚±‚جژ‚جپA•ذ‘«‚ً–³‚‚µ‚½•ƒگe‚جپAژq‹ں‚ة‰“—¶‚ھ‚؟‚ةگع‚·‚éپA”ك‚µ‚¢گS‚ج“à–ت‚ً’m‚锤‚à–³‚©‚ء‚½پB•ƒ‚حپAژ©•ھ‚ج•s’چˆس‚إ‹N‚«‚½ژ–Œج‚جژ–‚ًپA’p‚¸‚©‚µ‚ژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚©پAپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚ةŒˆ‚µ‚ؤکb‚·‚±‚ئ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚±‚ٌ‚ب•ƒ‚ج’´گl“I‚ب‰ن–‹‚³‚ئپA•ê‚ج”é‚ك‚ؤ‚¢‚錃‚µ‚¢‹Cگ«‚ج—¼•û‚ًŒ“‚ث”ُ‚¦‚ؤ‚¢‚½پBپ@ڈلٹQ‚ً”w•‰‚ي‚³‚ê‚ؤ‚àپA‚¶‚ء‚ئ‰ن–‚µ‚ؤپA‘د‚¦‘±‚¯‚é”S‚è‹‚³‚à‚ ‚ء‚½‚ھپAˆê•ûپA‚â‚邾‚¯‚â‚ء‚ؤ‘ت–ع‚¾‚ئ•ھ‚©‚é‚ئپA‚ ‚ء‚³‚è‚ئٹب’P‚ة’ْ‚ك‚ؤ‚µ‚ـ‚¤چ‡—“I‚بگ«ٹi‚àŒ“‚ث”ُ‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚©‚آ‚ؤˆê‘م–ع‚ةگrژµ‚ھ•K—v‚ئ‚µ‚½پAŒُ‚ج“¹‚ً“±‚پi”’‚¢ڈٌپj‚حپA“ٌ‘م–ع‚جƒ`ƒJ‚ج•v‚إ‚ ‚éگ³ٹى‚à‚ـ‚½•K—v‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚حپA”ç“÷‚ة‚à•ƒ‚خ‚©‚è‚إ‚ح‚ب‚پA•v‚جژx‚¦‚ئ‚ب‚éپiڈٌ‚ج–ًپj‚ً‘م‚ي‚è‚ة‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚‚ب‚ء‚½پB
پ@‚¾‚ھگ³ٹى‚حپA‚ا‚ٌ‚ب‚ةگh‚‚ؤ‚àپA‚ب‚é‚ׂڈٌ‚ة—ٹ‚炸پAڈٌ‚ًژ‚½‚ب‚¢‚إژP‚ً‚آ‚¢‚ؤپA•پ’ت‚جگl‚ئ•د‚ي‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‹ة—حپA•à‚±‚¤‚ئ“w‚ك‚é‚ج‚¾‚ء‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپAگ³ٹى‚ج‹گx‚ب‰ٌ•œ—ح‚ئپA”E‘د—ح‚ة‹ء‚«‚ب‚ھ‚çپA‚»‚ٌ‚ب•v‚جŒ’‹C‚بژp‚ًŒ©‚é‚ج‚ھپA‚¹‚ك‚ؤ‚à‚ج‹~‚¢‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@•v‚ج”ك‚µ‚فپB
پ@
پ@ڈH‚ھ—ˆ‚ؤپAٹ ‚è“ü‚ê‚جژdژ–‚إ‰ئ’†–Z‚µ‚¢ژٹْ‚ة‚ب‚ء‚½پBگ³ٹى‚ة‚ئ‚ء‚ؤپA”و‚ꂽگg‘ج‚ً‹x‚ك‚邹‚ء‚©‚‚ج“ْ—j“ْ‚¾‚ء‚½‚ھپA‚ف‚ٌ‚بٹو’£‚ء‚ؤ“‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ةپA‚ذ‚ئ‚è‚إ‰ئ‚إ‹x‚ٌ‚إ‚¢‚é–َ‚ة‚ح‚¢‚©‚ب‚¢•µˆح‹C‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پi’©‘پ‚‚©‚çژx“x‚µ‚ؤڈo‚©‚¯‚و‚¤‚ئ‚·‚éƒ`ƒJ‚½‚؟‚ةˆ«‚¢‚بپcپBپj‚ئژv‚ء‚½‚ج‚©پAپu‰´‚àپAŒم‚©‚çژq‹ں‚½‚؟‚ئژR‚ةچs‚‚©‚ç‚بپcپBپv‚ئŒ¾‚ء‚½پB
پ@پu‚ ‚ٌ‚½‚ح–ˆ“ْپA“SچHڈٹ‚إ“‚¢‚ؤ”و‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚â‚©‚çپA–³—‚¹‚ٌ‚إ‚و‚©‚وپBپvپu‚ب‚µ‚âپA‚ب‚ٌŒ¾‚¤‚ئ‚©پA‰´‚àŒم‚©‚çپu‚ـ‚±‚ئپv’B‚ًکA‚ê‚ؤˆêڈڈ‚ةچs‚‚©‚çپcپBپv‚ئˆس’n‚ً’£‚ء‚ؤ–ٌ‘©‚µ‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپA“SچHڈٹ‚جژdژ–‚ج‘ه•د‚³‚ھ”»‚ء‚ؤ‚¢‚½پB•v‚ھ“ْ—j“ْ‚ةپA‚ن‚ء‚‚èگg‘ج‚ً‹x‚ك‚邱‚ئ‚حپA‘هگط‚ب‚±‚ئ‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½پB“ء‚ةگ³ٹى‚جژdژ–‚حپAƒ~ƒNƒچ‚جƒRƒ“ƒ}‰½ƒ~ƒٹ‚جگ¸“x‚ً—v‹پ‚³‚ê‚éگ_Œo‚ًژg‚¤ژdژ–‚إ‚ ‚éپB
پ@‚»‚ê‚ة‘«‚جˆ«‚¢گ³ٹى‚ة‚حپAژR‚ة“o‚é‚ج‚¾‚¯‚إ‚àچœ‚جگـ‚ê‚éژ–‚¾‚ء‚½پBژR‚جژè“`‚¢‚ً‚·‚é‚و‚èپAڈ\•ھگأ—{‚µ‚ؤگg‘ج‚ًٹ®‘S‚ة‰ٌ•œ‚µ‚ؤپA‚ـ‚½Œژ—j“ْ‚©‚ç“‚‚½‚ك‚ةپA‰ئ‚إ‚ن‚ء‚‚è‹x‚ٌ‚إ”و‚ê‚ًژو‚ء‚ؤ—~‚µ‚©‚ء‚½پB
پ@‚¾‚ھƒ[ƒ“‚ة‚حپAچׂ©‚¢گ_Œo‚ًژg‚¤گ³ٹى‚جژdژ–‚ج‘ه•د‚³‚ھ‘S‘R”»‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB”_”ةٹْ‚ة‚ب‚é‚ئپuگ³ٹىپI‚¨‘O‚à“ْ—j‚®‚ç‚¢پAژR‚جژdژ–‚ًژè“`‚¢‚ة—ˆ‚ٌ‚©پ[پIپBپv‚ئپA—گ–\‚ةŒ¾‚¤‚ج‚¾‚ء‚½پBپ@
پ@‚ف‚ٌ‚ب‚ھڈo‚©‚¯‚½ŒمپAگ³ٹى‚حپA“ٌٹK‚إگQ‚ؤ‚¢‚éپu‚ـ‚±‚ئپv‚ئکaچ]‚½‚؟‚ةپAپu‚¨پ[‚¢پAپu‚ـ‚±‚ئپvپIپAکaچ]پI‘پ‚و’©”رگH‚¦پA‚±‚ê‚©‚çˆêڈڈ‚ةژR‚ةچs‚‚¼پIپBپv‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‹N‚±‚µ‚ؤپA“ٌگl‚ً‘£‚µ‚½پB
پ@‚±‚جچ ‚جگ³ٹى‚ح‚ـ‚¾Œ³‹C‚إپA‚ـ‚¾ڈ¬‚³‚بپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚ًکA‚ê‚ؤپAڈٌ‚à‚آ‚©‚¸‹`‘«‚ج‘«‚ًپuƒMƒVƒbپAƒMƒVƒbپv‚ئ‚«‚µ‚ـ‚¹‚ب‚ھ‚çپA‰“‚¢ژR“¹‚ًژٹش‚ً‚©‚¯‚ؤ“o‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ƒ‚ئژq‚ج•à‚فپB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚جگS‚ةپA•ƒ‚ئژR‚ةڈo‚©‚¯‚½پA‚ ‚é“ْ—j“ْ‚جˆê“ْ‚جڈo—ˆژ–‚ھپA‚ب‚؛‚©‘N–¾‚بژv‚¢ڈo‚ئ‚µ‚ؤژc‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚ئکaچ]‚حپA‘«‚جˆ«‚¢•ƒ‚ةپA‚ ‚ـ‚蕉’S‚ً‚©‚¯‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚ي‚´‚ئ‚ن‚ء‚‚è•à‚¢‚½پB“r’†پA“¥‚فگط‚è‚ھ‚ ‚ء‚½‚ھپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚حپA‰½‹C‚ب‚گو‚ة“n‚ء‚ؤ•à‚¢‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@ڈٌ‚ًژ‚ء‚ؤ—ˆ‚ب‚©‚ء‚½•ƒ‚حپA‚ر‚ء‚±‚ًˆّ‚«‚ب‚ھ‚çژپXپA‹x‚ف‚ب‚ھ‚ç•à‚‚ج‚إ’x‚©‚ء‚½پBپ@گو‚ة•à‚پu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚ة’x‚ê‚ب‚¢‚و‚¤‚ةپA‚ب‚é‚ׂ‘پ‘«‚إ‚آ‚¢‚ؤ—ˆ‚ؤ‚¢‚½‚ھپAگ³ٹى‚حپAŒ©’ت‚µ‚جˆ«‚¢“¥گط‚ج‘O‚ـ‚إ—ˆ‚é‚ئپA‹}‚ة‹ظ’£‚µ‚½ٹç‚إ—§‚؟ژ~‚ـ‚ء‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚حگU‚è•ش‚ء‚ؤ•ƒ‚ً‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@•ƒ‚حپAŒ©’ت‚µ‚جˆ«‚¢“¥گط‚إ—§‚؟ژ~‚ـ‚ء‚½‚ـ‚ـپAگg‘ج‚ھچd’¼‚µ‚½‚و‚¤‚ة‚ب‚èپA‚ب‚©‚ب‚©“n‚낤‚ئ‚µ‚ب‚©‚ء‚½پBگ³ٹى‚ج“ھ‚ةپA‚ ‚جٹُ‚ـ‚ي‚µ‚¢ژ–Œج‚ج‹L‰¯‚ھ‚و‚ف‚ھ‚¦‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚ھگS”z‚µ‚ؤ‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ة‹C‚ھ•t‚¢‚ؤپAچ¶‰E‚ً‰½‰ٌ‚àٹm”F‚·‚é‚ئˆê‹C‚ة‹}‚¬‘«‚إ“n‚ء‚½پBپ@“¥‚فگط‚è‚ً“n‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ئˆہگS‚µ‚½‚ج‚©پAپu‚³‚ پA‘پ‚و‚¤چs‚«‚ب‚³‚¢پBپv‚ئپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚ة‹êڈخ‚¢‚µ‚ب‚ھ‚牂¦‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤپA‚¨ژ›‚ج‹ك‚‚ـ‚إ—ˆ‚é‚ئپA•ƒ‚جژ–Œج‚ً•·‚¢‚ؤ‚¢‚½‚¨‚¶‚³‚ٌ‚ھ•sژv‹c‚»‚¤‚بٹç‚ً‚µ‚ؤ•à‚¢‚ؤ—ˆ‚½پBپ@•ƒ‚ھ•à‚ژp‚ة‹C‚ھ•t‚¢‚ؤپA‹ء‚«‚ب‚ھ‚畃‚ج‘«‚ً•sژv‹c‚»‚¤‚ةŒ©‚آ‚ك‚ب‚ھ‚ç•·‚¢‚½پBپuگ³ٹى‚µ‚ل‚ٌپA‚à‚¤•à‚¢‚ؤ‚à‘هڈن•v‚إ‚·‚ئ‚بپHپBپv•ƒ‚حپu‚¦‚¦پBپv‚ئˆêŒ¾‚¾‚¯“ڑ‚¦‚½پB
پ@‚»‚ج‚¨‚¶‚³‚ٌ‚حپA•ƒ‚ھڈٌ‚àژ‚½‚¸‚ة•à‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ•sژv‹c‚炵‚پA‚¢‚آ‚ـ‚إ‚àŒم‚ë‚©‚çٹ´گS‚µ‚ؤŒ©‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹ê“ï‚ج’JپB
پ@چ،ˆن‰ئ‚ج’iپX”¨‚جژR‚حپA‚¨ژ›‚ج‰،‚ج“¹‚©‚ç“o‚ء‚ؤ‚ن‚©‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@ژRگ…‚ھƒ`ƒ‡ƒچƒ`ƒ‡ƒچ‚ئ—¬‚ê‚éڈ¬“¹‚ً“o‚ء‚ؤ‚¢‚‚ئپAٹâ‚ھƒSƒچƒSƒچ‚µ‚½پAŒ¯‚µ‚¢‹}ژخ‚ھ‘±‚¢‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ج“¹‚حƒRƒP‚âƒVƒ_‚ھ‚½‚‚³‚ٌگ¶‚¦‚ؤ‚¢‚ؤپA”–ˆأ‚¢Œk’J‚ً—ر‚ھ”ي‚¢”ي‚³‚é‚و‚¤‚ة–خ‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚حپAگو‚ة‘ه‚«‚بٹâ‚جڈم‚ًپuƒsƒ‡ƒ“ƒsƒ‡ƒ“پv‚ئ”ٍ‚ر‰z‚¦‚ؤگgŒy‚ة“o‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@‚¾‚ھپA•ƒ‚ھ“o‚ء‚ؤ—ˆ‚é‚ج‚ھ‚₯‚ة’x‚¢‚ج‚إپA‚µ‚خ‚ç‚“ٌگl‚حپAٹâ‚ج–T‚إ‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پu•ƒ‚؟‚ل‚ٌپA’x‚¢‚ثپBپvپu‚¤پ[‚ٌپA‚»‚¤‚ثپBپv“ٌگl‚حگخ‚ًڈE‚ء‚½‚肵‚ب‚ھ‚çپA‚ا‚¤‚µ‚½‚ç‚¢‚¢‚©پH‚ئپAŒثکf‚ء‚ؤ‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚¤‚±‚¤‚µ‚ؤپA‚¢‚邤‚؟‚ةپA‚س‚ئگU‚è•ش‚é‚ئپAٹâ‚ة•ƒ‚جژè‚ھŒ»‚ي‚ꂽپB
پ@‚و‚¤‚â‚ٹâ‚ً‚و‚¶“o‚ء‚ؤ—ˆ‚½•ƒ‚حپA‹`‘«‚ج‘«‚ًژè‚إ•ّ‚¦‚ب‚ھ‚çپAٹâ‚جڈم‚ة‘«‚ًڈو‚¹‚ؤڈم‚ھ‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚¾‚ھ‹`‘«‚ج‘«ژٌ‚ھ‹ب‚ھ‚ç‚ب‚¢‚ج‚إپA‘«ڈê‚ھ‚·‚ׂء‚ؤپA’‡پXژv‚¤‚و‚¤‚ة“o‚ê‚ب‚©‚ء‚½پBپi‹êکJ‚µ‚ؤ‚¢‚镃‚ةپA‰½‚©ژèڈ•‚¯ڈo—ˆ‚ب‚¢‚¾‚낤‚©پcپBپj‚ئپA“ٌگl‚حٹç‚ًچ‡‚ي‚¹‚ؤŒ©‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚à‚ا‚©‚µ‚»‚¤‚ةŒ©‚ؤ‚¢‚éپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚ةپA–ع‚ھچ‡‚¤‚ئپA•ƒ‚جٹç‚ھ‹}‚ة•|‚¢ٹç‚ة‚ب‚ء‚½پBپu‚±‚çپIپA‚¨‘O‚½‚؟پA‚³‚ء‚³‚ئ‘پ‚گو‚ةچs‚©‚ٌ‚©پIپBپv‹}‚ةپAگl‚ھ•د‚ء‚½—l‚ة‘هگ؛‚ًڈo‚µ‚ؤپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚ً’ا‚ء•¥‚¤‚و‚¤‚ة‚µ‚½پB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟“ٌگl‚حپA•ƒ‚ج“{چ†‚ة‹ء‚¢‚½پB‚ ‚ـ‚è‚ة‚à“ث‘RپA“{–آ‚ç‚ꂽ‚ج‚إپA‚ ‚ي‚ؤ‚ؤ“¦‚°‚é‚و‚¤‚ةپA‹}‚¢‚إگو‚ة“o‚ء‚ؤچs‚ء‚½پB‚³‚ء‚«‚ـ‚إپA‚ ‚ٌ‚ب‚ة‰¸‚â‚©‚¾‚ء‚½‚ج‚ةپA‹}‚ة“{‚肾‚·•ƒ‚ج‹Cژ‚؟‚ھ‘S‚—‰ً‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@‚±‚جچ ‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚ح‚ـ‚¾—c‚پA‘«‚جˆ«‚¢•ƒ‚ج‹Cژ‚؟‚ھ”»‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB“{‚ç‚ê‚éژ–‚إپAپi‚±‚ج”–ˆأ‚¢چâ‚حپAŒˆ‚µ‚ؤ•ƒ‚ئˆêڈڈ‚ة‚ح“o‚ء‚ؤ‚ح‚¢‚¯‚ب‚¢‚ٌ‚¾پcپBپj‚ئ–َ‚à”»‚炸ژv‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پBپ@•ƒ‚حپA‚»‚ج‚ ‚ئڈ‚µ‚¸‚آ”‡‚¤‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤپA‹êکJ‚µ‚ؤ“o‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½‚ج‚¾‚낤‚ھپA•ƒ‚حپA‚»‚جژS‚ك‚بژp‚ًپAژq‹ں‚½‚؟‚ة‚حŒˆ‚µ‚ؤŒ©‚¹‚و‚¤‚ئ‚ح‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚½‚ئ‚¦•ƒ‚ھ‘«‚ھ•sژ©—R‚إ‚àچ\‚ي‚ب‚©‚ء‚½پB‚ا‚ٌ‚ب•ƒ‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚à‘هچD‚«‚ب•ƒ‚ئˆêڈڈ‚ةپAگFپX‚ئکb‚µ‚ً‚µ‚ب‚ھ‚ç“o‚肽‚©‚ء‚½‚ج‚ةپA‚±‚±‚ةچ·‚µٹ|‚©‚é‚ئپAŒˆ‚ـ‚ء‚ؤ‹}‚ة’ا‚¢•¥‚¤‚و‚¤‚ة“{–آ‚ç‚ê‚é‚ج‚ھ”ك‚µ‚©‚ء‚½پB
پ@•ê‚جƒ`ƒJ‚ھژR‚جڈم‚ج•û‚إژdژ–‚µ‚ؤ‚é‚ئپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚¾‚¯‚ھ“o‚ء‚ؤ‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚½پBپu•ƒ‚؟‚ل‚ٌ‚ح‚ا‚¤‚µ‚½‚ئ‚ثپHپBپvپ@ƒ`ƒJ‚ح•·‚¢‚½پBپuŒم‚إپA—ˆ‚و‚ٌ‚µ‚ل‚ پBپvپu‰½‚إˆêڈڈ‚ة—ˆ‚ٌ‚â‚ء‚½‚ئ‚ثپBپvپu‚¾‚ء‚ؤپAگو‚ةچs‚¯‚ء‚ؤŒ¾‚ي‚ꂽ‚à‚ٌپcپBپvپu‚»‚¤‚ثپcپBپvپ@ƒ`ƒJ‚حپAگ³ٹى‚ھˆêگl‚إ‹êکJ‚µ‚ب‚ھ‚ç“o‚ء‚ؤ‚‚éژp‚ً‘z‘œ‚µ‚ؤپA–³ژ–‚ة“o‚ء‚ؤ—ˆ‚ê‚é‚©‚ا‚¤‚©پAگS”z‚إژd•û‚ھ–³‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”E‘د‚ج•ƒپB
پ@‚â‚ھ‚ؤپA’‹‹ك‚‚ة‚ب‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚¾‚¢‚شŒo‚ء‚ؤ‚©‚çپA•ƒ‚ح‚و‚¤‚â‚“o‚ء‚ؤ—ˆ‚½پBپ@•ê‚حپAگ³ٹى‚ھژè“`‚¢‚ة—ˆ‚ؤ‚‚ê‚邾‚¯‚إٹً‚µ‚©‚ء‚½‚ھپAپi‘«‚جˆ«‚¢گ³ٹى‚ھژR‚ة“o‚ء‚ؤ—ˆ‚邱‚ئ‚¾‚¯‚إ‚àچ“‚¾پBپj‚ئٹ´‚¶‚½پBپi–¾“ْ‚جژdژ–‚ةچ·‚µ‚آ‚©‚¦‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پcپBپj‚ئگS”z‚µ‚½پB
پ@‚¾‚ھپA•ƒ‚à‚ف‚ٌ‚ب‚ھ“‚¢‚ؤ‚¢‚éژپAˆêگl‚¾‚¯‚إ‰ئ‚ج’†‚ة‚¢‚é‚و‚è‚àپAژR‚ة“o‚ء‚ؤپA’g‚©‚¢“ْچ·‚µ‚ً—پ‚ر‚ب‚ھ‚çپA‚ف‚ٌ‚ب‚ج–T‚إ‰½‚©ژè“`‚¢‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚©‚ء‚½‚ج‚¾پB
پ@•ƒ‚حپA‚ق‚µ‚ë‚جڈم‚ة‹`‘«‚ج•ذ‘«‚ًگL‚خ‚µ‚½‚ـ‚ـچہ‚ء‚ؤپA•ê‚جژè“`‚¢‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپ@“ٌگl‚ج‰،‚ة‚حپA“yژè‚ج‰،‚©‚çژخ‚ك‚ةگ¶‚¦‚½ƒoƒ‰ƒ“ƒX‚جˆ«‚¢–ط‚ھگ¶‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ•sژv‹c‚¾‚ء‚½پB‚»‚ج–ط‚حژل‚¢•c–ط‚جچ پA’N‚©‚ة“¥‚ف‚آ‚¯‚ç‚ꂽ‚ج‚©چھŒ³‚ھژخ‚ك‚ة‹ب‚ھ‚ء‚½‚ـ‚ـپA‹َ‚ةگ^‚ء’¼‚®‚ةŒü‚©‚ء‚ؤگL‚ر‚ؤ‚¢‚½پBپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚»‚ج–ط‚ًŒ©‚邽‚ر‚ةپAڈo—ˆ‚é‚ب‚ç‚ن‚ھ‚ٌ‚¾چھŒ³‚ً‰½‚ئ‚©’¼‚µ‚½‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚à‚ح‚â–³—‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@ژR‚ة“o‚é‚ئژٹش‚ھ‰ك‚¬‚é‚ج‚ھ‘پ‚ٹ´‚¶‚½پBڈu‚ٹش‚ة‚ك‚ـ‚¢‚ھ‚·‚é‚و‚¤‚ب’‹‚ة‚ب‚ء‚½‚©‚ئژv‚¤‚ئپA“ْ‚حگ¼‚ج•û‚ةŒX‚¢‚ؤ•é‚ê‚ؤ‚¢‚ء‚½پBپ@—[“ْ‚ً—پ‚ر‚ب‚ھ‚çپA‚ف‚ٌ‚ب‚إƒٹƒ„ƒJپ[‚ً‰ں‚µ‚ب‚ھ‚ç‹A‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@“r’†پAڈ¬گى‰ˆ‚¢‚ج‘گ‚ج‚½‚‚³‚ٌ‚¨‚¢–خ‚铹‚ةچ·‚µٹ|‚©‚ء‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA•ƒ‚ج‘O‚ةگو‚ة•à‚¢‚ؤگ ‚è‘«‚إ•à‚¢‚½پB‚»‚ê‚ة‚ح——R‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@•پ’iپAژo‚½‚؟‚ھ‚و‚‘گ‚ًŒ‹‚ٌ‚إگl‚ً‚آ‚ـ‚¸‚©‚¹‚é—V‚ر‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚»‚جŒ‹‚ٌ‚¾‚ـ‚ـ‚إ–Y‚ê‚ؤ‚¢‚½‘گ‚ةپA•ƒ‚ھ‘«‚ًژو‚ç‚ê‚ؤ“]‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚½پBپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚ح•ê‚©‚çپAپu•ƒ‚؟‚ل‚ٌ‚ئ•à‚ژ‚حپAگو‚ة•à‚¢‚ؤŒ‹‚ٌ‚¾‘گ‚ھ‚ب‚¢‚©‚ا‚¤‚©پAگ ‚è‘«‚إ‚و‚ٹm”F‚µ‚ب‚ھ‚ç•à‚«‚ب‚³‚¢‚وپIپBپv‚ئ—@‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾پB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚±‚ج“¹‚ة—ˆ‚é‚ئپAگو‚ة•à‚¢‚ؤگ ‚è‘«‚إ•à‚¢‚½پBŒ‹‚ٌ‚¾‚ـ‚ـ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‘گ‚ًŒ©‚آ‚¯‚é‚ئپA‹}‚¢‚إ‘«‚ً“ü‚ê‚ؤ—ح‚¢‚ء‚د‚¢ˆّ‚«‚؟‚¬‚ء‚½پB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حگو‚ة‘پ‚•à‚«‰ك‚¬‚ؤ‚س‚ئگU‚è•ش‚é‚ئپA‘«‚جˆ«‚¢•ƒ‚ًگS”z‚µ‚ب‚ھ‚çپAˆêگl‚إڈd‚¢ƒٹƒ„ƒJپ[‚ًˆّ‚•ê‚جژp‚ھ‚ ‚ء‚½پB‚»‚جژ‚ج—[“ْ‚ً—پ‚ر‚½•ƒ‚ئ•ê‚ج“ٌگl‚جژp‚ھپA‰½Œج‚©ژ©•ھ‚ج’m‚ç‚ب‚¢پA‰“‚¢‰ك‹ژ‚جƒCƒپپ[ƒW‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ئڈd‚ب‚ء‚½پBپ@‚ظ‚ٌ‚ج‚ي‚¸‚©‚جڈuٹشپAƒtƒ‰ƒVƒ…‚ً•°‚¢‚½ژ‚ج‚و‚¤‚ةƒpƒb‚ئ‹P‚¢‚ؤ•‚‚©‚ٌ‚إ‚¢‚½پB
پ@‚»‚ê‚ھˆê‘ج‰½‚ب‚ج‚©پHپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚ة‚ح”»‚ç‚ب‚©‚ء‚½پBپ@•sژv‹c‚ئپA‚»‚جژ‚ج—[•é‚ê‚ج•—Œi‚ھپA‚»‚جŒم‚àپu‚ـ‚±‚ئپv‚ج“ھ‚ج’†‚ة‚¢‚آ‚ـ‚إ‚àˆَڈغ‚ةژc‚ء‚½پB
پ@‚±‚¤‚µ‚ؤ‰ئ‚ة’…‚¢‚½چ ‚ة‚حپA‚·‚ء‚©‚è“ْ‚ھ•é‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢پAگ^‚ءˆأˆإ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@—‚“ْ‚ة‚ب‚é‚ئ•ƒ‚حپA‚à‚¤’©‘پ‚‚©‚ç”و‚ê‚àŒ©‚¹‚¸‚ة‰ïژذ‚ةڈo‚©‚¯‚ؤچs‚ء‚½پB‚»‚µ‚ؤپA‚ـ‚½ˆê“ْ’†گù”ص‚ج‘O‚ة—§‚؟‘±‚¯‚ؤپA“S‚ًچي‚éژdژ–‚ًˆêڈTٹشŒJ‚è•ش‚µ‚ؤ‚¢‚پB
پ@‚¾‚ھپA‚³‚·‚ھ‚ة”و‚ê‚ھڈo‚ؤ‚«‚½‚ج‚©پAژdژ–‚ھڈI‚ي‚é‚ئپA‹Dژش‚ج—ˆ‚éژٹش‚ـ‚إ‚جٹشپAژً‰®‚ة—§‚؟ٹٌ‚ء‚ؤƒLƒ…ƒEپ[‚ئˆê”tˆù‚ٌ‚إ”و‚ê‚ً–ü‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‹Dژش‚ج’†‚إچہ‚ê‚éژ‚ح—ا‚©‚ء‚½‚ھپA–ˆُ‚إچہ‚ê‚ب‚¢ژ‚à‚ ‚ء‚½پB
پ@ƒwƒgƒwƒg‚ة•à‚«”و‚ê‚ؤپA‚â‚ء‚ئ‰ئ‚ة‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚½ژپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚ھپAپi•ƒ‚ة—V‚ٌ‚إ–ل‚¨‚¤پBپj‚ئ‹كٹٌ‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB‚¾‚ھپA•ƒ‚حپA’ة‚ق‘«‚ً’÷‚ك•t‚¯‚é‹`‘«‚ًڈ‚µ‚إ‚à‘پ‚‚ح‚¸‚µ‚ؤ‰،‚ة‚ب‚肽‚©‚ء‚½پB‚ـ‚ئ‚ي‚è‚آ‚پu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚ًپA‚ي‚¸‚ç‚ي‚µ‚»‚¤‚ةŒ©‚¨‚낵‚½پBپu‚±‚çپIپA‚¨‘O‚½‚؟پA‚ـ‚¾‹N‚«‚ئ‚¤‚ئ‚©پIپA‚³‚ء‚³‚ئ‘پ‚گQ‚ç‚ٌ‚©پIپBپv‚ئ‘ه‚«‚بگ؛‚ًڈo‚µ‚ؤژ¶‚è‚آ‚¯‚½پB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA—•sگs‚ة‘هگ؛‚إ“{‚ç‚ê‚é‚ئپA‰½Œج“{‚ç‚ê‚é‚ج‚©”»‚炸پA”ك‚µ‚»‚¤‚ة“ٌٹK‚ةڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@‚»‚êˆب—ˆپA•ƒ‚ھ‰ïژذ‚©‚ç‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‚àپi—V‚ٌ‚إ–ل‚¨‚¤‚ئ‚ق‚â‚ف‚ة•ƒ‚ة‹كٹٌ‚ء‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پcپBپj‚ئژv‚¢چ‚ٌ‚إ‚¢‚ء‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒ`ƒJ‚ج’mŒbپB
پ@”_”ةٹْ‚ج‹Gگك‚ة‚ب‚ء‚½پB‘ٹ•د‚ي‚炸پAƒ`ƒJ‚ئƒ[ƒ“‚ح“ٌگl‚إ”_چى‹ئ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‹I’j‚ح‚à‚¤’†ٹwگ¶‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚؟‚ه‚¤‚اٹْ––ژژŒ±‚ھژn‚ـ‚èپAŒك‘O’†‚إ‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚é‚ئپA–¾“ْ‚جژژŒ±‚ةڈo‚éڈˆ‚ًٹJ‚¢‚ؤ•×‹‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚ئ‚±‚ë‚ھپA‚½‚ـ‚½‚ـ—pژ–‚ھ—L‚ء‚ؤ‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚½ƒ[ƒ“‚حپA‚»‚ٌ‚ب‹I’j‚جژp‚ًŒ©‚é‚ئپAƒJƒb‚ئ‚ب‚ء‚ؤŒ¾‚ء‚½پBپu‹I’jپIپA‰½‚©‚¨‘O‚حپA‹àژ‚؟‚ج–V‚؟‚ل‚ٌ‚ج‚²‚ئ‚µ‚ؤپA“c‚ٌ‚ع‚جژè“`‚¢‚à‚¹‚ٌ‚إ•×‹‚خ‚ء‚©‚肵‚ؤپIپBپvپu‚¤پcپEپBپvپuٹwچZ‚ھڈI‚ي‚ء‚½‚ç‚·‚®ژR‚ةژè“`‚¢‚ة—ˆ‚ٌ‚©پIپBپv‚ئ“{‚ء‚½پBپ@
پ@ژژŒ±’†‚ةپAٹwچZ‚ھ‘پ‚ڈI‚ي‚é‚ج‚حپA–¾“ْ‚ة”ُ‚¦‚ؤ•×‹‚·‚邽‚ك‚إ‚ ‚ء‚½پB‚¾‚ھپAƒ[ƒ“‚ة‚حپAژژŒ±‚ج‚½‚ك‚ة‘پˆّ‚¯‚·‚é‚ئ‚¢‚¤پA‚»‚جˆس–،‚ھ‘S‚”»‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@‚»‚ج“ْ‹I’j‚حپAƒ[ƒ“‚ة“{‚ç‚ê‚ؤ‚àپA•×‹‚·‚邽‚ك‚ةژR‚ة‚حچs‚©‚ب‚©‚ء‚½پB‚â‚ھ‚ؤ‘c•ê‚حپA“ْ‚ھ•é‚ê‚ؤ‚‚½‚ر‚ê‚ؤ‹A‚ء‚ؤ‚‚é‚ئپAپu‹I’jپA‚¨‘O‚حچ،“ْپA‰½‚إژR‚ة—ˆ‚ٌ‚â‚ء‚½‚ئ‚©پIپBپvژè“`‚¢‚ة—ˆ‚ب‚©‚ء‚½‹I’j‚ة• ‚ً—§‚ؤپA‚±‚ئ‚³‚ç‚ةپA‚«‚آ‚ژ¶‚ء‚½پB‹I’j‚حگà–¾‚µ‚ؤ‚à’ت‚¶‚ب‚¢ƒ[ƒ“‚ة‰½‚àŒ¾‚¦‚¸پA‹ƒ‚«‚»‚¤‚بٹç‚ً‚µ‚ؤ–ظ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپAƒ[ƒ“‚ةژ¶‚ç‚ê‚é‹I’j‚ج‰،ٹç‚ًŒ©‚ب‚ھ‚ç‰آˆ£‘ٹ‚ة‚ب‚ء‚½پB‚µ‚خ‚ç‚پAپi‚ا‚¤‚µ‚½‚ç‚¢‚¢‚¾‚낤‚©پHپBپj‚ئژvˆؤ‚µ‚½پBپ@‚»‚جژپAƒ`ƒJ‚ج”]— ‚ة‚¢‚¢ƒAƒCƒfƒA‚ھ•‚‚©‚ٌ‚¾پB‚»‚ء‚ئ‹I’j‚ج‚ئ‚±‚ë‚ة‹كٹٌ‚ء‚½پB
پ@پu‹I’jپA‚ ‚ٌ‚½–¾“ْ‚©‚狳‰بڈ‘‚ًژ‚ء‚½‚ـ‚ـژR‚ة—ˆ‚ؤپA”k‚؟‚ل‚ٌ‚ةˆê‰ٹ炾‚¯Œ©‚¹‚ب‚³‚¢پBŒم‚حڈ¬‰®‚إ‚¢‚‚ç‚إ‚à•×‹ڈo—ˆ‚é‚â‚낤‚ھپB”k‚؟‚ل‚ٌ‚ة‚حپA‚¤‚؟‚ھ“K“–‚ةپiچ،‰×•¨‚ً‰^‚ٌ‚إچs‚ء‚½پBپj‚ئ‚©پA“K“–‚ةŒ¾‚ء‚ئ‚‚©‚çپAŒم‚ح‹A‚è‚ةˆêڈڈ‚ة‹A‚ê‚خ‹C•t‚©‚ê‚ٌ‚©‚çپA‚»‚¤‚µ‚ب‚³‚¢پBپv‚ئ—@‚µ‚½پBپ@‹I’j‚حپA‚»‚جƒAƒCƒfƒA‚ً•·‚«‚ب‚ھ‚çپA•ê‚ج‘fگ°‚µ‚¢’mŒb‚ةŒh•‚µ‚ب‚ھ‚çپu‚¤‚ٌپBپv‚ئ‚¤‚ب‚¸‚¢‚½پB
پ@‚ ‚‚é“ْپA‹I’j‚حپAٹwچZ‚ھڈI‚ي‚é‚ئ‚·‚®‚ةپAƒJƒoƒ“‚ًژ‚ء‚ؤ‚»‚ج‚ـ‚ـژR‚ة“o‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پBپ@‹I’j‚حپAژR‚ة“o‚ء‚ؤ—ˆ‚é‚ئپAˆêگ¶Œœ–½‚ة•ê‚جژè“`‚¢‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚éژp‚ً‚ي‚´‚ئƒ[ƒ“‚ةŒ©‚¹‚½پBƒ[ƒ“‚ح‚»‚جژp‚ًŒ©‚é‚ئپAپu‚¨‚¨پA‹I’jپA‚و‚¤ژè“`‚¢‚ة—ˆ‚½‚ثپBچ،“ْ‚حڈ‹‚©‚ثپ[پBپv‚ئ‚ث‚¬‚炤‚ئپA”[“¾‚µ‚½‚ج‚©پA‹@Œ™—ا‚‚ب‚ء‚ؤپA‚ـ‚½ˆî•ن‚ًڈW‚ك‚ةڈم‚ج“c‚ٌ‚ع‚ةچs‚ء‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚ھ–ع”z‚¹‚·‚é‚ئپA‹I’j‚ح‚·‚®‚ة‚¢‚ب‚‚ب‚ء‚½پBڈ¬‰®‚ة–ك‚é‚ئپAƒڈƒ‰‚ج‰A‚إ‚µ‚ء‚©‚è•×‹‚µ‚½پBپ@‚µ‚خ‚ç‚‚µ‚ؤƒ[ƒ“‚ھ–ك‚ء‚ؤ—ˆ‚½پBپ@‚½‚ء‚½چ،‚¢‚½‚ج‚ة‹I’j‚ھ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إپAƒLƒ‡ƒچƒLƒ‡ƒچ‚µ‚ب‚ھ‚çپAپu‚ ‚çپH‹I’j‚ح‚ا‚¤‚µ‚½‚ئ‚بپHپBپv‚ئپA•·‚¢‚½پBپuچ،پA‰؛‚ة‰×•¨‚ً‰^‚ٌ‚إچs‚©‚¹‚ـ‚µ‚½‚¯‚ٌپBپv‚ئپAƒ`ƒJ‚ح“K“–‚ب‚±‚ئ‚ًŒ¾‚ء‚½پBپu‚ ‚ ‚»‚¤‚بپA‚سپ[‚ٌپBپv‚ئپA‹^‚¤—lژq‚à‚ب‚”[“¾‚µ‚ؤپA‚ـ‚½‹ڈ‚ب‚‚ب‚ء‚½پB
پ@‹I’j‚ھ‚·‚ء‚©‚è•×‹‚µڈI‚ي‚éچ پAگش‚¢—[“ْ‚ھپA‹َ‚ًگُ‚ك‚©‚¯‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ë‚»‚ë‹A‚éچ ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB•ê‚ھŒؤ‚ر‚ة—ˆ‚½پBپu‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌ‚ھ‚»‚ë‚»‚ëڈ¬‰®‚ة–ك‚ء‚ؤ—ˆ‚ç‚·‚وپBپvپ@‹I’j‚حپA‹A‚è‚ة’S‚¢‚إ‚¢‚‰×•¨‚ج’†‚ةƒJƒoƒ“‚ً‚»‚ء‚ئ‰B‚µپA‚»‚ê‚ً”w’†‚ة’S‚¢‚إ‚¢‚½پB
پ@‚µ‚خ‚ç‚‚·‚é‚ئƒ[ƒ“‚ھچ~‚è‚ؤ—ˆ‚½پB‹I’j‚جژp‚ًŒ©‚é‚ئپA‚ـ‚¾چ،‚ـ‚إژè“`‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚ئژv‚¢چ‚ٌ‚إپAپu‚¨‚¨پA‹I’jپAچ،“ْ‚حپA‚ت‚ء‚©‚½‚ثپ[پA‚«‚آ‚©‚ء‚½‚낤پHپBپv‚ئ—D‚µ‚گ؛‚ً‚©‚¯‚ؤ‚ث‚¬‚炤‚ج‚¾‚ء‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚ح‹I’j‚ة–ع”z‚¹‚µ‚ب‚ھ‚çپAڈ‚µ—اگS‚ج™èگس‚ًٹ´‚¶‚½‚ھپAٹF‚ھ‚¨Œف‚¢‚ة‚¤‚ـ‚‚¢‚‚½‚ك‚جپA‚â‚ق‚ً“¾‚ب‚¢‰R‚à‚ ‚邱‚ئ‚ً–³Œ¾‚إ‹I’j‚ة‹³‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—حژ‚؟پB
پ@‚±‚¤‚µ‚ؤ‹I’j‚حپAˆê“r‚بگS‚ًژ‚آƒ[ƒ“‚ًپA‚¤‚ـ‚‚©‚ي‚µ‚ؤ‚¢‚’mŒb‚ً•ê‚©‚çٹw‚ٌ‚إ‚¢‚ء‚½پB
‚¾‚ھپA‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌ‚ئ•ê‚جڈ—ژ肵‚©‚¢‚ب‚¢’†پA‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚à—ح‚ج—v‚éپA‚«‚آ‚¢ژdژ–‚¾‚¯‚حپA‹I’j‚جژdژ–‚ة‚ب‚é‚ج‚¾‚ء‚½پB‚»‚ê‚©‚ç‚حپA‚µ‚ء‚©‚è•×‹‚µ‚½‚ ‚ئ‚حپAƒ`ƒJ‚ھڈ‚µ‚إ‚àٹy‚ة‚ب‚é‚و‚¤‚ة‚ئپAڈd‚¢‚à‚ج‚ً‰^‚شژdژ–‚ًگi‚ٌ‚إژè“`‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@‚ـ‚¾پA‚±‚جچ ‚حپAژR‚جڈم‚ج‚ظ‚¤‚ـ‚إƒٹƒ„ƒJپ[‚ھ’ت‚ê‚éپuژR“¹پv‚حڈo—ˆ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB‚¨ژ›‚ج‘O‚ج‚ ‚؛“¹‚ةƒٹƒ„ƒJپ[‚ً’u‚¢‚ؤپA“k•à‚إ“o‚邵‚©‚ب‚©‚ء‚½پB‹I’j‚حپAڈ¬‚³‚¢چ ‚©‚çپA•ؤ‚ً‹l‚ك‚½ڈd‚¢ƒJƒ}ƒX‚ً”w’†‚ة’S‚¢‚إپAگخ‚ھƒSƒچƒSƒچ‚ ‚é”–ˆأ‚¢Œk’J‚ج‹}‚بچ⓹‚ًپA‰½“x‚àچ~‚肽‚è“o‚ء‚½‚肵‚ؤƒٹƒ„ƒJپ[‚ـ‚إ‰^‚ٌ‚إ‚¢‚½پB
پ@‹I’j‚حپA•ê‚ة‘م‚ي‚ء‚ؤ—حژdژ–‚خ‚©‚肵‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©‘«چک‚ھڈن•v‚ة‚ب‚ء‚ؤپAƒKƒbƒ`ƒٹ‚µ‚½‘جٹi‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB‹گx‚ب‘ج—ح‚ًژ‚آپA‚½‚‚ـ‚µ‚¢ڈ”N‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@‚ ‚é“ْپAٹwچZ‚إپu‰“‘«پv‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA‚ف‚ٌ‚ب‰“‚‚جژR‚ة“o‚ء‚ؤ”و‚ê‚ؤ‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB‚¾‚ھپA‹I’j‚حپA”و‚ꂽ‚»‚ش‚è‚ج‚ف‚¶‚ٌ‚àŒ©‚¹‚ب‚¢‚إپA‚»‚ج‚ـ‚ـژR‚ة“o‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤپA”_چى‹ئ‚ًژè“`‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپ@‚»‚ٌ‚ب‹I’j‚جژp‚ًŒ©‚ؤپAژR‚جک[‚ةڈZ‚قپA“¯‚¶“¯‹‰گ¶‚ج‘§ژq‚ًژ‚آپA‚¨‚¶‚³‚ٌ‚ھ‹ء‚¢‚ؤŒ¾‚ء‚½پBپu‚¤‚؟‚ج‘§ژq‚حپA‰“‘«‚©‚ç‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚çپAپi‚«‚آ‚©‚ء‚½پ[پBپj‚ئ‚¢‚ء‚ؤ•”‰®‚إƒOƒbƒ^ƒٹگQچ‚ë‚ٌ‚إپA‚¢‚ء‚؟‚ه‚ٌ“®‚©‚ٌ‚ئ‚ةپA‚ ‚ٌ‚½‚ٌ‚ئ‚±‚ج‘§ژq‚حپA‚¦‚ç‚¢‹گx‚بگg‘ج‚µ‚ئ‚é‚ب‚ پ[پBپvپu‚¦پcپBپv
پ@
پ@‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©پA‹I’j‚ح‹كڈٹ‚إ•]”»‚جپAپu—حژ‚؟‚جƒKƒL‘هڈ«پv‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپuٹwŒ|‰ïپv‚إ‚حپAپu“چ‘¾کYپv‚ج‹S‚ھ“‡‚ةڈZ‚قپu‹S‚ج‘هڈ«پv‚ة”²‚ؤ‚«‚³‚ꂽ‚ظ‚اپAƒKƒbƒ`ƒٹ‚ئ‚µ‚½‘جٹi‚¾‚ء‚½پB‚â‚ھ‚ؤپAپu‘ٹ–o•”پv‚âپuڈ_“¹•”پvپAپuŒ•“¹•”پvپA‰½‚إ‚àڈo—ˆ‚éپAƒXƒ|پ[ƒc–œ”\‚جگlٹش‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پBپ@‹كڈٹ‚ج“¯‹‰گ¶‚حپAƒKƒbƒ`ƒٹ‚µ‚½‘جٹi‚ج‹I’j‚ًŒ©‚ؤپAپu‚¨پ[‚¢پAƒSƒٹƒ‰پIپBپv‚ئ—â‚â‚©‚µ‚ؤŒؤ‚ٌ‚¾پB
پ@ˆê•ûپAٹأ‚â‚©‚³‚ê‚ؤˆç‚ء‚½’ي‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚ج•û‚حپA‹•ژم‘جژ؟‚جپAگü‚جچׂ¢گlٹش‚إ‚ ‚ء‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپAˆّ‚ءچ‚فژvˆؤ‚جپA“à‹C‚إ’p‚¸‚©‚µ‚ھ‚è‚â‚إ‚ ‚ء‚½پBپu—c’t‰€‚جٹwŒ|‰ïپv‚إ‚حپAپu‰Y“‡‘¾کYپv‚ًŒ}‚¦‚éپA‰³•P‚³‚ـ‚ج–T‚ةژک‚éپu—³‹{ڈé‚جژq‹›‚جˆê•Cپv‚ً‰‰‚¶‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤگ^گV‚µ‚¢ژR”§‚ھچي‚ç‚êپA‚‚ث‚‚ث‚ئ‹ب‚ھ‚ء‚½پuژR“¹پv‚ھڈo—ˆ‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پBڈd‚¢•ؤ•U‚ً’S‚ھ‚¸‚ةپA‚â‚ء‚ئƒٹƒ„ƒJپ[‚ةگد‚ٌ‚إˆّ‚ء’£‚ء‚ؤ‰^‚ׂé‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@ٹ ‚è“ü‚ê‚ھڈI‚ي‚èپAƒJƒ}ƒX‚ة‹l‚ك‚½•ؤ•U‚ً‚½‚‚³‚ٌگد‚ٌ‚إپA‚ف‚ٌ‚ب‚إ‹ب‚ھ‚è‚‚ث‚ء‚½ژR“¹‚ً‰ں‚µ‚ؤ‹A‚ء‚ؤچs‚ء‚½پBپ@ŒZ‚ج‹I’j‚ھ‘O‚إˆّ‚ء’£‚èپA—ح‚ج–³‚¢پu‚ـ‚±‚ئپv‚àچک‚ة“ê‚ً‚‚‚ء‚ؤپAگو“ھ‚إˆّ‚ء’£‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚±‚ج‹êکJ‚جژv‚¢ڈo‚ج‚½‚‚³‚ٌ‹l‚ـ‚ء‚½ژR‚àپA‚â‚ھ‚ؤژè•ْ‚·‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚پB‚¨ژ›‚جڈم‚ة‚ ‚é“c‚ٌ‚ع‚جˆê”ش’¸ڈم‚ة‚ ‚éچ،ˆن‰ئ‚جژR‚ة‚حپAƒIƒŒƒ“ƒWگF‚ج‰تژہ‚ھ‹P‚ژ‚ھ—ˆ‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@‘پ‚ئ‚؟‚è‚ج‘z‘œ—حپB
پ@ ƒVƒ}پiƒ`ƒJ‚جژoپj‚ج–؛پA•qچ]‚ھ‰إ“ü‚è‚·‚邱‚ئ‚ةŒˆ‚ـ‚ء‚½پBƒ`ƒJ‚حپA‰½‚©‚¨ڈj‚¢‚ة‚ب‚é‚à‚ج‚ً‘{‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚ ‚é“ْپA‹ك‚‚جپuکa‘•“Xپv‚ة“ü‚ء‚ؤŒ©‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‰½–œ‰~‚à‚·‚éمY—ي‚بپuگU‚葳‚ج’…•¨پv‚ھ”hژè‰ك‚¬‚é‚ئ‚¢‚¤——R‚¾‚¯‚إپA”¼’l‹ك‚‚إ”„‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ًŒ©‚آ‚¯‚½پB
پ@‰ئ‚ًŒڑ‚ؤ‚½‚خ‚©‚è‚إ—]—T‚ج‚ب‚©‚ء‚½ƒ`ƒJ‚ة‚حپA‚»‚ج’…•¨‚ھپA‰إ‚ةچs‚•qچ]‚ج‚½‚ك‚ة—pˆس‚³‚ê‚ؤ—^‚¦‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚ج‚و‚¤‚ةژv‚¦‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚حپA‚³‚ء‚»‚‚»‚ج’…•¨‚ً•ï‚ٌ‚إ–ل‚ء‚ؤپAچ‚’lژD‚ً‚آ‚¯‚½‚ـ‚ـ‘هژ–‚ةƒ^ƒ“ƒX‚ة‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@‚ئ‚±‚ë‚ھپAƒ[ƒ“‚ح‚ ‚é“ْپAƒ`ƒJ‚جƒ^ƒ“ƒX‚ًٹJ‚¯‚ؤپA‚ب‚¨‚µ‚ؤ‚ ‚ء‚½”hژè‚ب’…•¨‚ًŒ©‚آ‚¯‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB‰½–œ‚à‚·‚é’lژD‚ًŒ©‚ؤ‹ء‚¢‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پBƒ[ƒ“‚حپAپi‚ؤ‚ء‚«‚èƒ`ƒJ‚ھژ©•ھ‚إ’…‚邽‚ك‚ةپA‚±‚ٌ‚بچ‚‰؟‚ب’…•¨‚ً‚ف‚ٌ‚ب‚ة–ظ‚ء‚ؤ”ƒ‚ء‚ؤ‰B‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾پBپj‚ئ‘پچ‡“_‚µ‚½پB
پ@ƒ[ƒ“‚حپi‚»‚ج’lژD‚ًڈط‹’‚ة‚µ‚ؤپA‚¢‚آ‚©Œم‚إƒ`ƒJ‚ً‚ئ‚ء‚؟‚ك‚ؤ‚â‚낤پcپEپBپj‚ئپA‚¹‚ء‚©‚مY—ي‚ة•t‚¢‚ؤ‚¢‚½’lژD‚ً—گ–\‚ةˆّ‚«‚؟‚¬‚ء‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤŒ‹”[‚àچد‚فپAژ®‚ج“ْژو‚è‚àŒˆ‚ـ‚ء‚½پB‚¢‚و‚¢‚وپA‚¨ڈj‚¢‚ةپu’…•¨پv‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚ؤ‚ ‚°‚و‚¤‚ئƒ^ƒ“ƒX‚ًٹJ‚¯‚ؤ‚ف‚é‚ئپA‚«‚ê‚¢‚ة•ï‚ٌ‚إ‚ ‚ء‚½•ï‚فژ†‚ھ”j‚ê‚ؤپAپu’lژDپv‚ھ‚؟‚¬‚ç‚ê‚ؤ–³‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپ@
پ@ƒ`ƒJ‚حپA‚ئ‚ؤ‚àژc”O‚ھ‚ء‚½‚ھپA’N‚ھ‚â‚ء‚½‚ج‚©”»‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إپAژd•û‚ب‚–ظ‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپ@‚¾‚ھƒ[ƒ“‚حپAƒ`ƒJ‚ة‰½‚©Œ¾‚¢‚½‚°‚ة‘ز‚؟چ\‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚ ‚éژپAƒ[ƒ“‚حƒ`ƒJ‚ة“–‚ؤ‚آ‚¯‚ھ‚ـ‚µ‚•¶‹ه‚ًŒ¾‚ء‚½پBپu“ٌٹK‚ھ‰JکR‚肵‚ؤپA‘پ‚‰ئ‚ًŒڑ‚ؤ’¼‚³‚ب‚¢‚ئ‚¢‚©‚ٌ‚ئ‚ةپA‚ ‚ٌ‚½‚ح‰½‚ٌ‚©پIژ©•ھ‚¾‚¯‰½–œ‰~‚à‚·‚éچ‚‚¢’…•¨‚ً”ƒ‚ء‚ؤ‚©‚çپcپBپvپ›
پ@ƒ`ƒJ‚حپAڈuٹش‚ةƒ[ƒ“‚جژd‹ئ‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ً’m‚ء‚½پBپu”k‚؟‚ل‚ٌپA‚ ‚ج’…•¨‚ح•qچ]‚؟‚ل‚ٌ‚ةŒ‹چ¥‚جڈj‚¢‚ة”ƒ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚ةپA’lژD‚؟‚¬‚ء‚½‚ج‚ح”k‚؟‚ل‚ٌ‚â‚ء‚½‚ئ‚إ‚·‚©پHپBپvپuپcپEپBپvپu‚¤‚؟‚ھ‰½‚إ‚ ‚ٌ‚ب”hژè‚ب’…•¨‚ً’…‚ç‚ê‚ـ‚·‚©پIپAژہچغ‚ح’lژD‚ج”¼ٹz‚إ”„‚ء‚ؤ‚¢‚½•¨‚إ‚·‚وپB‚¾‚¯‚اچ‚‰؟‚ب’lژD‚ج•t‚¢‚½•¨‚ًڈj‚¢‚ة‚ ‚°‚ê‚خپA’N‚¾‚ء‚ؤٹً‚µ‚©‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپcپBپv
پuپcپEپBپvپ@پu‚¢‚‚ç•n–R‚إ‹à‚ھ‚ب‚¢‚©‚ç‚ئ‚¢‚ء‚ؤپAˆہ‚¢‚à‚ج‚ًڈj‚¢‚ة‚ ‚°‚½‚çچ،ˆن‰ئ‚جگlٹش‚ھ’ل‚Œ©‚ç‚ê‚é‚ئ‚إ‚·‚وپB‚¹‚ء‚©‚—ا‚¢ڈj‚¢‚ً‚ ‚°‚ç‚ê‚é‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚ةپcپBپvپuپcپEپBپv
پ@ƒ[ƒ“‚حپAƒ`ƒJ‚ھŒ¾‚¢–َ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚ء‚½پBژ©•ھ‚ج‚â‚ء‚½‚±‚ئ‚ً”½ڈب‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@‚ـ‚½‚ ‚é“ْپAƒ[ƒ“‚ھƒٹƒ„ƒJپ[‚ًˆّ‚¢‚ؤژR‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚·‚é‚ئپAژR‚جک[‚ج•û‚إگط‚èڈo‚µ‚½‚خ‚©‚è‚جگ™‚ج–ط‚ًƒgƒ‰ƒbƒN‚ةگد‚ٌ‚إ‚¢‚é’j‚ھ‚¢‚½پBƒ[ƒ“‚حŒy‚ˆ¥ژA‚µ‚ؤچs‚«‰ك‚¬‚و‚¤‚ئ‚µ‚½پBپuچ،“ْ‚ح—ا‚¢“V‹C‚إ‚·‚بپ[پBپvپu‚ ‚ پA‚حپ[پBپv
پ@‚¾‚ھپAٹ¾‚ً—¬‚µ‚ب‚ھ‚çچق–ط‚ًگد‚ٌ‚إ‚¢‚é’j‚ھ‘ه•د‚»‚¤‚ةŒ©‚¦‚½‚ج‚إپA—§‚؟ژ~‚ـ‚ء‚ؤپAپu‚¨‚âگڈ•ھپA—§”h‚بگ™‚ج–ط‚إ‚·‚بپ[پBپv‚ئŒy‚‚ث‚¬‚ç‚ء‚½پBپ@‚·‚é‚ئ’j‚حپAپu‚ ‚ ‚ا‚¤‚àپA‚¨‰A‚³‚ٌ‚إپc‚¨گ¢کb‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚¨‘î‚ج‚¨‚©‚°‚إ‚ظ‚ٌ‚ئ‚ة—ا‚¢چق–ط‚ھژè‚ة“ü‚è‚ـ‚µ‚½‚خ‚¢پB—L“‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پBپv‚ئڈç’k”¼•ھ‚ة‰‘خ‚µ‚½پB
پ@‚¾‚ھپAƒ[ƒ“‚ح‚»‚جŒ¾—t‚ً•·‚‚ئپA‰½‚ًژv‚ء‚½‚ج‚©ٹçگF‚ھ‹}‚ة•د‚èپAƒLƒbپI‚ئ‚µ‚½•\ڈî‚إپA‹}‚¢‚إژR‚ة“o‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB’j‚حپAƒJƒbƒJ‚µ‚ؤ‹}‚¢‚إ‹ژ‚ء‚ؤ‚¢‚—lژq‚ًŒ©‚ؤپAپi‚ ‚çپAڈç’k‚ھ’ت‚¶‚ب‚©‚ء‚½‚بپHپEپBپj‚ئژv‚ء‚ؤ‚µ‚خ‚ç‚Œ©‘—‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‰½‚©‘ه•د‚بŒë‰ً‚ً‚µ‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚¢پAپu‚¨‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌپIچ،‚ج‚حڈç’k‚إ‚·‚وپ[پBپv‚ئ‘هگ؛‚إ‹©‚ٌ‚¾‚ھپA‚à‚¤‚ح‚é‚©‰“‚‚ةچs‚ء‚½ƒ[ƒ“‚جژp‚حڈ¬‚³‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚جگ؛‚حƒ[ƒ“‚جژ¨‚ة‚ح•·‚±‚¦‚ؤ‚ح‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@ƒ[ƒ“‚ح“o‚ء‚ؤ‚«‚ؤپA“c‚ٌ‚ع‚ةƒ`ƒJ‚جژp‚ًŒ©‚آ‚¯‚é‚ئپAگ¦‚¢Œ`‘ٹ‚إ‹كٹٌ‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‚¢‚«‚ب‚è“{–آ‚è‚آ‚¯‚½پBپuƒ`ƒJپI‰½‚©‚¨‘O‚حپAڈ³’m‚¹‚ٌ‚¼پIپBپvپu‚¦پcپEپHپBپvپu‚¨‚ê‚ة–ظ‚ء‚ؤڈںژè‚ب‚±‚ئ‚ً‚µ‚ؤ‚©‚ç‚ةپBپvپu‚ب‰½ژ–‚إ‚·‚©پHپBپvپu‰B‚³‚ٌ‚إ‚à‚و‚©پI’m‚ء‚ئ‚é‚ئ‚¼پA‚¨‘O‚ح‚¤‚؟‚جگ™‚ج–ط‚خڈںژè‚ةگl‚ة”„‚ء‚ؤ‚µ‚à‚¤‚½‚낤‚ھپIپBپvپu‚؟‚ه‚ء‚ئ‘ز‚ء‚ؤ‰؛‚³‚¢پB’N‚ھ‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئŒ¾‚ي‚µ‚ل‚ء‚½‚ئ‚إ‚·‚©پHپBپvپu‚³‚ء‚«چق–ط‚ًگد‚ٌ‚إ‚½‹g‘؛‚³‚ٌ‚ئ‚¢‚¤گl‚©‚çپA‚؟‚ل‚ٌ‚ئ•·‚¢‚ؤ—ˆ‚½‚ئ‚¼پBپvپu‚ٌپcپEپBپv
پ@ƒ`ƒJ‚حپA–َ‚à”»‚炸“{‚苶‚¤ƒ[ƒ“‚ج‘ش“x‚ة‹ء‚¢‚½‚ھپA—âگأ‚ةچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پBپi‰½‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚¾‚낤پcپBپj‚ئ“ھ‚ً‚©‚µ‚°‚ب‚ھ‚çپAژو‚è‚آ‚“‡‚à‚ب‚¢‚ظ‚اŒƒ“{‚µ‚ؤ‚¢‚éƒ[ƒ“‚ة‚حپA‚±‚êˆبڈم–َ‚ً•·‚¢‚ؤ‚à‘ت–ع‚¾‚ئ’ْ‚كپA’¼گع‹g‘؛‚³‚ٌ‚ج‰ئ‚ةژ–‚جگ^‘ٹ‚ً•·‚«‚ة‚¢‚ء‚½پB
پ@‚±‚ج‹g‘؛‚ئ‚¢‚¤’j‚ج‚¹‚¢‚إپAƒ`ƒJ‚ح‚ئ‚ٌ‚إ‚à‚ب‚¢–ع‚ةچ‡‚ء‚½‚ج‚¾‚ھپAˆê‰—âگأ‚ة‚ب‚ء‚ؤ’T‚è‚ً“ü‚ꂽپBپ@پu‚ ‚جپ[پAژہ‚ح‚¤‚؟‚ج‚¨”k‚؟‚ل‚ٌ‚©‚çپAژ„‚ح‚ذ‚ا‚“{‚ç‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ئ‚إ‚·‚ھپA‚³‚ء‚«‚¤‚؟‚ج”k‚؟‚ل‚ٌ‚ة‰½‚©Œ¾‚ي‚ء‚µ‚ل‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚إ‚·‚©پHپBپv
پ@’j‚حپAƒnƒb‚ئژv‚¢ڈo‚µ‚½‚و‚¤‚ةپAپu‚ ‚ پA‚ ‚ٌژپAŒy‚¢ڈç’k‚إ‰‘خ‚µ‚½‚ج‚ةپA‰½‚¾‚©’ت‚¶‚ب‚©‚ء‚½‚ف‚½‚¢‚إپA‚¨‘î‚ج‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌ‚ھƒJƒbƒJ‚µ‚ؤ“o‚ء‚ؤ‚ن‚©‚ꂽ‚©‚çپAژہ‚ًŒ¾‚¤‚ئگS”z‚µ‚ئ‚ء‚½‚ئ‚إ‚·‚وپBپv
پ@‚·‚ء‚©‚èپAژ–ڈî‚ً•·‚¢‚ؤپA”[“¾‚µ‚ؤ–ك‚ء‚ؤ—ˆ‚½ƒ`ƒJ‚حپA‚·‚®‚ةƒ[ƒ“‚ةکb‚³‚ب‚¢‚إپA‚ـ‚¸•v‚جگ³ٹى‚ةکb‚·‚±‚ئ‚ة‚µ‚½پBگ³ٹى‚ح—âگأ‚ةƒ`ƒJ‚جکb‚ً•·‚¢‚ؤ‚©‚çƒ[ƒ“‚ًŒؤ‚ٌ‚¾پB
پ@پu‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌپB‚ ‚ٌ‚½پA‰½‚إ•¨ژ–‚ً‚؟‚ل‚ٌ‚ئٹm”F‚¹‚ٌ‚ئ‚بپIپBپvپuپcپBپvپu‘¼گl‚جŒ¾—t‚ً‰L“غ‚ف‚ة‚ؤپAƒ`ƒJ‚ً“ھ‚²‚ب‚µ‚ة“{–آ‚ء‚ؤ‚©‚ç‚ةپcپB‚¤‚؟‚جژR‚ج–ط‚ھگط‚ç‚ê‚ئ‚é‚©‚ا‚¤‚©پA‚؟‚ل‚ٌ‚ئٹm”F‚·‚ê‚خ‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ة‚ب‚ç‚ٌ‚ئ‚â‚낤‚ھپIپBپvپuپcپBپvپuƒ`ƒJ‚ح‚à‚¤ڈ‚µ‚إ‘ه’p‚©‚‚ئ‚±‚낾‚ء‚½‚ئ‚خ‚¢پIپBپv
پ@‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©گ³ٹى‚حƒ`ƒJ‚جŒ¾‚¢•ھ‚ً—ا‚•·‚¢‚ؤپA—âگأ‚ة”»’f‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
ژn‚ك‚جچ ‚حپA‰إŒئ‚جŒ–‰ـ‚جژ‚ة‚حپA‚¢‚آ‚à•ê‚جƒ[ƒ“‚ً‚©‚خ‚¢پAپu‚¨‘O‚ھˆ«‚é‚©‚ئ‚â‚낤‚à‚ٌپIپBپv‚ئˆêٹ…‚µ‚ؤ“{‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپAƒ`ƒJ‚ح‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©پA•v‚جگ³ٹى‚جگS‚ًٹ®‘S‚ة’ح‚ٌ‚إ–،•û‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾پB
پ@پu‰½‚©پI‚¨‘O‚½‚؟‚حپA•v•w“ٌگl‚µ‚ؤ‘g‚ٌ‚إ”Nٹٌ‚ج‰´‚ًٹٌ‚ء‚ؤ‚½‚©‚ء‚ؤ‚¢‚¶‚ك‚ؤ‚©‚ç‚ةپcپBپvƒ[ƒ“‚حڈ‚µ—ـ‚®‚ف‚ب‚ھ‚ç‚àپA‰÷‚µ‚»‚¤‚ةژ©•ھ‚ج•”‰®‚ة“¦‚°‚é‚و‚¤‚ة–ك‚ء‚ؤچs‚ء‚½پB
پ@‚¹‚ء‚©‚؟‚إژv‚¢چ‚ف‚جŒƒ‚µ‚¢چQ‚ؤژز‚جƒ[ƒ“‚¾‚ء‚½‚ھپA‚±‚جژ–Œڈ‚ً‹«‚ةپAگ[‚”½ڈب‚µ‚½‚ج‚©پA“ھ‚²‚ب‚µ‚ةƒ`ƒJ‚ً“{‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‚ةپAˆêŒؤ‹z’u‚¢‚ؤچl‚¦‚邱‚ئ‚ًگSٹ|‚¯‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚©‚çپAƒ[ƒ“‚حپiژ©•ھ‚ج’¼ٹ´‚â‘M‚«‚ھپA‚¹‚ء‚©‚؟‚بٹشˆل‚¢‚ھ‚؟‚جژv‚¢چ‚ف‚ھ‘½‚پA–ہکf‚ً‚©‚¯‚½‚肵‚ؤپA“–‚ؤ‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢‚à‚ج‚¾پcپBپj‚ئژ©گM‚ً‚ب‚‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤ––‚ءژq‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤپAŒئ‚جژَ‚¯‚½—ىٹ´‚ئ‰إ‚جژü“‚بچô—ھ‚ئ‚ھŒƒ‚µ‚‚ش‚آ‚©‚èچ‡‚¤‘خ—§‚ج“ْ‚ھ‹ك‚أ‚±‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گrژµ‚جŒ¶‘zپB
پ@ˆê•ûپA”ژ‘½‚ة‚¢‚éگrژµ‚حپAگجژَ‚¯‚½Œ[ژ¦‚ًژv‚¢ڈo‚µ‚ؤپA‚ـ‚¾Œ©‚تƒ`ƒJ‚جژq‹ں‚ةٹَ–]‚ً‘ُ‚µ‚ؤگ¶‚«‚ؤ‚¢‚½پBپiگ_—lپAƒ`ƒJ‚جژq‹ں‚ج’†‚إپAˆê‘جپA’N‚ھژ„‚ج•ّ‚¢‚½“ن‚ً‰ً‚‚ج‚إ‚·‚©پHپA‹³‚¦‚ؤ‰؛‚³‚¢پcپBپj‚»‚جژپAˆأˆإ‚ج’†‚جگ؛‚ھ•·‚±‚¦‚ؤ—ˆ‚½پB
پ@پiگl‚ئگ_پiگrژµ‚وپA‚»‚ج–¼‘O‚ً’m‚肽‚¢‚©پHپB‚»‚جژq‚حپAگl‚ئگ_‚جŒ¾—t‚ھˆê‚آ‚ة‚ب‚ء‚½–¼‘O‚ًژ‚ء‚ؤŒ»‚ي‚ê‚é‚إ‚ ‚낤پcپBپj‚جŒ¾—tپHپcپBپjگrژµ‚ح‚»‚جˆس–،‚ھ”»‚ç‚ب‚©‚ء‚½پBپiگl‚ئگ_‚جŒ¾—t‚جژڑ‚ًژ‚آƒ`ƒJ‚جژq‹ں‚ھ“ن‚ً‰ً‚‚©پcپcپBپj
پ@گrژµ‚حپA–²‚ج‚و‚¤‚بŒ[ژ¦‚ًژَ‚¯پA‚»‚ج“ن‚ھ‰ً‚¯‚¸‚ةپAˆأˆإ‚ج’†‚إٹَ–]‚جŒُ‚ً‘ز‚؟‚ي‚ر‚é‚و‚¤‚ةگ¶‚«‚ؤ‚¢‚½پBپ@‚»‚ê‚©‚ç‰i‚¢چخŒژ‚ھ—¬‚ꂽپB
پ@‚ ‚é“ْپAƒ`ƒJ‚ھ‚ـ‚¾—c‚¢گMژq‚ًکA‚ê‚ؤژہ‰ئ‚ة‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB
پ@پu•ƒ‚³‚ٌپA‚½‚¾‚¢‚ـپ[پBپvپu‚¨‚¨پAƒ`ƒJ‚©پBپvگrژµ‚ح‹v‚µ‚ش‚è‚ة‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚½–؛‚جƒ`ƒJ‚جگ؛‚ً•·‚¢‚ؤٹى‚ٌ‚إŒ}‚¦‚½پBپu‚ظ‚çپAگMژqپIپA‚¨‘c•ƒ‚³‚ٌ‚¾‚وپBپvپu‚¨‚¨پAگMژq‚ئŒ¾‚¤‚ج‚©پcپBپc‚ پBپv
پ@گrژµ‚حژv‚ي‚¸پAگجژَ‚¯‚½Œ[ژ¦‚جŒ¾—t‚ً•Kژ€‚ةژv‚¢ڈo‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپi‚¨‚¨پIپA‚»‚¤‚¾پBگl‚ئŒ¾‚ھˆê‚آ‚ة‚ب‚ء‚½ژڑ‚حپAگM‚ئ‚¢‚¤ژڑ‚¾پcپBپ@‚à‚µ‚©‚µ‚½‚çپcپAژ©•ھ‚ج“ن‚ً‚±‚جژq‚ھ‰ً‚¢‚ؤ‚‚ê‚é‚ج‚¾‚낤‚©پcپBپjپ@‹}‚ةگrژµ‚ج–ع‚ةŒُ‚ھچ·‚µ‚ؤ—ˆ‚½‚و‚¤‚ب‹C‚ھ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚¤ژv‚¤‚ئ–î‚àڈ‚‚à‚½‚ـ‚炸پA‚ـ‚¾ڈ¬‚³‚بگMژq‚ة‚·‚ھ‚è‚آ‚«‚½‚‚ب‚ء‚½پBپuگMژqپIپA‚¨‚¢‚إگMژqپIپvژè‚إ‚ـ‚³‚®‚é‚و‚¤‚ة‘{‚µ“–‚ؤ‚é‚ئپAگMژq‚جڈ¬‚³‚بگg‘ج‚ً’T‚è“–‚ؤ‚½پB
پ@گrژµ‚حپAگMژq‚ً•ّ‚±‚¤‚ئپAگMژq‚جژè‚ً’ح‚ٌ‚إˆّ‚«ٹٌ‚¹‚و‚¤‚ئ‚µ‚½پB‚¾‚ھگMژq‚حپA“ث‘R‹‚¢—ح‚إکr‚ًˆّ‚ء’£‚ç‚ꂽ‚ج‚إپA‹ء‚¢‚ؤ”½ژث“I‚ة“¦‚°‚و‚¤‚ئ‚µ‚½پBپ@پu‚¢‚âپIپBپvپu‚ظ‚çگMژqپA‚±‚ء‚؟‚ة‚¨‚¢‚إپBپvپu‚¢‚âپ[پIپBپvگrژµ‚حپA‚»‚ê‚إ‚àŒ™‚ھ‚éگMژq‚جژè‚ً—£‚³‚ب‚©‚ء‚½پB‚»‚جڈuٹشپAگMژq‚جژw‚ھ’E‰P‚µ‚ؤٹO‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پBپu‚يپ[‚ٌپA’ةپ[‚¢پA’ة‚¢‚و‚¤پIپBپvپ@گMژq‚حپAŒƒ‚µ‚‹ƒ‚«ڈo‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ھˆê“x‚ ‚ء‚ؤ‚©‚çپA‚»‚جŒمپAƒ`ƒJ‚ھگMژq‚ًکA‚ê‚ؤ—ˆ‚ؤ‚àپAگrژµ‚حگMژq‚جژè‚ًˆ¬‚낤‚ئ‚·‚é‚ھپAŒƒ‚µ‚’ïچR‚µ‚ؤ“¦‚°‚و‚¤‚ئ‚·‚é‚ئپA’ح‚ٌ‚¾ژè‚ً‚·‚®—£‚·‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پBپ@گrژµ‚حپA‰½“x‚©گMژq‚ً•ّ‚±‚¤‚ئ‚µ‚½‚ھپAژں‘و‚ةŒ™‚ھ‚éگMژq‚ة–³—‚ةگG‚ê‚邱‚ئ‚ً‚ ‚«‚ç‚ك‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپAˆظڈي‚ةچ‚‚ش‚ء‚ؤ‚¢‚½•ƒ‚جژp‚ً•sژv‹c‚بژv‚¢‚إŒ©‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ط‚ج‘ˆ‚¢پB
پ@‚ ‚éژپAƒ`ƒJ‚ھژR‚ةچs‚‚ئپAژR‚ج–ط‚ھگط‚ç‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚»‚ج–ط‚حپA‰ئ‚ً—§‚ؤ’¼‚·ژ‚جچق–ط‚ة‚µ‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤپAƒ`ƒJ‚ھ‘هژ–‚ةژ}•¥‚¢‚ً‚µ‚ؤژè‚ھ‚¯‚ؤ‚¢‚½پuw‚ج–طپv‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@پi’N‚ھ‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚µ‚½‚ج‚¾‚낤پcپBپj‚ئپAƒ`ƒJ‚حپA”ئگl‚ً’T‚µ‚ة—ׂجژR‚ج•û‚ً•à‚¢‚½پBپ@‚·‚é‚ئپA—ׂج‚¨‚₶‚ھ“d‹C‹ک‚إژ}•¥‚¢‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ج‚·‚®–T‚إŒ©ٹo‚¦‚ ‚é–ط‚ھ“|‚³‚ê‚ؤ“]‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پu‚¨‚¶‚³‚ٌپI‚±‚ج–ط‚ح‚ ‚»‚±‚ة‚ ‚ء‚½–ط‚¶‚ل‚ب‚©‚إ‚·‚©پHپBپvپu‚ ‚ پA‚»‚ج–ط‚ح‰ئ‚جچق–ط‚ةژg‚¤‚ج‚ةپA‚؟‚ه‚¤‚ا‚¢‚¢‘ه‚«‚³‚ة‚ب‚ء‚½‚©‚çپAگط‚ء‚½‚ئپBپvپ@•ê‚حپAپuƒJƒbپ[پIپv‚ئ‚ب‚ء‚ؤپA—ׂج‚¨‚₶‚ةگH‚ء‚ؤٹ|‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@پu‚»‚±‚جژR‚حپA‚¤‚؟‚ھ–ط‚ج”¤‚إ‚·‚¯‚ا‚ثپBپvپu‚»‚ٌ‚ب”nژ‚بپA‚¤‚؟‚ھ‹àڈo‚µ‚ؤ”ƒ‚¤‚½–ط‚إ‚·‚خ‚¢پcپcپBپvپ@ƒ`ƒJ‚حپA‰½‚ھ‰½‚¾‚©”»‚ç‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ—âگأ‚ة‚ب‚ء‚ؤ’²‚ׂؤ‚ف‚½پB
پ@‚·‚é‚ئپAنn‚جٹى•½‚ھپA‚»‚جژR‚àٹـ‚ك‚ؤپAٹm‚©‚ةƒ[ƒ“‚ج‹`ŒZ‚©‚甃‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚ةٹض‚ي‚炸پAژc”O‚ب‚ھ‚ç‚»‚جپu‚ذ‚ج‚«‚ج–طپv‚جگ¶‚¦‚½“y’n‚¾‚¯‚ھپA“o‹L‚à‚ê‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ”»‚ء‚½پBپ@‚»‚ج“o‹L‚à‚ê‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ً—ا‚¢‚±‚ئ‚ةپAژ‚؟ژه‚جژً—گ‚ج‘§ژq‚ھپA‚»‚جژR‚ج–ط‚ًڈںژè‚ةگl‚ة”„‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾پB
پ@•sژv‹c‚ب‚±‚ئ‚ةپAƒ[ƒ“‚âٹى•½‚½‚؟‚ھ”ƒ‚ء‚½ژR‚âŒأ‚¢‰ئ‚حپA‚±‚ئ‚²‚ئ‚“ٌ‘م–ع‚ة‘ه‚«‚ب–â‘è‚ً‚à‚½‚ç‚·‚ج‚¾‚ء‚½پBپuŒـ”N‚µ‚©ژ‚½‚ب‚¢پBپv‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ”ƒ‚ء‚½Œأ‚¢‰ئ‚حپA‚à‚¤ƒKƒ^‚ھ—ˆ‚ؤپA‰JکR‚è‚ح‚·‚邵پA‘ن•—‚جژ‚ب‚ا‚حپuƒ~ƒVپAƒ~ƒVƒbپIپv‚ئ‰¹‚ھ‚µ‚ؤ—h‚ê‚éڈَ‘ش‚¾‚ء‚½پB
پ@ƒ[ƒ“‚حچ،‚ة‚à•ِ‚ê‚»‚¤‚ب•s‹C–،‚ب‰¹‚ً•·‚‚ئپAپu‘پ‚و‚¤‰ئ‚ً—§‚ؤ’¼‚³‚ب‚¢‚ئپA•|‚‚ؤ‚ئ‚ؤ‚àڈZ‚ك‚½‚à‚ٌ‚¶‚ل‚ب‚¢‚خ‚¢پIپBپv‚ئŒ¾‚¤‚ج‚¾‚ء‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپA‚¢‚و‚¢‚و‰ئ‚ًŒڑ‚ؤ‚éژ‚ھ‹ك‚أ‚¢‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚إپA‘هچH‚³‚ٌ‚ة—ˆ‚ؤ–ل‚ء‚ؤŒ©‚ؤ‚à‚ç‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚½پBپu‘هچH‚³‚ٌپA‚±‚±‚ج–ط‚ح‰ئ‚جŒڑ’z‚ج’Œ‚ةژg‚¦‚ـ‚·‚©پHپBپvپu‚ ‚ پA‚±‚è‚ل‚ پ[—§”h‚ب–ط‚إ‚·‚½‚¢پB‰؛‚ج•û‚ج‘¾‚¢•”•ھ‚ح’Œ‚ة‚·‚é‚ج‚ح‚à‚ء‚½‚¢‚ب‚©پA”–‚‚»‚¢‚إژ؛“à‚ج•ا”آ‚ة‚µ‚½‚ç—ا‚©‰ئ‚ھڈo—ˆ‚ـ‚·‚خ‚¢پBڈم‚ج•û‚ج•”•ھ‚ح’Œ‚ئ‚µ‚ؤڈ\•ھ‚ةژg‚¦‚ـ‚·پBپv
پ@‚»‚جŒ¾—t‚ً•·‚¢‚½“ْ‚©‚çپAƒ`ƒJ‚حپA‰ئ‚ھڈo—ˆ‚é‚»‚جژ‚ً–²Œ©‚ؤپA‚»‚ج–ط‚ً–ˆ“ْ’ڑ”J‚ةژ}•¥‚¢‚ً‚µ‚ؤ‘هگط‚ةژè“ü‚ê‚ً‚µ‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚¾‚ء‚½پB‚»‚ê‚ب‚ج‚ةپAنn‚جٹى•½‚ج•sژèچغ‚ة‚و‚éپAپu“o‹L‚à‚êپv‚ةپA‚آ‚¯چ‚ـ‚êپA—•sگs‚ة‚à‰،‚©‚ç’D‚ي‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ج‚¾پBپ@ƒ`ƒJ‚ھ‚ا‚ٌ‚ب‚ة‰÷‚µ‚¢ژv‚¢‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚àپAپuڈ‘—ق‚ج“o‹LکR‚êپv‚إ‚حپA‚±‚؟‚ç‚ج•s’چˆس‚إ‚ ‚èپA‰½‚ئ‚àژd•û‚ھ–³‚¢‚ئژ•ٹڑ‚ف‚µ‚ؤ’ْ‚ك‚邵‚©–³‚©‚ء‚½پB
پ@Œ_–ٌ‚جژ‚ةپA‚«‚؟‚ٌ‚ئŒ©—ژ‚ئ‚³‚ب‚¢‚إٹm”F‚µ‚ؤ‚¢‚ê‚خپA–{—ˆ‚¤‚؟‚ج“y’n‚ة‚ب‚ء‚½”¤‚إ‚ ‚ء‚½‚ج‚ةپAنn‚àŒئ‚àچ،ˆن‰ئ‚جگlٹش‚حپA‚¨گlچD‚µ‚ج‚ئ‚±‚ë‚ھ‚ ‚èپA‰½ڈˆ‚©‚ج‚ٌ‚ر‚肵‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚©پA‘هگط‚بڈٹ‚ً‚¢‚¢‰ءŒ¸‚ة‚µ‚ؤ‚â‚è‰ك‚²‚·‚ئ‚±‚ë‚ھ—L‚ء‚½پB
پ@‚»‚ج‚½‚ك‚ةپA‘هگط‚بچàژY‚ً‚ف‚·‚ف‚·پAگl‚©‚ç’D‚ي‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚é‚ج‚¾‚ء‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚حپAپiچ،ŒمپA‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ھ“ٌ“x‚ئ‚ب‚¢‚و‚¤‚ةپAژ©•ھ‚ھ‚µ‚ء‚©‚肵‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پcپBپj‚ئ‚¢‚¤‹Cژ‚؟‚ً‹‚‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@‚¤‚؟‚ج“y’n‚ة‚ب‚ء‚½”¤‚ج‚±‚جژR‚ًپA‘¼گl‚ة’@‚«”„‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½ژ‚؟ژه‚ج‹Pژہ‚ئ‚¢‚¤‘§ژq‚ة‘خ‚µ‚ؤپAƒ`ƒJ‚حپA“à‚ة”é‚ك‚½Œƒ‚µ‚¢“{‚è‚ئ“¬‘ˆ‚ج‰ٹ‚ًگأ‚©‚ة”R‚₵‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@‚»‚جŒم‚àپAچ،ˆن‰ئ‚ج•½کa‚ئچK‚¹‚ً‚±‚ئ‚²‚ئ‚’D‚¢پA”j‰َ‚µ‚ؤ‚¢‚±‚¤‚ئ‚µ‚ؤŒ»‚ي‚ê‚ؤ—ˆ‚邱‚جژً—گ‚جپi‹Pژہپj‚ئ‚¢‚¤’j‚ًپAƒ`ƒJ‚حچ،ˆن‰ئ‚ً‹‡’n‚ةٹׂê‚و‚¤‚ئژژ—û‚ًژdٹ|‚¯‚éپuچإڈ‰‚ج“Gپv‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ً’¼ٹ´‚µپA• ‚ً‚‚‚èپAگSچ\‚¦‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘وˆê‚ج“GپAŒد’jپB
پ@‚ ‚é“ْپA‚»‚جژً—گ‚ج‹Pژہ‚ھچ،ˆن‰ئ‚ة–K‚ث‚ؤ—ˆ‚½پBپu—آڈe‚ج–ئ‹–‚جچXگV‚جˆ×‚ةپA‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚à‚¨‹à‚ھ‚¢‚邯‚ٌپA‚·‚®•ش‚·‚©‚ç‚؟‚ه‚ء‚ئ‘ف‚µ‚ؤ‚‚êپBپv‚ئŒ¾‚ء‚ؤپAƒ[ƒ“‚ة‚¨‹à‚ًژط‚è‚ة—ˆ‚½پBپ@ƒ[ƒ“‚حپA‰™‚©‚ç—ٹ‚ـ‚ê‚é‚ئپuŒ™پv‚ئ‚àŒ¾‚¦‚ب‚¢‚إپA‚ـ‚ئ‚ـ‚ء‚½‘ه‹à‚ً‘ف‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پBپ@‚¨‹à‚ًژط‚è‚ؤ‹A‚éژپAپu‚¨‚س‚‚ë‚ة‚حگâ‘خ‚ة–ظ‚ء‚ئ‚«‚ب‚¢‚وپIپBپv‚ئ‹؛‚·‚و‚¤‚ة”O‚ً‰ں‚µ‚ؤ‹A‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB‚ئ‚±‚ë‚ھ‚»‚ج’j‚حپA–ٌ‘©‚µ‚½‚ج‚ة‚¢‚آ‚ـ‚إ‚½‚ء‚ؤ‚àپAƒ[ƒ“‚ةژط‚肽‹à‚ً•ش‚»‚¤‚ئ‚à‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپAژR‚جژ–‚إ• ‚ً—§‚ؤ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA‚»‚جڈم‚ة‹à‚ً•ش‚³‚ب‚¢کb‚ًƒ[ƒ“‚©‚ç•·‚¢‚½ژپAپuƒJپ[ƒbپIپv‚ئ“ھ‚ةŒŒ‚ھڈم‚ء‚½پBپu”k‚؟‚ل‚ٌپAژ„‚ھ‘م‚ي‚è‚ةچs‚ء‚ؤپA’¼گع•ش‚µ‚ؤ–ل‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚ه‚¤‚©پHپBپvپu‚¢‚âپ[پA‚à‚¤—ا‚©—ا‚©پB‚µ‚و‚ٌ‚ب‚©پBپv‚ئƒ[ƒ“‚ح‚ ‚«‚ç‚ك‚½‚و‚¤‚ةŒ¾‚ء‚½پB
پ@‚¾‚ھپAƒ`ƒJ‚ح‚à‚¤ٹù‚ةگS‚ةŒˆ‚ك‚ؤ‚¢‚½پB‚µ‚خ‚ç‚‚µ‚ؤƒ`ƒJ‚حپA‚»‚ج‰ئ‚ة–K‚ث‚ؤچs‚ء‚½پBپ@‚»‚جژپA‹Pژہ‚ح‹ڈ‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA‚»‚ج•êگe‚جƒJƒc‚ھ‹ڈ‚½پBژd•û‚ب‚پAپu‚¨‘î‚ج‘§ژq‚³‚ٌ‚ھپA‚·‚®•ش‚·‚©‚ç‚ئŒ¾‚ء‚ؤپA‚¤‚؟‚ج”k‚؟‚ل‚ٌ‚©‚炨‹à‚ًژط‚肽‚ـ‚ـپA‚¢‚آ‚ـ‚إŒo‚ء‚ؤ‚à•ش‚µ‚ؤ‚‚ê‚ب‚¢‚»‚¤‚إ‚·‚ھپcپBپvپ@ƒ`ƒJ‚حژً—گ‚ج’j‚ج•êگeپiƒJƒcپj‚ةڈع‚µ‚ژ–ڈî‚ًکb‚µ‚½پB
پ@پu‚ ‚çپ[پA‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚½‚ئ‚خ‚¢‚بپ[پA‚·‚ٌ‚ـ‚¹‚ٌپB‚ ‚ٌ“z‚ح‚ظ‚ٌ‚ب‚²‚ئ‚à‚¤پA‚ë‚‚إ‚à‚ب‚¢“z‚¶‚ل‚¯‚ٌپ[پcپvپ@•êگe‚حپA‘§ژq‚ھژط‹à‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚ح‰½‚à’m‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚ھپAپuƒ[ƒ“‚ةچد‚ـ‚ٌ‚â‚ء‚½‚ئپA—ا‚ژس‚ء‚ؤ‚¨‚¢‚ؤ‰؛‚³‚¢پBپv‚ئŒ¾‚¢‚ب‚ھ‚çپA‚¨‹à‚ًژ‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤپAƒ`ƒJ‚ة“n‚µ‚ؤ•ش‚µ‚½پB•êگe‚ح‘§ژq‚ج‘م‚ي‚è‚ةژ©•ھ‚إ—§‚ؤ‘ض‚¦‚ؤ‚‚ꂽ‚ج‚¾‚ء‚½پB
پ@‚»‚ê‚©‚çپA‰½“ْ‚©‚µ‚ؤپA‚»‚جژً—گ‚ج’j‚ھژً‚جڈL‚¢‚ًƒvƒ“ƒvƒ“‚³‚¹‚ب‚ھ‚çپA‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚½پBƒ`ƒJ‚ًŒ©‚é‚ئ‚ـ‚‚µ—§‚ؤ‚½پBپu‚¨پ[پI‹M—l‚ٌپA‚و‚‚àƒoƒ‰‚µ‚ؤ‚‚ꂽ‚بپ[پIپAگe‚ة‚حگâ‘خ‚ة–ظ‚ء‚ئ‚‚و‚¤‚ةŒ¾‚¤‚ئ‚ء‚½‚낤‚ھپB–ٌ‘©”j‚ء‚½‚©‚ç‘S•”ƒoƒŒ‚ؤ‚µ‚à‚¤‚½‚â‚ب‚¢‚©پIپBپv
پ@ڈںژè‚ب‚±‚ئ‚خ‚©‚茾‚¤‹Pژہ‚ةپAƒ`ƒJ‚حŒ¾‚¢•ش‚µ‚½پBپu‰½Œ¾‚¢‚و‚é‚ئ‚إ‚·‚©پA–ٌ‘©‚ً”j‚ء‚½‚ج‚ح‚ا‚ء‚؟‚إ‚·‚©پHپBپvپu‹M—lپI‰إŒن‚ج‚‚¹‚µ‚ؤپAگ¶ˆس‹C‚ب‚±‚ئ‚ً‚·‚ٌ‚بپIپBپvپu‚·‚®•ش‚·‚©‚ç‚ئŒ¾‚¤‚±‚ئ‚إ”k‚؟‚ل‚ٌ‚ح‘ف‚µ‚ؤ‚ ‚°‚½‚ئ‚ةپA‚ ‚ٌ‚½‚ھ‚؟‚لپ[‚ٌ‚ئ•ش‚³‚ٌ‚©‚ç‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپIپBپvپu‚¤‚邳‚¢پIپA‚à‚¤پA‚©‚©‚ ‚ئ‚¨‘O•û‚ئ‚حپAگeگت•t‚«چ‡‚¢‚ح‚³‚¹‚ٌ‚©‚ç‚بپI‚و‚¤ٹo‚¦‚ئ‚¯پIپBپvپ@‚³‚ٌ‚´‚ٌŒ¾‚¢‚½‚¢•ْ‘è‚ًŒ¾‚ء‚ؤ‹A‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹¶گl‚ج‘خڈˆپB
پ@‚»‚ê‚©‚ç–”‚µ‚خ‚ç‚Œo‚ء‚ؤپA‹Pژہ‚ھگŒ‚ء‚د‚ç‚ء‚½گ¨‚¢‚إپAژً‚ج“ُ‚¢‚ً‚ص‚ٌ‚ص‚ٌ‚³‚¹‚ب‚ھ‚猻‚ي‚ꂽپBپu‚â‚¢پI‹M—lپ\‚ٌپIپA‚س‚´‚¯‚ٌ‚بپ[پIپA‚±‚ج–ىکYپ\پIپBپvƒtƒ‰ƒtƒ‰‚µ‚ب‚ھ‚ç‚à‰s‚¢–ع‚إŒ؛ٹض‚ةŒ»‚ي‚ꂽپB
پ@‘نڈٹ‚ة‹ڈ‚½ƒ[ƒ“‚حپA‚»‚ج“{چ†‚ھ•·‚±‚¦‚é‚ئپA”½ژث“I‚ة‘نڈٹ‚ة‚ ‚é•ï’ڑ‚ًڈW‚ك‚é‚ئŒث’I‚جˆّ‚«ڈo‚µ‚ج‰œگ[‚‚ة‰B‚µ‚½پBپ@‹Pژہ‚ج–ع‚حپAٹù‚ةچہ‚ء‚½–ع‚ة‚ب‚è—گ«‚ًژ¸‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚±‚ج“ْ‚ح“ْ—j‚إپA•ƒ‚ج—Fگl‚جڈ¼‰؛‚ج‚¨‚¶‚³‚ٌ‚ھˆحŒé‚ًچ·‚µ‚ة—ˆ‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‹Pژہ‚ح‚¨‹q‚ھ—ˆ‚ؤ‚¢‚و‚¤‚ئچ\‚ي‚¸پA‚₽‚ç‚ئ‘هگ؛‚إ“{–آ‚ء‚ؤˆحŒé‚ج‘ن‚ًڈR‚è”ٍ‚خ‚µ–\‚ê‰ô‚ء‚½پB‚¨‚¶‚³‚ٌ‚حپA“ث‘RŒ»‚ي‚ê‚ؤ“{–آ‚èژU‚ç‚·–\“k‚ة•ً‚ê‚ؤپAپu‰½‚إ‚·‚©پ[‚ ‚ٌ‚½‚حپIپBپv‚ئ‹Pژہ‚ة’چˆس‚µ‚½پB
پ@پu‰½‚©پI‚¨‘O‚حپ[پA’N‚âپ[پIٹضŒW‚ب‚¢‚‚¹‚ة–ظ‚ء‚ئ‚êپIپBپv‹Pژہ‚حپA‹t‚ةˆِ‰ڈ‚ً•t‚¯ˆذˆ³‚µ‚ؤ‚¨‚¶‚³‚ٌ‚ً‹؛‚µ‚½پBپ@ƒ[ƒ“‚حپA–َ‚à”»‚炸’‡چظ‚ة—§‚ئ‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚‚ꂽ‚¨‚¶‚³‚ٌ‚ًگS”z‚µ‚ؤپAپu‚ ‚ٌ‚½‚حپA‚¤‚؟‚جگg“à‚ج‘ˆ‚¢‚ةٹض‚ي‚ç‚ٌ‚إپA‚à‚¤‘پ‚‹A‚ء‚½‚ظ‚¤‚ھ‚و‚©پIپB‘پ‚و‚¤‹A‚ٌ‚بپ[‚¢پBپv‚»‚¤Œ¾‚ي‚ê‚é‚ئ‚¨‚¶‚³‚ٌ‚àگ¬‚·‚·‚ׂھ–³‚پAژd•û‚ب‚گS”z‚»‚¤‚بٹç‚ً‚µ‚ب‚ھ‚ç‹A‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@‹Pژہ‚حپAژ×–‚ژز‚ھ‹ڈ‚ب‚‚ب‚ء‚½‚ج‚ًٹm”F‚·‚é‚ئپAپu‚±‚çپI‹M—l‚ٌپcپBپv‚ئچX‚ةپA‘هگ؛‚ًڈo‚µ‚ؤ–\‚ꑱ‚¯‚½پBپ@‚ئ‚¤‚ئ‚¤پA‚½‚ـ‚è‚©‚ث‚½ƒ[ƒ“‚ھ“{–آ‚ء‚½پBپu‹PژہپIپA‚¨‘O‚ف‚½‚¢‚ب“z‚حپA‚à‚¤‰ئ‚ة‚ح—ˆ‚ٌ‚إ‚ٌ—ا‚©پIپA‚à‚¤‚ئ‚ء‚ئ‚ئ‹A‚êپIپBپvپu‰½‚ًپA‚±‚ج”k‚ پIپBپv‹Pژہ‚ح“{‚苶‚ء‚½‚و‚¤‚ةپAƒ[ƒ“‚ً’ا‚¢‚©‚¯‚½پB
پ@“¦‚°‰ٌ‚éƒ[ƒ“‚ًٹl•¨‚ًڈP‚¤ڈb‚ج‚و‚¤‚ة‘f‘پ‚•ك‚ـ‚¦‚é‚ئپAڈô‚جڈم‚ةپuƒhƒXƒ“پIپv‚ئ“|‚µپAƒ[ƒ“‚جگg‘ج‚ً‘«‚إ‹‚‚ح‚³‚فچ‚ٌ‚إ‰ں‚³‚¦‚آ‚¯‚½پBپu‹PژہپI‰½‚·‚é‚ئ‚©پA‚â‚ك‚ٌ‚©پIپBپvƒ[ƒ“‚ح•Kژ€‚إ“¦‚°‚و‚¤‚ئ’ïچR‚µ‚½‚ھ–³‘ت‚إ‚ ‚ء‚½پB‚ـ‚·‚ـ‚·‹‚‰ں‚³‚¦•t‚¯پA‚¢‚آ‚ـ‚إ‚à•ْ‚³‚ب‚©‚ء‚½پBپ@‚آ‚¢‚ةƒ[ƒ“‚حپA‚ ‚«‚ç‚ك‚½‚ج‚©‰ں‚³‚¦‚آ‚¯‚ç‚ꂽ‚ـ‚ـپA’ïچR‚ً‚â‚ك‚ؤگأ‚©‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@‚¢‚‚çگŒ‚ء‚د‚ç‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚àپA‚±‚ج’j‚حژ©•ھ‚جڈf•ê‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚ ‚ـ‚è‚ة–³—ç‚بچs“®‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚¶‚¢‚ء‚ئ‹Pژہ‚جچs“®‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚½‚ھپAٹù‚ة“{‚è‚ھ’¸“_‚ة’B‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپi–l‚ج‚¨”k‚؟‚ل‚ٌ‚ة‰½‚ً‚·‚éپIپBڈf•ƒ‚¾‚낤‚ھ‰½‚¾‚낤‚ھ‹–‚³‚ٌ‚¼پIپcپEپBپjپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚جگS‚ةپA‹Pژہ‚ة‘خ‚·‚錃‚µ‚¢ژEˆس‚ھ‚و‚¬‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚»‚جژپAƒ`ƒJ‚جگ؛‚ھ‚µ‚½پBپu‚à‚¤‚¢‚¢‰ءŒ¸‚ة‚â‚ك‚ب‚ء‚¹پIپA”Nٹٌ‚è‚ة‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚µ‚½‚çپAچœ‚ھگـ‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚¶‚ل‚ب‚¢‚إ‚·‚©پIپvپ@ƒ`ƒJ‚ح‘ه‚«‚بگ؛‚إ“{‚ء‚ؤŒ¾‚ء‚½پB‚»‚ê‚إ‚àˆêŒü‚ة•ْ‚»‚¤‚ئ‚µ‚ب‚¢‚ج‚إپAƒ`ƒJ‚à‚آ‚¢‚ة“ھ‚ة—ˆ‚½پB
پ@پu‚ ‚ٌ‚½‚حپA‚à‚¤‚¤‚؟‚ئ‚حگeگت•tچ‡‚¢‚ح‚³‚¹‚ٌ‚ئŒ¾‚ء‚ئ‚炵‚½‚ئˆل‚¤‚ٌ‚إ‚·‚©پIپB‚»‚ê‚إ‚àپB‚±‚؟‚ç‚حگe‘°‚¾‚ئژv‚ء‚ؤچ،‚ـ‚إ‘ه–ع‚ةŒ©‚ؤ‚ ‚°‚½‚ج‚ةپA‚»‚ء‚؟‚ھ‚»‚ٌ‚ب–³—ç‚ب‚±‚ئ‚ً•½‹C‚إ‚·‚é‹C‚ب‚çپA‚±‚؟‚ç‚àچl‚¦‚ً•د‚¦‚ـ‚·‚وپIپBٹoŒه‚µ‚ب‚ء‚¹پBپvپ@‚»‚¤Œ¾‚¤‚ئƒ`ƒJ‚حپAژَکbٹي‚ًژو‚èپA110”ش‚ً‰ô‚µ‚ؤŒxژ@‚ة“dکb‚ً‚©‚¯‚½پBپu‚à‚µ‚à‚µپAŒxژ@‚إ‚·‚©پA‚·‚®—ˆ‚ؤ‰؛‚³‚¢پcپBپv
پ@“dکb‚ًگط‚é‚ئپAپu‹Pژہ‚³‚ٌپAچ،پAŒxژ@Œؤ‚ٌ‚¾‚¯‚ٌ‚ثپA•ك‚ـ‚肽‚‚ب‚©‚ء‚½‚çپAچ،‚ج‚¤‚؟‚ة‘پ‚¤‹A‚è‚ب‚ء‚¹پBچإŒم‚جŒxچگ‚إ‚·‚وپB‚à‚¤‚·‚®Œxژ@‚ھ‚‚邯‚ٌپAکAچs‚³‚ê‚ؤŒY–±ڈٹ‚إ‚à‚ب‚ٌ‚إ‚àپA‚µ‚خ‚ç‚“ü‚ء‚ؤ“ھ—â‚₵‚½‚ç‚و‚©‚½‚¢پIپBپv‚ئ“f‚«ژج‚ؤ‚é‚و‚¤‚ة‹؛‚©‚µ‚½پB
پ@‚µ‚خ‚ç‚‚·‚é‚ئپA‹Pژہ‚ح‹}‚ة—ح‚ھ‹¯‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚¢پA•|‚‚ب‚ء‚½‚ج‚©پA‚â‚ء‚ئژè‚ً—£‚µ‚ؤƒ[ƒ“‚ًٹJ•ْ‚µ‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚ح‚·‚®‚ةƒ[ƒ“‚ً‹N‚±‚µ‚ؤپAپu‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌپA‘پ‚و‚¤“ٌٹK‚ة“¦‚°‚ب‚ء‚¹پBپv‚ئƒ[ƒ“‚ً‹Pژہ‚©‚牓‚´‚¯‚½پBپ@‹Pژہ‚حپAژ©•ھ‚جپA“x‚ً‰ك‚¬‚½چsˆ×‚ً’p‚¶‚½‚ج‚©پA‹C‚ـ‚¸‚»‚¤‚ةƒ`ƒJ‚ج•û‚ًŒ©‚½پBپ@‹Pژہ‚ح‚·‚®‚ة‹A‚낤‚ئ‚µ‚½‚ھپA‚خ‚آ‚جˆ«‚»‚¤‚ب—lژq‚إˆêڈu‚½‚ك‚ç‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپuپcپEپBپvپ@
پ@پu‹Pژہ‚³‚ٌپA‚ ‚ٌ‚½پA‚¤‚؟‚ة‰½‚©•¶‹ه‚ھ‚ ‚é‚ئ‚ب‚çپAژًˆù‚ـ‚ٌ‚إگŒ‚ء‚د‚ç‚ء‚ؤ‚ب‚¢‚ئ‚«—ˆ‚«‚ç‚ٌ‚ئ‚ثپHپBپ@‰½‚ھŒ¾‚¢‚½‚¢‚ج‚©ƒOƒfƒ“ƒOƒfƒ“‚ةگŒ‚ء‚ؤ‚½‚ç‚¢‚ء‚؟‚ه‚ٌ‚ـ‚ئ‚à‚ةکb‚à‚³‚ê‚ٌ‚½پ[‚¢پIپBچ،“x‚©‚ç‰ئ‚ة—ˆ‚éژ‚حپA’j‚炵‚م‚¤ژًˆù‚ـ‚ب‚¢‚إ‚µ‚ç‚س‚إ—ˆ‚ٌ‚µ‚ل‚¢پIپB‚»پ[‚µ‚½‚ç‚؟‚ل‚ٌ‚ئ‚¨‹q‚³‚ٌ‚ئ‚µ‚ؤپA‚ـ‚ئ‚à‚ةکb‘ٹژè‚ً‚µ‚ؤ‚ ‚°‚ـ‚·‚½‚¢پBپvپuپcپE‚¨پ[پIپA”»‚ء‚½پB‚ظ‚ٌ‚ب‚çچ،“x—ˆ‚éژ‚حˆù‚ـ‚ٌ‚إ—ˆ‚é‚©‚ç‚بپcپIپBپv
پ@‹Pژہ‚حپAƒ`ƒJ‚ج“°پX‚ئ‚µ‚½ژp‚ةŒ©‘—‚ç‚ê‚ب‚ھ‚çŒ؛ٹض‚ةچ~‚è‚ؤپAŒC‚ً‘f‘پ‚—ڑ‚¢‚½پBپ@‹}‚¢‚إ‹A‚é‚»‚ش‚è‚ًŒ©‚¹‚½‚‚ب‚¢‹Pژہ‚جگS‚ًŒ©“§‚©‚µ‚½‚و‚¤‚ةپA‹~‚¢‚جژè‚ًڈo‚µ‚ؤ‚‚ꂽپAƒ`ƒJ‚جٹç‚ً‹C‚ـ‚¸‚»‚¤‚ةƒ`ƒ‰ƒb‚ئŒ©‚½پB‚»‚ê‚©‚çپAپuƒuƒcƒuƒcپcپBپv‚ئˆ«‘ش‚ً‚آ‚«‚ب‚ھ‚çپAŒ؛ٹض‚جƒKƒ‰ƒXŒث‚ًƒKƒ`ƒƒƒ“‚ئ•آ‚ك‚ؤ‹A‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@‚¾‚ھپAƒ`ƒJ‚حŒxژ@‚ة“dکb‚ً‚©‚¯‚éگ^ژ—‚ً‚µ‚½‚¾‚¯‚إپAژہچغ‚ح‰ٌگü‚ح’ت‚¶‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پBپ@”é‚ك‚ç‚ꂽپu—E‹C‚ئ’mŒbپv‚ئپu‹@“]‚ج—ک‚‹C”z‚èپv‚ًژ‚آƒ`ƒJ‚ةپA‹Pژہ‚حٹ®‘S‚ة•‰‚¯‚½‚ج‚¾‚ء‚½پBپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حژً‚ة“M‚ꂽپuگlٹش‚ج‚‚¸پv‚ة‚ب‚ء‚½ڈX‚¢’j‚جژp‚ًپAŒ™‚ئŒ¾‚¤‚ظ‚اŒ©‚¹‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپi‚ا‚ٌ‚ب‚ةگl‚ةŒ™‚ي‚êپA‰Œ‚½‚ھ‚ç‚ꂽ‚èپA‚±‚جگ¢‚©‚猩•ْ‚³‚ê‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚àپAŒˆ‚µ‚ؤژ©–\ژ©ٹü‚ة‚ب‚炸پA‚±‚ج‚و‚¤‚بŒ©‹ê‚µ‚¢‘هگl‚¾‚¯‚ة‚حپAگâ‘خ‚ب‚é‚ـ‚¢پcپEپIپj‚ئگS‚ةژv‚ء‚½پB
پ@“V‚حپA‚â‚ھ‚ؤ–K‚ê‚éژژ—û‚ج‚½‚ك‚ةپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚ةگlٹش‚ئ‚µ‚ؤ‚جچإˆ«‚جŒ©–{‚ئ‹³ŒP‚ًŒ©‚¹‚ؤ‚‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚ء‚½پB‚ـ‚½پA—âگأ‚إ“Iٹm‚ة•¨ژ–‚ًڈˆ—‚·‚é•ê‚جƒ`ƒJ‚ج‘ش“x‚ةگS‚ً—¯‚ك‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚»‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA‹Pژہ‚ح‚à‚¤ƒ`ƒJ‚ھ‹ڈ‚é‘O‚إ‚حپAŒƒ‚µ‚–\‚ꂽ‚肵‚ب‚‚ب‚ء‚½پBچ،‚ـ‚إچ،ˆن‰ئ‚جگlٹش‚ة‘خ‚µ‚ؤژg‚ء‚ؤ—ˆ‚½پAگŒ‚ء‚½گ¨‚¢‚إ‚ج‹؛‚©‚µ‚ھپAƒ`ƒJ‚ة‚ح‘S‘RŒّ‚©‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًŒه‚ء‚½‚ج‚¾‚ء‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚حپA‚±‚ج‹Pژہ‚ئ‚ج’·‚¢گي‚¢‚ةŒˆ’…‚ً•t‚¯‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈں•‰‚ئŒˆ’…پBپ@
پ@‚»‚ê‚©‚炵‚خ‚ç‚Œo‚ء‚½‚ ‚é“ْپAچؤ‚ر‹Pژہ‚ھگq‚ث‚ؤ—ˆ‚½پBƒ`ƒJ‚حژd•û‚ب‚ڈoŒ}‚¦‚½پB
پuچ،“ْ‚حژًˆù‚ٌ‚إ—ˆ‚ب‚©‚ء‚½‚낤‚ثپHپAژًˆù‚ٌ‚إ—ˆ‚½‚ç“ü‚ê‚ؤ‚â‚ç‚ٌ‚ئŒ¾‚¤‚ئ‚ء‚½‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپHپBپvپuچ،“ْ‚حˆù‚ٌ‚ا‚ç‚ٌپIپBˆù‚ـ‚ٌ‚إ‚µ‚ç‚س‚إ—ˆ‚½پcپBپvپu‚ظ‚ٌ‚ئ‚ثپ[پB‚ظ‚ٌ‚ب‚ç‚ ‚ٌ‚½‚حچ،“ْ‚¾‚¯‚ح‚¨‹q‚³‚ٌ‚½‚¢پB‚ا‚¤‚¼ڈم‚è‚ب‚ء‚¹پBپv
پ@ƒ`ƒJپA‚حŒ¾‚¢‚آ‚¯‚ًژç‚ء‚ؤ—ˆ‚½‹Pژہ‚ً‚¨‹q‚ئ‚µ‚ؤ‰‘خ‚µپAˆê‰‚¨’ƒ‚ًڈo‚µ‚ؤ‚ ‚°‚½پBپ@—ژ‚؟’…‚¢‚½‚ئ‚±‚ë‚إپAپu‚ ‚ب‚½‚ج•êگe‚ئپA‚¤‚؟‚ج”k‚؟‚ل‚ٌ‚ح‚½‚ء‚½“ٌگl‚¾‚¯‚جژo–…‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپcپA‚»‚ê‚ب‚ج‚ةپA‚ ‚ٌ‚½‚ھڈںژè‚ةپA‚à‚¤گeگت•tچ‡‚¢‚ً‚³‚¹‚ٌ‚ء‚ؤŒˆ‚ك‚ؤپA‚±‚ٌ‚بژâ‚ر‚µ‚©‚±‚ئ‚ح–³‚©‚إ‚µ‚ه‚¤پB‘¼‚ة’N‚àگg“à‚ھ‚¢‚ب‚¢‚ج‚ة‰آˆ£‚»‚©‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپBپvپuپcپBپv
پ@پu‚ ‚ٌ‚½‚ح‚»‚ê‚إ—ا‚©‚낤‚¯‚اپA”k‚؟‚ل‚ٌ‚½‚؟‚ح‰½‚جٹضŒW‚ب‚©‚ئ‚ةپA‚¤‚؟‚ئ‚ ‚ٌ‚½‚جŒ–‰ـ‚ةٹھ‚«چ‚ـ‚ب‚‚ؤ‚à—ا‚©‚낤‚ھپIپBپvپuپcپBپvپuچإڈ‰‚©‚ç‚ ‚ٌ‚½‚ھ‚«‚؟‚ٌ‚ئژً‚ةگŒ‚ي‚ٌ‚إکb‚ة—ˆ‚é‚ب‚çپA‚؟‚ل‚ٌ‚ئˆê‘خˆê‚جچ·‚µ‚إژû‚ـ‚锤‚¶‚ل‚ب‚¢‚ثپBپvپu‚ ‚ پcپBپv
پ@ژً‚ج“ü‚ء‚ؤ‚ب‚¢‹Pژہ‚حپAگl‚ھ•د‚ء‚½‚و‚¤‚ة‚¨‚ئ‚ب‚µ‚©‚ء‚½پBƒ`ƒJ‚حپAچ،‚ـ‚إŒë‰ً‚إپA‚±‚¶‚ꂽ–â‘è‚ة‚آ‚¢‚ؤپAˆê‚آˆê‚آپAƒLƒbƒ`ƒٹ‚ئ‚¯‚¶‚ك‚ً•t‚¯‚ؤگà–¾‚µ‚½پB—ژ‚؟’…‚¢‚ؤپAƒ`ƒJ‚جکb‚µ‚ً•·‚‚ئپA’m‚ç‚ت‚±‚ئ‚ئ‚حŒ¾‚¦پAچ،‚ـ‚إژ©•ھ‚ج‚µ‚½‚±‚ئ‚إپAچ،ˆن‰ئ‚ة–ہکf‚ً‚©‚¯پA‹C‚ج“إ‚ب‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ”»‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB
پ@‹Pژہ‚حپAŒë‰ً‚ھ‰ً‚¯‚½‚ئ‚«پAگe•ƒ‚جژèˆل‚¢‚إ‘¹ٹQ‚ً—^‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚ةپAڈ‚µگ\‚µ–َ‚ب‚³‚»‚¤‚ة‚µ‚½‚ھپAڈٹ‘FپA–ꂳ‚ٌ‚½‚؟‚ج—ژ‚؟“x‚إپAپu‰´‚ج’m‚ء‚½‚±‚ئ‚¶‚ل‚ب‚¢پIپBپv‚ئپAŒ¾‚ي‚ٌ‚خ‚©‚è‚ةپAƒEƒ„ƒ€ƒ„‚ج‚ـ‚ـŒˆ’…‚µ‚و‚¤‚ئ‚µ‚½پBپu‚¨پ[پAژ–ڈî‚ح‚و‚¤”»‚ء‚½پB‚»‚ٌ‚ب‚ç’‡’¼‚肽‚¢پB‚»‚ٌ‚ب‚爬ژ肵‚و‚¤پBپv
پ@‚à‚¤‰ك‹ژ‚ج‚±‚ئ‚ئ‚µ‚ؤ“ٌ“x‚ئ–â‘è‚ًڈِ‚µ•ش‚³‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‘’‚邽‚ك‚ةپAˆ¬ژ肵‚ؤپAƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“‚ئژè‚ً‘إ‚ئ‚¤‚ئ‚¢‚¤‚آ‚à‚è‚炵‚©‚ء‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚حپA‹Pژہ‚ج‚²‚ـ‚©‚»‚¤‚ئ‚¢‚¤‚¸‚é‚¢ژv‚¢‚ًŒ©“§‚©‚µ‚½پBپuƒtƒ“پAƒ`ƒFƒbپIپBپv‚ئگم‘إ‚؟‚µ‚ب‚ھ‚ç‚àپAچ،چXپAگج‚جژR‚ًژو‚è–ك‚·‹C‚à–³‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپAژè‚ًچ·‚µڈo‚µ‚ؤ‚¢‚é‹Pژہ‚ئپAژd•û‚ب‚ˆ¬ژ肵‚ؤپA’‡’¼‚肵‚ؤ‚ ‚°‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB‹Pژہ‚حپAپi‚±‚ê‚إ‚¨Œف‚¢‚ةگج‚جژ–‚حگ…‚ً—¬‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¨‚¤پBپj‚ئڈںژè‚ة“sچ‡‚ج—ا‚¢’ٌˆؤ‚ً‚µ‚½پB
پ@‚»‚جژپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚ھٹwچZ‚©‚ç‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB‹Pژہ‚ھچہ•~‚ةڈم‚ھ‚èچ‚ٌ‚إپA‰½‚â‚ç•ê‚ئکb‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚ح•ê‚جژ–‚ھگS”z‚ة‚ب‚èپAپi‰½‚©‚ ‚ء‚½‚ج‚©پBپHپj‚ئ‚¨‚ا‚¨‚ا‚µ‚ب‚ھ‚ç–T‚إŒ©‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚»‚ٌ‚بپu‚ـ‚±‚ئپv‚جژp‚ًŒ©‚é‚ئپAپu‚¨‚ءپA‚¨‘O‚ح‹I’j‚©پHپBپv‚ئ•·‚¢‚½پBپu‚¢‚¢‚âپA’ي‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚¢پBپvپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA–ظ‚ء‚ؤ‹Pژہ‚جٹç‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA‘م‚ي‚è‚ة•ê‚ھ“ڑ‚¦‚½پB‹Pژہ‚حپA‰½‚©‚¢‚ë‚¢‚ë‚ئکb‚µ‚©‚¯‚ؤ—ˆ‚½‚ھپAƒjƒRƒٹ‚ئ‚à‚µ‚ب‚¢–³•\ڈî‚ج‚¨‚ئ‚ب‚µ‚¢پu‚ـ‚±‚ئپv‚ًلة‚ف•t‚¯‚é‚ئپAپu‚¨‘O‚ح‚¨‚ئ‚ب‚µ‚©‚ثپ[پA‰´‚ئ‰½‚à’‚è‚«‚ç‚ٌ‚ج‚©پIپBپv‚ئ•ج‚ق‚و‚¤‚ةŒ¾‚ء‚½پBپuپcپBپv
پ@پuپu‚ـ‚±‚ئپv‚حƒ`ƒJ‚و‚èپAگ³ٹىژ—‚جژq‹ں‚â‚بپ[پBپv‚ئ”nژ‚ة‚·‚é‚و‚¤‚ةŒ¾‚ء‚½پB‚·‚é‚ئƒ`ƒJ‚حپAپu‚»‚¤‚½‚¢پA‚±‚جژq‚ح‚¤‚؟‚جژq‹ں‚¶‚ل‚ب‚©‚ئپIپB‚و‚»‚©‚çڈE‚ء‚ؤ—ˆ‚½ژq‹ں‚½‚¢پAƒnƒnپcپBپv‚ئڈç’k‚ًŒ¾‚ء‚ؤ‚©‚ي‚µ‚½پB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‹Pژہ‚ئƒ`ƒJ‚جŒ¾—t‚ة‚ذ‚ا‚ڈ‚آ‚¢‚½پBپi•ƒ‚جژq‚إ‰½‚ھˆ«‚¢پcپIپB‚»‚ê‚ة•ê‚³‚ٌ‚ـ‚إژ©•ھ‚جژq‚¶‚ل‚ب‚¢‚ب‚ٌ‚ؤچ“‚¢‚¶‚ل‚ب‚¢‚©پcپj‚ئ“àگSژv‚¢‚ب‚ھ‚çپAپi•ê‚حژم‚ف‚ًˆ¬‚ç‚ê‚ب‚¢ˆ×‚ةپA‘هگl‚ج‹ى‚¯ˆّ‚«‚جŒ¾—t‚جپAŒy‚¢ڈç’k‚ج‚â‚è‚ئ‚è‚ً‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚낤پcپBپj‚ئ‰ًژك‚µ‚ؤ‹–‚»‚¤‚ئژv‚ء‚½پB
پ@‹Pژہ‚حپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚ھƒ`ƒJ‚جŒŒ‚و‚è‚àپA•ƒ‚جگ³ٹى‚ج‚¨‚ئ‚ب‚µ‚¢گ«ٹi‚ًژَ‚¯Œp‚¢‚إ‚¢‚邱‚ئ‚ًŒ©”²‚¢‚ؤ‚¢‚½پBٹm‚©‚ةپA‚±‚جژ‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپAچ،ˆن‰ئ‚جپA‚ج‚ٌ‚ر‚è‚ئ‚µ‚½پA‚¨‚ئ‚ب‚µ‚¢گ«ٹi‚ج‚ف‚ًپAژَ‚¯Œp‚¢‚إ‚¢‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚½پB‚¾‚ھپA‚»‚ج“à‘¤‚ة‚حپA“cŒû‰ئ‚جŒƒ‚µ‚‹‚¢‹Cگ«‚ھ–§‚©‚ة‰èگ¶‚¦‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پi‚¨‘O‚ب‚ٌ‚©‚ئپA‚ـ‚ئ‚à‚ةکb‚¹‚é‚©پIپA‚³‚ء‚³‚ئ‘پ‚‹A‚êپIپcپBپj‚ئ‚¢‚¤ژv‚¢‚ھپAچ،‚ة‚àگ؛‚ة‚ب‚é’¼‘O‚إپAŒƒ‚µ‚‚‚·‚ش‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚ء‚½پB
پ@ٹm‚©‚ةپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚ ‚éژ‚ـ‚إپA“cŒû‰ئ‘¤‚جگlٹش‚ئپAŒƒ‚µ‚‘خ—§‚·‚é‚و‚¤‚ب‰^–½‚ة’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚½پBƒ`ƒJ‚حپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚ةپAنn‚ج‚±‚ئ‚ًکb‚·ژپA‚¢‚آ‚àپu‚¨‘O‚ج–ꂳ‚ٌ‚½‚¢پIپBپv‚ئپAٹى•½‚جپA‚¢‚¢‰ءŒ¸‚ب‘خ‰‚ھڈµ‚¢‚½چذ‚¢‚ةپA‚و‚ء‚غ‚ا• ‚ً—§‚ؤ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚©پAپu‚ـ‚±‚ئپv‚àپAٹى•½‚ئ“¯‚¶‚پAچ،ˆن‰ئ‚ج‚¢‚¢‰ءŒ¸‚بŒŒ‹ط‚ًژَ‚¯Œp‚¢‚إ‚¢‚é‚ئپAˆأ‚ةŒˆ‚ك‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚±‚ë‚ھ‚ ‚ء‚½پBپ@
پ@‚±‚¤‚µ‚ؤ‚»‚êˆب—ˆپA‹Pژہ‚حŒˆ‚µ‚ؤگŒ‚ء‚ؤ‰ئ‚ة—ˆ‚ب‚‚ب‚ء‚½پBپ@گ‹‚ةƒ`ƒJ‚حپA‚±‚جƒLƒcƒl‚ج‚و‚¤‚ب’j‚ئ‚ج’·‚¢گي‚¢‚ةپAٹ°—e‚ئ‹–‚µ‚جگ¸گ_‚إŒˆ’…‚ً‚آ‚¯‚½‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ…‚جگي‚¢پB
پ@‚ ‚éگ…•s‘«‚ج”N‚جڈ‹‚¢‰ؤ‚ج“ْ‚¾‚ء‚½پB
ƒ`ƒJ‚ھ‹v‚µ‚ش‚è‚ةژR‚ة“o‚ء‚ؤŒ©‚é‚ئپA“c‚ٌ‚ع‚ھ‚·‚ء‚©‚èٹ±ڈم‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپ@‚ذ‚ر‚ھ“ü‚ء‚ؤپAچ،‚ة‚àˆî‚ھŒح‚ê‚©‚©‚ء‚ؤ‚¢‚½پBƒ`ƒJ‚ح‚ ‚ي‚ؤ‚ؤگىŒû‚ج•û‚ًŒ©‚ةچs‚‚ئپA‚¤‚؟‚ج“c‚ٌ‚ع‚ة—¬‚ê‚ؤ‚¢‚‚ح‚¸‚جٹض‚ةپA‘ه‚«‚بگخ‚ھگد‚فڈم‚°‚ç‚ê‚ؤ‘S‘Rگ…‚ھ—¬‚ê‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤ‚ ‚ء‚½پBپu’N‚ھ‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ً‚µ‚½‚ج‚¾‚낤پcپv
پ@ƒ`ƒJ‚حپA“{‚è‚ًٹo‚¦‚ب‚ھ‚çپA‰؛—¬‚ج•û‚ة’H‚ء‚ؤ•à‚¢‚ؤچs‚‚ئپA‘SٹJ‚µ‚½ٹض‚ًŒ©‚آ‚¯‚½پB
‚»‚±‚ح—ׂج“c‚ٌ‚ع‚إپAگ…‚ھˆى‚ê‚é’ِپuƒUپ[ƒUپ[پv‚ئ—¬‚êچ‚ٌ‚إ‚¢‚½پBƒ`ƒJ‚ح“{‚è‚ً‰ں‚³‚¦‚«‚ê‚ب‚‚ب‚èپA—ׂج“c‚ٌ‚ع‚ة‚¢‚éگl‚جڈٹ‚ةƒcƒJƒcƒJ‚ئ‹كٹٌ‚ء‚½پB
پ@پu‚¤‚؟‚جˆî‚ھŒح‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ةپA‚¨‚½‚‚ج“c‚ٌ‚ع‚¾‚¯پAگڈ•ھڈپ‚ء‚ؤ‚ـ‚·‚ثپv
پuپcپcپvپu‚¢‚‚çگ…•s‘«‚إچ¢‚ء‚ؤ‚àپA‚±‚ٌ‚بژ‚ح‚¨Œف‚¢—l‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚¤‚؟‚ج•û‚ة—¬‚ê‚éٹض‚ًٹ®‘S‚ةژ~‚ك‚ؤ‚àپAژ©•ھ‚½‚؟‚¾‚¯ڈپ‚¦‚خ‚¢‚¢‚ئ‚¢‚¤چl‚¦‚إ‚·‚©پHپv
پ@ˆê”N‚ج‹êکJ‚ھ–³‘ت‚ة‚ب‚èپAژûٹn‚ھ–³‚‚ب‚邱‚ئ‚حپAˆê‰ئ‚جژ€ٹˆ‚ج–â‘肾‚ء‚½پB
پ@‚¾‚ھپAگ…‚ً“ئگ肵‚½—×گl‚حپAˆê‚آ‚àژس‚낤‚ئ‚µ‚ب‚©‚ء‚½پBپuگl‚ج‚±‚ئ‚ب‚ٌ‚©’m‚ء‚½‚±‚ئ‚¶‚ل‚ب‚¢‚وپIپv•ê‚ح‚»‚ٌ‚بژ©•ھڈںژè‚ب‘ش“x‚ج—×گl‚ھ‹–‚¹‚ب‚©‚ء‚½پBŒƒ‚µ‚¢ŒûŒ–‰ـ‚ً‚µ‚ؤƒ`ƒJ‚ح‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB
پ@‚ـ‚¾—c‚©‚ء‚½––‚ءژq‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپAƒ`ƒJ‚ھ‹»•±‚µ‚ب‚ھ‚ç–ك‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤپAƒ[ƒ“‚ة‚³‚ء‚«‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚ًکb‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ً–T‚إ•·‚¢‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚»‚ê‚©‚炵‚خ‚ç‚‚½‚ء‚½‚ ‚é“ْپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپAƒNƒ‰ƒX‚ج“¯‹‰گ¶‚½‚؟‚ًژR‚ةکA‚ê‚ؤ—ˆ‚½پBٹwچZ‚إپu‚¤‚؟‚جژR‚ة‚ف‚©‚ٌ‚ًژو‚è‚ة—ˆ‚ب‚¢‚©پHپv‚ئ—U‚ء‚½‚çژOگl‚ظ‚ا‚آ‚¢‚ؤ—ˆ‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپAگ…‚ً’D‚ء‚½—ׂجگl‚جپAژR‚ة‚ب‚ء‚½ƒ~ƒJƒ“”¨‚ةپu‚¤‚؟‚ج”¨‚جƒ~ƒJƒ“‚¾‚©‚ç‚¢‚‚ç‚إ‚àگH‚ׂؤ‚¢‚¢‚وپv‚ئ‰R‚ًŒ¾‚ء‚ؤپA‚ف‚ٌ‚ب‚ةڈںژè‚ة‚؟‚¬‚ء‚ؤگH‚ׂ³‚¹‚½پBپ@‰½ŒجپA‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ً‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ج‚©پAپu‚ـ‚±‚ئپv‚à‚و‚”»‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@
---------------------------------------------------
پ@
پu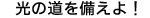 پvپ@ پvپ@ پ@ پ@
پ@‘و“ٌ•”پ@ƒ`ƒJ’è’…ژ‘م
پ@پi پjپ@‚¨‚ي‚èپB پjپ@‚¨‚ي‚èپB
پ@پ@
---------------------------------------------------
پ@
‚¨‚ي‚èپB
|
پ@ژه‚جŒ¾—t‚ھژ„‚ة—ص‚ٌ‚¾پBپuگl‚جژq‚وپA‚ ‚ب‚½‚حˆê–{‚ج–ط‚ًژو‚èپA‚»‚جڈم‚ةپwپc‚ئپc‚جژq‘·‚ج‚½‚ك‚ةپx‚ئڈ‘‚«پA‚ـ‚½‚à‚¤ˆê–{‚ج–ط‚ًژو‚ء‚ؤپA‚»‚جڈم‚ةپwپc‚ئپc‘S‰ئ‚ج‚½‚ك‚ةپx‚ئڈ‘‚¯پB‚±‚ê‚حپiƒGƒtƒ‰ƒCƒ€‚ج–طپj‚إ‚ ‚éپB‚ ‚ب‚½‚ح‚±‚ê‚ç‚ًچ‡‚ي‚¹‚ؤپAˆê‚آ‚ج–ط‚ئ‚ب‚¹پB‚±‚ê‚ç‚ح‚ ‚ب‚½‚جژè‚إˆê‚آ‚ة‚ب‚éپBپ@پ@ƒGƒ[ƒLƒGƒ‹‚R‚Sڈح‚P‚T |
پ@
پ@’mŒb‚ً‹پ‚ك‚ؤ‚¢‚éگlپAŒه‚è‚ً“¾‚éگl‚حچK‚¢‚إ‚ ‚éپB’mŒb‚ة‚و‚ء‚ؤ“¾‚é‚à‚ج‚ح‹â‚ة‚و‚ء‚ؤ“¾‚é‚à‚ج‚ة—D‚èپA‚»‚ج—ک‰v‚ح‹à‚و‚è‚à—ا‚¢‚©‚ç‚إ‚ ‚éپBپ@’mŒb‚ح•َگخ‚و‚è‚à‘¸‚پA‚ ‚ب‚½‚ج–]‚ق‰½•¨‚àپA‚±‚ê‚ئ”ن‚ׂé‚ة‘«‚è‚ب‚¢پB‚»‚ج‰E‚جژè‚ة‚حپA’·ژُ‚ھ‚ ‚èپAچ¶‚جژè‚ة‚ح•x‚ئپA—_‚ê‚ھ‚ ‚éپB
پ@‚»‚ج“¹‚حٹy‚µ‚¢“¹‚إ‚ ‚èپA‚»‚ج“¹‹ط‚ح‚ف‚ب•½ˆہ‚إ‚ ‚éپB
’mŒb‚حپA‚±‚ê‚ً•ك‚炦‚éژز‚ة‚حپu–½‚ج–طپv‚إ‚ ‚éپA‚±‚ê‚ً‚µ‚ء‚©‚è•ك‚炦‚éگl‚حچK‚¢‚إ‚ ‚éپBژه‚حپA’mŒb‚ً‚à‚ء‚ؤ“V‚ً’è‚ك‚ç‚ꂽپB
پ@‰ن‚ھژq‚وپAٹm‚©‚ب’mŒb‚ئپAگT‚ف‚ئ‚ًژç‚ء‚ؤپA‚»‚ê‚ً‚ ‚ب‚½‚ج–ع‚©‚ç—£‚µ‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚»‚ê‚ح‚ ‚ب‚½‚جچ°‚ج–½‚ئ‚ب‚èپA‚ ‚ب‚½‚جژٌ‚جڈü‚è‚ئ‚ب‚éپB‚±‚¤‚µ‚ؤپA‚ ‚ب‚½‚حˆہ‚ç‚©‚ةژ©•ھ‚ج“¹‚ًچs‚«پA‚ ‚ب‚½‚ج‘«‚ح‚آ‚ـ‚¸‚‚±‚ئ‚ھ–³‚¢پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@⼌¾پAژOڈحڈ\ژOگك
’·•زڈ¬گàپu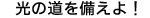 پvپ@ پvپ@
‡AپA پ@‘و“ٌ•”پiƒ`ƒJ’è’…ژ‘م‡Aپj پ@‘و“ٌ•”پiƒ`ƒJ’è’…ژ‘م‡Aپj
پ@
‚¨‚ي‚èپBپ@
پ@ |