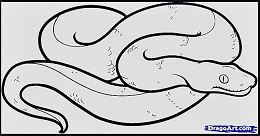ژQپ@چlپB
پu ‰“کH‚ج‰ت‚ؤ‚ةپB پv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@“cŒû گ³گ_پB
پu—َ•—‚ج‹u‚ة—§‚؟‚ؤپBپvپ@پ@پ@“cŒû ƒ`ƒJپB
پuˆîچب‚ھ‘M‚«“n‚éژپBپvپ@پ@‚ظ‚ج‚ع‚ج“¶ژqپB
“َپA“¬‘ˆ•زپB
‘و‚P•”پBƒ`ƒJپAڈC—ûژ‘مپB
‘و‚Q•”پBƒ`ƒJپA’è’…ژ‘مپB
پ@
‘و‚R•”پB
پ@
‡BپAƒ`ƒJپAŒƒ“¬ژ‘مپB
‚PکbپB
‚OپAپ@‚PپBپ@‚QپAپ@‚RپAپ@‚SپAپ@‚T
پA
پ@
‘Oپ@•زپBپ@پ@Œمپ@•زپB
|
پ@
‚àپ@‚پ@‚¶پB
|
پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@‚ح‚¶‚ك‚ةپB
پ@
ڈ¬پ@گàپBپ@
پuŒُ‚ج“¹‚ً”ُ‚¦‚وپIپBپv
پ@
“َپA“¬‘ˆ•زپBپAپ@‘و‚R•”پBپAپ@
‡BپAƒ`ƒJپAŒƒ“¬ژ‘مپB
‚PپB
‚OپAپ@پ@‚PپBپ@پ@‚QپAپ@پ@‚RپAپ@پ@‚SپAپ@پ@‚TپAپ@
پ@
‰ًپ@گàپB
’·•زپ@ڈ¬گàپB
پuŒُ‚ج“¹‚ً”ُ‚¦‚وپIپBپv
“َپA“¬‘ˆ•زپBپ@پ@‘و‚R•”پB
ƒ`ƒJپAŒƒ“¬ژ‘مپB
‚جپA ‚ ‚ç‚·‚¶پBپ@‚à‚‚¶پB
‚OپAپ@‚PپBپ@‚QپAپ@‚RپAپ@‚SپAپ@‚TپA
پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@“¦‚ꂽگآژضپB
پ@—[•é‚ê‚ة‚ب‚ء‚½‹َ‚ج‰؛پAژR‚جژdژ–‚ًڈI‚¦‚ؤƒ[ƒ“‚حگgژx“x‚µ‚ؤ‹A‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚ـ‚¾ڈ¬‚³‚ب‚©‚آ‚¦‚ئپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‹à‹›‚جƒtƒ“‚ج‚و‚¤‚ةپAƒ[ƒ“‚ج‚»‚خ‚ة‚‚ء‚آ‚¢‚ؤŒم‚ً•à‚¢‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
پ@ƒ~ƒJƒ“‚âٹ`‚جگ¶‚¦‚½چׂ¢“¹‚ةچ·‚µٹ|‚©‚ء‚½ژ‚¾‚ء‚½پB“¹‰ˆ‚¢‚و‚èˆê’iچ‚‚¢‚ف‚©‚ٌ”¨‚ةگ¶‚¦‚½ƒ~ƒJƒ“‚ج–ط‚ج—t‚ھ—h‚ê‚ؤ‚¢‚½پB‚©‚آ‚¦‚حپi‚ب‚ٌ‚¾‚낤پHپBپj‚ئ‚س‚ئŒ©ڈم‚°‚½پB‚ـ‚¾ƒ~ƒJƒ“‚جژہ‚حگآ‚پA—خ‚ج—t‚ج’†‚ة–„‚à‚ê‚ؤŒ©•ھ‚¯‚ھ‚آ‚©‚ب‚©‚ء‚½پB‚»‚ج—خ‚ج—t‚جژ}‚ة–ع‹ت‚جƒpƒbƒ`ƒٹ‚µ‚½‚©‚ي‚¢‚¢ژq‹ں‚جژضپv‚ھژ}‚ً“`‚ء‚ؤ“o‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ًŒ©‚آ‚¯‚½پB
پ@
پ@پu‚ ‚ءپA‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌپIپA‚ظ‚猩‚ؤپA‰آˆ¤‚¢پ[پIپBپv‚»‚جگ؛‚ةپAگو‚ة•à‚¢‚ؤ‚¢‚½ƒ[ƒ“‚ئپu‚ـ‚±‚ئپv‚حگU‚è•ش‚èپA‚©‚آ‚¦‚جژw‚³‚·•ûŒü‚ًŒ©‚½پBپ@‚»‚±‚ة‚حگ¶‚ـ‚ꂽ‚خ‚©‚è‚جپAگآ—خ‚جپuڈ¬‚³‚بژضپv‚ھپAƒ~ƒJƒ“‚جژ}—t‚جڈم‚ة—h‚ê‚ؤ‚¢‚½پBپu‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌپA‚؟‚ه‚ء‚ئŒ©’£‚ء‚ئ‚ء‚ؤ‚ثپA‚·‚®کUپi‚ؤ‚عپj‚ًژو‚ء‚ؤ—ˆ‚邯‚ٌپBپvپ@‚»‚¤Œ¾‚¤‚ئ‚©‚آ‚¦‚ح‹}‚¢‚إڈ¬‰®‚ة–ك‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پBپ@ڈ¬‰®‚ة’u‚¢‚ؤ‚ ‚éکU‚ًژو‚è‚ة‘ه‹}‚¬‚إ‘–‚ء‚ؤ‚¢‚‚©‚آ‚¦‚جژp‚ًپA“ٌگl‚ح‚ ‘R‚ئ‚µ‚ؤŒ©‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
پ@پi‚ٌپcپHپBپjƒ[ƒ“‚حژq‹ں‚جژض‚ًƒJƒS‚ة“ü‚ê‚ؤژ‚ء‚ؤ‹A‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚آ‚¦‚ةپuƒMƒ‡ƒbپIپBپv‚ئ‚µ‚ؤپu‚ـ‚±‚ئپv‚جٹç‚ًŒ©‚½پBپu‚©‚آ‚¦‚حپA‚ا‚¤‚·‚é‚آ‚à‚è‚â‚ë‚©پHپAژض‚ًژ‚ء‚ؤ‹A‚é‚آ‚à‚è‚خ‚¢پBپvپu‚¤‚ٌپcپBپv
پ@
پ@Œ©‚é‚ئپA‚ـ‚¾گ¶‚ـ‚ꂽ‚خ‚©‚è‚جژض‚إپA‚¬‚±‚؟‚ب‚–ط“o‚è‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپuپu‚ـ‚±‚ئپvپA‚©‚ي‚¢‚»‚¤‚â‚©‚çپA“¦‚ھ‚µ‚ؤ‚â‚낤‚خ‚¢پBپvپu‚¤‚ٌپA“¦‚ھ‚µ‚ؤ‚â‚낤پBپvپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA’¼ٹ´“I‚ةƒ[ƒ“‚جˆسŒ©‚ًگ³‚µ‚¢‚ئژv‚ء‚½پBپ@پu‚ـ‚±‚ئپvپ@‚ئپ@ƒ[ƒ“‚حپA‚©‚آ‚¦‚ھ–ك‚ء‚ؤ—ˆ‚ب‚¢ٹش‚ةپAپuƒKƒTƒKƒTپIپv‚ئژ}‚ً—h‚·‚ء‚ؤ“¦‚ھ‚µ‚ؤ‚ ‚°‚½پBپu‚ح‚و‚¤“¦‚°‚ëپA‚ح‚و‚¤“¦‚°‚ëپA‚¨‘OپA•ك‚ـ‚邼پIپBپvپ@ژض‚ح‹ء‚¢‚½‚ج‚©پAژ}‚ً“`‚ء‚ؤƒ`ƒ‡ƒچƒ`ƒ‡ƒچ‚ئ‘گ‚ق‚ç‚ة“¦‚°‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤپA‚©‚آ‚¦‚حپAڈ¬‚³‚بکU‚ًژè‚ة‰؛‚°‚ؤپA‘ه‹}‚¬‚إ–ك‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB‚»‚ج‚¢‚ء‚µ‚ه‚¤Œœ–½‚بژp‚ًŒ©‚ب‚ھ‚çپA“ٌگl‚حڈ‚µ—اگS‚ج™èگس‚ًٹ´‚¶‚ؤ‚¢‚½پBپu‚ پ[‚ پA’x‚©‚ء‚½‚ثپ[پB‚à‚¤“¦‚°‚ؤ‚µ‚à‚¤‚½‚¼پ[پvپu‚¦پIپA‚بپ[‚ٌپB‚àپ[‚¤پcپBپvپ@‚©‚آ‚¦‚ح‚ھ‚ء‚©‚肵‚½پBپuژض‚ح“¦‚°‘«‚ھ‘پ‚©‚ثپ[پAپvپ@پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA–َ‚ج•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًŒ¾‚ء‚ؤپA‚»‚جڈê‚ًŒë–‚‰»‚µ‚½پBپu‚ پ[‚ٌپA‚àپ[‚¤پA‰آˆ¤‚©‚ء‚½‚ج‚ةپ[پcپBپvپuپcپBپvپu‚ ‚ٌ‚ب‰آˆ¤‚¢–ع‚ً‚µ‚½ژض‚ح‚à‚¤‚¨‚ç‚ٌ‚â‚ء‚½‚ج‚ةپ[پBپvپu‚ ‚ پA‚»‚¤‚ثپ[پA‚خ‚ء‚ؤ‚ٌپA‚µ‚ه‚ٌ‚ب‚©‚½‚¢پBپvپ@‚©‚آ‚¦‚حپAƒ[ƒ“‚ةˆش‚ك‚ç‚ê‚ب‚ھ‚çپAƒJƒ‰‚جکU‚ًپA‚¾‚é‚»‚¤‚ة‰؛‚°‚ؤپAژc”O‚»‚¤‚ةپA‰½“x‚àگU‚è•ش‚è‚ب‚ھ‚çپAژR‚ًچ~‚è‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@
پ@-----------------------------------
پ@
پ@‚±‚جپAکU‚ج’†‚ة“ü‚ê‚ç‚ê‚é’¼‘O‚إپAٹë‹@ˆê”پA“ï‚ً”ً‚¯‚ؤپu“¦‚°‚½گآژضپv‚حپA‰“‚¢ڈ«—ˆ‚جپu‚ـ‚±‚ئپvژ©گg‚ج‰^–½‚ًˆأژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚½پBڈ¬‚³‚بگآ‚¢ژض‚حڈم‚ةŒü‚©‚ء‚ؤˆêگ¶Œœ–½‚ة“o‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپ@‚¾‚ھکA‚ê‹ژ‚낤‚ئ‚·‚éڈ—‚جژq‚جژ‚آƒJƒS‚جٹë‹@‚©‚瓦‚êپA‚ذ‚ئ‚ـ‚¸ƒ~ƒJƒ“‚ج–ط‚ً‰؛‚è‚ؤپA–T‚ج‘گ‚ق‚ç‚ج’†‚ة“¦‚°‚ؤگِ‚ٌ‚¾پB
پ@
پ@‚±‚جژض‚حپAژR‚ًگأ‚©‚ةŒ©ژç‚葱‚¯‚éپuژR‚جژهپv‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚پBپ@‚â‚ھ‚ؤڈI‚ي‚è‚ج“ْ‚ھ‹ك‚أ‚چ پAچ،ˆن‰ئ‚جژR‚ھپAˆî•ن‚©‚çپA‘N‚â‚©‚بƒ~ƒJƒ“”¨‚ة•د‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚“ْ‚ھ—ˆ‚éپBپ@‚»‚جژپA•َگخ‚ج‚و‚¤‚ة‹P‚ƒIƒŒƒ“ƒWگF‚ج‹ت‚ھپAژR‚ً•¢‚¢‚آ‚‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚ھپAژض‚جٹè–]‚إ‚à‚ ‚èپAƒIƒŒƒ“ƒWگF‚ة‹P‚‘¶چف‚ً–¾‚©‚·‚±‚ئ‚ھپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚جˆêگ¶‚ً‚©‚¯‚éچإ‘ه‚جژg–½‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚پB
پ@-----------------------------------
پ@
پ@
پ@
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œڑ‚ؤ’¼‚µ‚جژپB
پ@چ،ˆن‰ئ‚ج‰ئ‚حپA‚©‚ب‚èŒأ‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‘ن•—‚ھ‚‚邽‚رپA“Vˆن‚ج‚ ‚؟‚炱‚؟‚ç‚©‚çپA‰JکR‚è‚ھ‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پBƒ[ƒ“‚حپA“Vˆن‚©‚ç—ژ‚؟‚ؤ—ˆ‚éگ…“H‚ھپAڈô‚ف‚جڈم‚ً‚ت‚ç‚·‚ج‚ًŒ©‚é‚ئپAƒoƒPƒc‚âگô–تٹيپA’ƒکq‚ب‚ا‚ً‹}‚¢‚إڈW‚كپA‚»‚±‚ç’†‚ة’u‚¢‚½پBپ@•—‚ھگپ‚‚ئپAƒMƒCƒMƒC‚ئچ،‚ة‚à•ِ‚ê‚»‚¤‚ة‚èپA“Vˆن‚â’Œ‚©‚ç‚«‚µ‚ق‰¹‚ھ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
پ@پu‚¦‚¸‚©پ[پi•|‚¢پjپB‚ح‚و‚¤‰ئ‚ًŒڑ‚ؤ’¼‚³‚ب‚¢‚ئ‚¢‚©‚ٌ‚خ‚¢پB‚¨‚çپA‚à‚¤‹°‚낵‚‚ؤ‚±‚ٌ‚ب‰ئ‚ة‚ح‚¨‚è‚«‚ç‚ٌپIپBپvپ@ƒ[ƒ“‚حپAƒ`ƒJ‚ة•¶‹ه‚ًŒ¾‚ء‚½پBپ@ژ©•ھ‚½‚؟‚ج‘م‚إپA‚ئ‚¤‚ئ‚¤‰ئ‚ھŒڑ‚ؤ’¼‚¹‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚ةپA‘§ژq‚â‰إ‚ج‘م‚ةڈd‰×‚ً‰ں‚µ‚آ‚¯‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚إپAƒ`ƒJ‚حڈ‚µ• ‚ً—§‚ؤ‚ب‚ھ‚ç•·‚¢‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚¹‚ء‚©‚پA‰ئ‚ًŒڑ‚ؤ’¼‚·‚½‚ك‚ج’Œ‚ة‚µ‚و‚¤‚ئپA‘هژ–‚ةژ}‚ً‚ح‚ç‚ء‚ؤˆç‚ؤ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚ةپAژR‚ج–ط‚حپAنn‚½‚؟‚جپA‚¢‚¢‰ءŒ¸‚ب‘خ‰‚إپA‚ ‚جƒLƒcƒl’j‚ة’D‚ي‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ج‚¾پB
پ@
پ@‚¾‚ھپA‚à‚¤•¶‹ه‚ًŒ¾‚ء‚ؤ‚àپA‚ا‚¤‚ة‚à‚ب‚é‚à‚ج‚إ‚à‚ب‚©‚ء‚½پBƒ`ƒJ‚حژd•û–³‚پAژط‹à‚ً‚µ‚ؤ‚إ‚àپAŒڑ‚ؤ’¼‚·‚±‚ئ‚ةŒˆ‚كپA•v‚جگ³ٹى‚ة‚à‘ٹ’k‚µ‚ؤ‚ف‚½پBپu”‹–ىپv‚ئ‚¢‚¤‘هچH‚³‚ٌ‚ةگ}–ت‚ًڈ‘‚¢‚ؤ–ل‚¢پAŒ©گد‚肵‚ؤ‚à‚ç‚ء‚½‚ھپA•n‚µ‚¢چ،ˆن‰ئ‚ج‰ئŒv‚ة‚حپA‘ه•د‚ب‹àٹz‚إ‚ ‚ء‚½پBŒژپX‚ج‹‹—؟‚©‚çŒvژZ‚µ‚ؤ‚ف‚½‚ھپA‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚à•شچد‚ة–³—‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ@پu•v‚جڈلٹQ‚ً——R‚ةپA’¬“à‰ï‚ة‘ٹ’k‚µ‚ؤژط‹à‚·‚ê‚خ‚¢‚¢پBپv‚ئ‚¢‚¤کb‚ھڈo‚½‚ھپAƒ`ƒJ‚ح‚«‚ء‚د‚è’f‚ي‚ء‚½پBپi‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚µ‚½‚çپA‚ ‚ئ‚إ‹كڈٹ‚©‚牽‚ًŒ¾‚ي‚ê‚é‚©”»‚ء‚½‚à‚ج‚¶‚ل‚ب‚¢پcپBپjپ@ƒ`ƒJ‚حپAپi”_‹ئ‚جژdژ–‚جچ‡ٹش‚ةپAژ©•ھ‚ھ“ْŒظ‚¢‚جژdژ–‚ً‚·‚ê‚خپA•v‚ج‹‹—؟‚ئچ‡‚ي‚¹‚ê‚خپA‚ا‚¤‚ة‚©•ش‚µ‚ؤ‚¢‚¯‚锤‚¾‚يپcپBپj‚ئپAگS‚ة• ‚أ‚à‚è‚ً‚µ‚ؤپA‘هچH‚³‚ٌ‚ة—ٹ‚ف‚ةچs‚ء‚½پB
پ@
پ@‚¾‚ھپA‚»‚ٌ‚بƒ`ƒJ‚ة‘خ‚µ‚ؤپAپu’N‚ة‚à—ٹ‚炸‚ةپA‚ظ‚ٌ‚ئ‚ة‚؟‚ل‚ٌ‚ئپA–ˆŒژ‚»‚ٌ‚ب‹àٹz‚ً•شچدڈo—ˆ‚é‚ئ‚إ‚·‚©پHپBپv‚ئپA‚¢‚ش‚©‚µ‚»‚¤‚ب‹^‚¢‚ج–ع‚إŒ©‚½پB
پ@پu—\ژZ‚ً—§‚ؤ‚ؤپAŒژپX‚؟‚ل‚ٌ‚ئٹشˆل‚¢‚ب‚•شچد‚µ‚ـ‚·‚©‚çپA‘هڈن•v‚إ‚·پBپvپu‚¢‚âپ[پAگ\‚µ–َ‚ھ‚ب‚¢‚ھپAٹë‚ب‚¢‹´‚ح“n‚ê‚ٌ‚خ‚¢پIپBپvپ@‘هچH‚ح—₽‚’f‚ي‚ء‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚حپAگM‚¶‚ؤ–ل‚¦‚ب‚¢‚ج‚ھ‰÷‚µ‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@ƒ`ƒJ‚حژd•û‚ب‚پA‚à‚¤ˆêŒ¬‚ج•ت‚ج‘هچH‚³‚ٌ‚ة—ٹ‚ف‚ةچs‚ء‚½پBپ@پu‚ئ‚ة‚©‚چإ’لپAڈZ‚ك‚邾‚¯‚ج‰ئ‚إ‚¢‚¢‚إ‚·پA”’•ا‚à“h‚ç‚ب‚‚ؤ‚¢‚¢‚إ‚·‚©‚çپA‰½‚ئ‚©‚±‚ج—\ژZ“à‚إŒڑ‚ؤ‚ؤ‚‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚©پHپBپvپuپcپBپvپu‚¤‚؟‚½‚؟‚àڈo—ˆ‚邱‚ئ‚حپA‰½‚إ‚àژè“`‚¢‚ـ‚·‚¯‚ٌپBپvپ@•Kژ€‚إ‚¨ٹè‚¢‚·‚éƒ`ƒJ‚جڈî”M‚ة•‰‚¯‚½‚ج‚©پA‘هچH‚³‚ٌ‚ح‚â‚ء‚ئ‚جژv‚¢‚إڈ³’m‚µ‚ؤ‚‚ꂽپBپ@‚±‚¤‚µ‚ؤپAŒأ‚¢‰ئ‚ح‰ً‘ج‚³‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پB‚»‚جٹشپA‰ئ‘°‚½‚؟‚ح•ƒ‚ج—Fگl‚ج‰ئ‚ة‰¼ڈZ‚ـ‚¢‚³‚¹‚ؤ–ل‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ŒںچُƒTƒCƒg‚©‚ç‚ج•û‚ح ƒgƒbƒvƒyپ[ƒW‚ض‰ٌ‚ء‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پ«
ڈ¬پ@پ@گàپB
پuŒُ‚ج“¹‚ً”ُ‚¦‚وپIپBپv |
 |
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚ـ‚و‚¤”LپB
پ@
پ@‰ئ‚ھŒڑ‚آ‚ـ‚إ‚جٹشپA“ٌڈ\Œ¬‚ظ‚اگو‚جپA•ƒ‚ج—c‚ب‚ب‚¶‚ف‚ج—F’B‚إ‚ ‚éپAپuڈ¼–{‚ج‚¨‚¶‚³‚ٌپv‚ج‰ئ‚ة‚µ‚خ‚ç‚–ï‰î‚ة‚ب‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پB‘c•ê‚جƒ[ƒ“‚ئپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚½‚؟‚حپAژ”‚ء‚ؤ‚¢‚½ژO–ر”L‚جپiƒ~ƒPپj‚ً•ّ‚¢‚ؤپA‰¼ڈZ‚ـ‚¢‚ةکA‚ê‚ؤ—ˆ‚½‚ھپA‚»‚ج‰ئ‚ة‚حٹù‚ة•ت‚جژO–ر”L‚ھژ”‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA•ّ‚¢‚ؤ—ˆ‚½ƒ~ƒP‚ً‚»‚ج”L‚ج‚·‚®‚»‚خ‚ةکA‚ê‚ؤ—ˆ‚ؤپAپu’‡—ا‚‚µ‚ؤ‚ثپBپv‚ئپA‚»‚خ‚ةچ~‚낵‚½پBپ@‚¾‚ھپAگو‚ة‚¢‚½”L‚حپAژ©•ھ‚ج“ê’£‚è‚ة“ü‚ء‚ؤ—ˆ‚½پAŒ©’m‚ç‚ت‚و‚»‚à‚ج‚ھ“ث‘RŒ»‚ي‚ꂽ‚ج‚إپA‹}‚ةŒx‰ْ‚µ‚½ٹç‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@
پ@ƒ~ƒP‚ج‘ج‚ةپA•@‚ً‹ك‚أ‚¯ƒNƒ“ƒNƒ“‚ئڈL‚¤‚µ‚®‚³‚ً‚µ‚½‚©‚ئژv‚¤‚ئپA‚½‚؟‚ـ‚؟پuƒtپ[ƒbپIپBپv‚ئ’ـ‚ً‚½‚ؤ‚ؤŒƒ‚µ‚¢Œ–‰ـ‚ً’§‚ٌ‚إ—ˆ‚½پB‚¢‚«‚ب‚èڈP‚ي‚ê‚ؤ‹ء‚¢‚½ƒ~ƒP‚حپA‚¢‚؟‚à‚ژU‚ة‰½ڈˆ‚©‚ة“¦‚°‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پBپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚·‚®ƒ~ƒP‚جŒم‚ً’ا‚ء‚½پB‹¯‚¦‚ؤپA”¨‚ج’†‚ً‹ى‚¯”²‚¯‚ؤ‚¢‚Œمژp‚ًŒ©‚آ‚¯‚ؤپAپuƒ~پ[پAƒ~پ[پIپBپv‚ئ‘هگ؛‚إ‹©‚ٌ‚¾پBƒ~پ[‚حˆêڈuƒ`ƒ‰ƒb‚ئگU‚è•ش‚ء‚ؤپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚ًŒ©‚½‚ھ–”‚·‚®Œ©‚¦‚ب‚‚ب‚ء‚½پBپuƒ~پ[پAƒ~پ[پIپBپvپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‹ك‚‚ج‰ئ‚جٹ_چھ‚ً‰z‚¦‚½‚èپA‚ ‚؟‚±‚؟‚ً‘{‚µ‚ـ‚ي‚ء‚½‚ھپA‚ئ‚¤‚ئ‚¤Œ©ژ¸‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@
پ@‚â‚ھ‚ؤپAƒ~ƒP‚حپA–é‚ة‚ب‚ء‚ؤ’‰—ى“ƒ‚ً–عˆَ‚ة‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚ا‚¤‚ة‚©Œ³‚ج‰ئ‚ة–ك‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚ھپA‚à‚¤‚±‚ج‰ئ‚ح‰َ‚³‚ê‚é’¼‘O‚إ‚ ‚èپA’N‚à‹ڈ‚ب‚©‚ء‚½پB‰ئ‚جژü‚è‚ًپAƒOƒ‹ƒOƒ‹‚ئپA‰½‰ٌ‚à‰ô‚è‚ب‚ھ‚çپAپuƒjƒƒپ[پ[ƒ“پBپvپ@پuƒjƒƒپ[پ[ƒ“پBپvپ@‰½“x‚à‰½“x‚àپAژهگl‚ًŒؤ‚ٌ‚إپA’†‚ج‹C”z‚ً‚¤‚©‚ھ‚ء‚½‚ھپA‰ئ‚ج’†‚حگ^‚ءˆأˆإ‚إپAگl‰e‚à‚ب‚پAƒVپ[ƒ“‚ئگأ‚ـ‚è‚©‚¦‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپuƒjƒƒپ[ƒIƒ“پBپvپ@پuƒjƒƒپ[پ[ƒIƒ“پcپBپv
پ@
پ@ƒ~ƒP‚حپAˆہ‚炬‚ج‰ئ‚ھˆأˆإ‚جگ¢ٹE‚ة‘م‚ي‚ء‚½‚±‚ئ‚ً’m‚ء‚½پB‚»‚ê‚إ‚àپAژهگl‚ج‰e‚ً‹پ‚ك‚ؤپAŒؤ‚ر‘±‚¯‚½پBپ@ƒ~ƒP‚حپA‰½‚ج”½‰‚à‚ب‚¢ˆإ‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ–آ‚«‹©‚ٌ‚إ‚à‹•‚µ‚¢‚خ‚©‚è‚إپA‚·‚ء‚©‚è–آ‚«”و‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پBپiژهگl‚ح‚à‚¤‚±‚±‚ة‚ح‹ڈ‚ب‚¢‚ٌ‚¾پcپBپjپ@ƒ~ƒP‚حژd•û‚ب‚پAکA‚ê‚ؤچs‚©‚ê‚ؤ‚·‚®“¦‚°ڈo‚µ‚½پA‚ ‚جˆس’nˆ«‚ب”L‚ج‹ڈ‚é•|‚¢ڈêڈٹ‚ة–ك‚邵‚©‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@‚»‚ج‚±‚ëپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚àپA“¦‚°‚½ƒ~ƒP‚ً‚ ‚؟‚±‚؟‘{‚µ‚ـ‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚ظ‚ئ‚ظ‚ئ‚ةپA”و‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢پA‚ ‚«‚ç‚ك‚ؤ–ك‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚¨گ¢کb‚ة‚ب‚éژ–‚ة‚ب‚ء‚½پA‰¼‚ج‰ئ‚ج“ٌٹK‚إپAƒ[ƒ“‚ة•z’c‚ً•~‚¢‚ؤ–ل‚ء‚ؤپA‚µ‚خ‚炉،‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپA–é’†‚ةƒ~ƒP‚ج‹©‚ش‚و‚¤‚ب–آ‚«گ؛‚ً•·‚‚ئپAپu‚ ‚ءپAƒ~ƒP‚ھ–آ‚¢‚ؤ‚¢‚éپBƒ~پ[پIپBپv
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپAپuƒKƒoƒbپIپv‚ئ•z’c‚©‚ç‹N‚«ڈo‚µ‚ؤپA‚·‚®ٹO‚ةڈo‚ؤ‘{‚µ‰ô‚ء‚½پBپuƒ~پ[پIپBƒ~پ[پIپBپvپ@‰½ڈˆ‚©—£‚ꂽڈٹ‚©‚ç–آ‚¢‚ؤپA‚±‚؟‚ç‚ً‚¤‚©‚ھ‚¤ƒ~ƒP‚ج–ع‚ھŒُ‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپAˆأˆإ‚ج’†‚ة–ع‚ًŒُ‚点‚ؤ‹ƒ‚ƒ~ƒP‚ةپA‚¢‚肱‚ج‚²”ر‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚ؤ‚ ‚°‚و‚¤‚ئ‚µ‚½پBپ@پuƒ~پ[پAƒ~پ[پBپvپ@ٹm‚©‚ةژهگl‚جŒؤ‚شگ؛‚ھ•·‚±‚¦‚ؤ‚¢‚锤‚ب‚ج‚ةپAƒ~ƒP‚ح‹°‚ê‚ؤŒˆ‚µ‚ؤ‹كٹٌ‚ء‚ؤ—ˆ‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@پuپu‚ـ‚±‚ئپvپA”L‚حگl‚ة‚حپA‚ب‚آ‚©‚ٌ‚إپA‰ئ‚ة’…‚‚ئ‚خ‚¢پB”L‚جڈKگ«‚حˆ£‚ê‚©‚ئ‚خپ[‚¢پcپBپvگS”z‚µ‚ؤŒم‚ë‚ة•t‚¢‚ؤ—ˆ‚ؤ‚¢‚½ƒ[ƒ“‚ھ‚آ‚ش‚â‚¢‚½پBپ@ƒ~ƒP‚ح‚±‚ج“ْپA‚ئ‚¤‚ئ‚¤‰ئ‚ج’†‚ة‚ح“ü‚ء‚ؤ—ˆ‚ب‚©‚ء‚½پBپ@ژهگl‚ھˆع‚ء‚½‰ئ‚حپAٹù‚ة•ت‚جژ”‚¢”L‚ج“ê’£‚è‚إ‚ ‚èپAپuŒ–‰ـ‚ة•‰‚¯‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½ƒ~ƒP‚حپAŒˆ‚µ‚ؤ‚à‚¤“ٌ“x‚ئپA‚»‚ج“y’n‚ة“ü‚ء‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پBپv‚ئ‚¢‚¤پA”L‚جگ¢ٹE‚جŒµ‚µ‚¢|‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@
|
|
|
 |
|
|
پ@—‚“ْپA‰ئ‚ح‰َ‚³‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پB’Œ‚ةƒqƒ‚‚ً‚©‚¯‚ؤ‘هگ¨‚إˆّ‚ء‚د‚é‚ئپAڑ؛‚ً‚½‚ؤ‚ب‚ھ‚çپAƒKƒ‰ƒKƒ‰‚ئپAٹ¢‚â•ا‚ھ•ِ‚ê—ژ‚؟پA‚·‚ء‚©‚èپAٹ¢âI‚جŒإ‚ـ‚è‚ة‚ب‚ء‚½پB‚½‚؟‚ـ‚؟پA”pچق‚ھ•ذ•t‚¯‚ç‚ê‚ؤپA‰½‚à‚ب‚¢”pڑذ‚ة‚ب‚ء‚½پBگl’m‚ꂸپAƒ~ƒP‚ح“ئ‚è‚ع‚ء‚؟‚إپA’‰—ى“ƒ‚ج‚س‚à‚ئ‚©‚çپA‚»‚ج—lژq‚ً‹ء‚¢‚ؤŒ©‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
پ@‚â‚ھ‚ؤƒ~ƒP‚حپA‹ح‚©‚بٹ¢âI‚ھژc‚ء‚½‹َ‚«’n‚ة‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB‰½‚à–³‚‚ب‚ء‚½‰ئ‚جگص‚ًپA‚³‚ـ‚و‚¢•à‚«‚ب‚ھ‚çپAپuƒjƒƒپ[ƒIƒ“پBپvپ@پuƒjƒƒپ[ƒIƒ“پBپv‚ئپAگSچׂ‚ب‚ء‚ؤ–آ‚¢‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚جژپA•ê‚جƒ`ƒJ‚حپAٹ¢âI‚جگص’n‚ً‚³‚ـ‚و‚¤ƒ~ƒP‚ًŒ©‚آ‚¯‚ؤپA‰½“x‚à‰¼ڈZ‚ـ‚¢‚ج‰ئ‚ج‚ظ‚¤‚ةکA‚ê–ك‚»‚¤‚ئ‚µ‚½‚ھپA‰¼ڈZ‚ـ‚¢‚ج‰ئ‚ج‹ك‚‚ـ‚إ‚‚é‚ئپA‚¢‚¶‚ك‚é”L‚ج‹C”z‚ًٹ´‚¶‚½‚ج‚©پAŒƒ‚µ‚–\‚ê‚ؤƒ`ƒJ‚ًˆّ‚ء‘~‚«پA‚·‚®‚¢‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚¾‚ء‚½پB
پ@
پ@‚±‚¤‚µ‚ؤپAپuˆہ‚炬‚ج‰ئپv‚ًژ¸‚ء‚½ƒ~ƒP‚حپA‰½“ْ‚à–ى—ا”L‚ة‚ب‚ء‚ؤپA’‰—ى“ƒ‚ج‰؛‚ج–÷‚ج’†‚âچr‚ê–ى‚ً‚³‚ـ‚و‚¢‘±‚¯‚½پB‰ئ‚ئژهگl‚ھپA•ھ—ô‚µ‚½‚Q‚آ‚ج‰ئ‚جٹش‚ًپA‰½“x‚à‰½“x‚àچs‚ء‚½‚è—ˆ‚½‚肵‚ؤ‚¢‚½پB‚ا‚؟‚ç‚ةچs‚ء‚ؤ‚àپAƒ~ƒP‚جˆہ‚ç‚®‹َٹش‚ح–³‚©‚ء‚½پB”و‚ê‰ت‚ؤپAچs‚«ڈê‚ًژ¸‚ء‚½ƒ~ƒP‚حپA‹¯‚¦‚ب‚ھ‚çپA‚ـ–é’†‚ج“¹‚ً‚¨• ‚ً‚·‚©‚µ‚ؤپuƒjƒƒپ[ƒIƒ“پBƒjƒƒپ[ƒIپ[ƒ“پIپBپv‚ئپA‰½“x‚à–آ‚«‚ب‚ھ‚çپA‚¢‚آ‚©ژهگl‚ئˆêڈڈ‚ةڈZ‚ك‚éپuˆہڈZ‚ج‰ئپv‚ً•Kژ€‚ة‘{‚µ‹پ‚ك‚ؤ‚³‚ـ‚و‚ء‚½پB
پ@
پ@‚â‚ھ‚ؤپA‰َ‚µ‚½ٹ¢âI‚ج’†‚©‚çپAٹî‘b‚جگخ‚ئ’Œ‚ھ—§‚ؤ‚ç‚êپAڈ‚µ‚¸‚آپAگV‚µ‚¢‰ئ‚جŒ´Œ`‚ھŒ»‚ي‚ê‚ؤ—ˆ‚½پBپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA—c’t‰€‚©‚ç‹A‚ء‚ؤ‚‚邽‚ر‚ةپA—ׂج‰ئ‚ج‘O‚ةچہ‚ء‚ؤپA‰ئ‚ھڈo—ˆ‚ ‚ھ‚é—lژq‚ًŒ©‚ ‚°‚ؤ‚¢‚½پB
پ@— ‚ة‰ô‚é‚ئپAŒZ‚جپ@‚ج‚肨‚ھپA•ا“h‚è‚جچ¶ٹ¯‚³‚ٌ‚جژè“`‚¢‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½پB•ا‚ج’|‚جٹiژq‚ةکm‚ًٹھ‚«•t‚¯‚ؤ•ز‚ٌ‚¾‚èپA‚»‚جڈم‚ة“h‚éگش“y‚ً‘«‚إ‚±‚ثپAچڈ‚ٌ‚¾کm‚ً’†‚ةƒpƒ‰ƒpƒ‰‚ئ“ü‚ê‚ؤپA‘«‚إ‰½“x‚à“¥‚ٌ‚إ‚حچ¬‚؛چ‡‚ي‚¹‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
پ@‚»‚ج‚±‚ëپA‰ئ‚ھڈ‚µ‚¸‚آڈo—ˆ‚ ‚ھ‚é—lژq‚ًپA–ى—ا”L‚ة‚ب‚ء‚½ƒ~ƒP‚àپA’‰—ى“ƒ‚ج‹u‚ج‚س‚à‚ئ‚ج‘گ–÷‚ج’†‚©‚ç‚¢‚آ‚àŒ©‚ة—ˆ‚ؤ‚¢‚½پBپ@ƒ~ƒP‚جپAŒ©‚½‚±‚ئ‚à–³‚¢ٹç‚ج‘هچH‚³‚ٌ‚ھپAپuƒRƒ“پAƒRƒ“پIپBپv‚ئپA“B‚ً‘إ‚ء‚ؤ–Z‚µ‚“‚¢‚ؤ‚¢‚½پB
پ@ژپXپAƒ`ƒJ‚جژp‚ھŒ©‚¦‚½پBƒ~ƒP‚حپAƒ`ƒJ‚جٹç‚ًŒ©‚آ‚¯‚é‚ئپA‰½‚ئ‚ب‚ٹَ–]‚ًژ‚آ‚±‚ئ‚ھڈo—ˆ‚½پBپi‚à‚¤ڈ‚µ‰ن–‚µ‚½‚çپA‚¢‚آ‚©‚«‚ء‚ئ‹A‚ê‚é‚ٌ‚¾پcپBپjپ@‚¨• ‚ً‚·‚©‚¹‚½ƒ~ƒP‚حپAپuƒjƒƒپ[پ[ƒ“پIپBپv‚ئˆêگ؛–آ‚¢‚ؤپA‚ـ‚½‘گ‚ق‚ç‚ةڈZ‚ق–ى‘l‚ً’T‚µ‚ةپA–÷‚ةڈء‚¦‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@
پ@‚â‚ھ‚ؤپAگV‚µ‚¢’Œ‚جچœ‘g‚ف‚ھڈo—ˆ‚ ‚ھ‚èپA“ڈڈم‚°‚ج–ف‚ھپA‰®چھ‚جڈم‚©‚çژl•û‚ة‚ـ‚©‚ꂽپBپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‹كڈٹ‚جگl‚ھڈW‚ـ‚ء‚ؤپA–ف‚ًڈE‚¤ژp‚ًپA•sژv‹c‚»‚¤‚ةŒ©‚ؤ‚¢‚½پBپ@پ@‚±‚¤‚µ‚ؤ”¼”NŒمپAگV‚µ‚¢‰ئ‚ھ–³ژ–‚ةٹ®گ¬‚µ‚½پB‰ئ‘°‚ج‚ف‚ٌ‚ب‚حچؤ‚ر–ك‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB
پ@
پ@•ذ•t‚¯‚àپA‚ا‚¤‚ة‚©ڈI‚ي‚èپA“ٌٹK‚إƒ[ƒ“‚ئƒcƒgƒ€ڈf•ê‚³‚ٌ‚ھپA‚ئ‚±‚ج‚ـ‚ج‰،‚جپA‰ں“ü‚ê‚ج‘O‚إپA•ذ•t‚¯‚µ‚ب‚ھ‚çپA‰½‚©کb‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚àپA‚Qگl‚ج—lژq‚ًŒم‚ë‚إŒ©‚ؤ‚¢‚½ژپAƒgƒ“ƒgƒ“‚ئٹK’i‚ًڈم‚ھ‚ء‚ؤ—ˆ‚éپA‚©‚·‚©‚بگ¶‚«•¨‚ج‹C”z‚ھ‚µ‚½پBپuƒjƒƒپ[پ[ƒ“پIپBپv
پ@
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚©‚·‚©‚ب‹ƒ‚«گ؛‚ً•·‚«پAٹK’i‚ج•û‚ةٹç‚ًگL‚خ‚µ‚½پBٹK’i‚جڈم‚ج’Œ‚©‚ç‚»‚ء‚ئ‰؛‚ًŒ©‚é‚ئپA‚¢‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½ƒ~ƒP‚ھپAژü‚è‚ًŒx‰ْ‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚¨‚»‚邨‚»‚éپAٹK’i‚ً‚ ‚ھ‚낤‚ئ‚·‚éژp‚ھŒ©‚¦‚½پBپu‚ ‚ءپAپIپBپvپ@ƒ~ƒP‚ح‹ء‚¢‚ؤ–ع‚ً‘ه‚«‚Œ©ٹJ‚¢‚ؤ‚±‚؟‚ç‚ًŒ©‚½پBپ@پu‚ ‚ءپAƒ~پ[‚¾پBƒ~پ[‚ھ‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚½پIپBپvپuپcپHپBپvپu‚¨‚¢‚إپAƒ~پ[پA‚¨‚¢‚إپBپvپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚ح‚µ‚ل‚¬‚ب‚ھ‚çپAƒ~پ[‚ج–¼‘O‚ًˆêگ¶Œœ–½‚ةŒؤ‚ٌ‚¾پB‚»‚جگ؛‚ً•·‚¢‚ؤƒ~ƒP‚ح‹}‚¢‚إ‚ ‚ھ‚ء‚ؤ‚«‚½پB
پ@
پ@پuƒjƒƒپ[ƒIپ[ƒ“پBپvپ@ƒ~ƒP‚حپA‚·‚ء‚©‚è–ر•ہ‚ف‚ھ‰ک‚ê‚ؤپA‘‰‚¹‚±‚¯‚ؤ‚حپA‚¢‚½‚ھپA‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©–ى—ا”Lژ‘م‚ج‹êکJ‚ًڈd‚ث‚ؤپA‹‚ç—‚µ‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پBگV‚µ‚¢ڈô‚جڈL‚¢‚ًڑk‚¬‚ب‚ھ‚çپAژü‚è‚ج—lژq‚ًژf‚¢‚ب‚ھ‚çپA‚¨‚»‚邨‚»‚éپA‹كٹٌ‚ء‚ؤ—ˆ‚½پBپ@Œ³‚¢‚½ڈêڈٹ‚ةپAچؤ‚رپAژهگl‚½‚؟‚ج“¯‚¶ٹç‚ش‚ê‚ًٹm”F‚·‚é‚ئپA‚â‚ء‚ئˆہگS‚µ‚½‚و‚¤‚ةپuƒSƒچƒSƒچپv‚ئچA‚ً–آ‚炵‚ؤپAƒ[ƒ“‚ج•G‚ة‰½“x‚à“ھ‚ً‚±‚·‚è‚آ‚¯پAژC‚èٹٌ‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB
پ@
|
|
|
 |
|
|
پ@پu‚¨پ[پA‚و‚µ‚و‚µپA‚و‚¤‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚ثپBپvپ@ƒ[ƒ“‚àپAٹً‚µ‚»‚¤‚ةƒ~ƒP‚ً•ّ‚¢‚ؤپA•ڈ‚إ‚ؤ‚ ‚°‚½پBƒ~ƒP‚ج‘ج‚حپA‚ ‚خ‚çچœ‚ھŒ©‚¦‚é‚ظ‚اپAƒKƒٹƒKƒٹ‚ة‘‰‚¹‚±‚¯‚ؤŒy‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپu‚±‚ç‚ پcپA‚¸پ[‚ئ‰½‚àگH‚ׂئ‚ç‚ٌ‚خ‚¢پBپvپ@ƒ[ƒ“‚ح‹}‚¢‚إپA‚¢‚肱“ü‚è‚جٹں‚ج‚²”ر‚ًچى‚ء‚ؤ‚ ‚°‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚±‚جژپA‘Sگg‚إ”ٍ‚رڈم‚ھ‚é‚ظ‚اٹً‚µ‚‚ؤپA‚½‚ـ‚ç‚ب‚¢ٹى‚ر‚ًٹ´‚¶‚ؤ‚¢‚½پBپ@‚»‚جŒمپAƒ~ƒP‚حپAگV‚µ‚¢‰ئ‚ة‚àٹµ‚ê‚ؤپA‚½‚‚³‚ٌ‚جژq‹ں‚ًگ¶‚ٌ‚إپAژq‘·‚ً‘‚₵‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@
پ@
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–°‚ê‚éچ°پB
پ@‚±‚¤‚µ‚ؤپA‚ا‚¤‚ة‚©پA‰ئ‚حٹ®گ¬‚µ‚½پB‚¾‚ھ”’•ا‚ً“h‚ç‚ب‚¢گش“y‚ً“h‚ء‚½‚¾‚¯‚ج•ا‚حپAگG‚é‚ئ‚·‚®ƒUƒ‰ƒUƒ‰‚ئ‰؛‚ة—ژ‚؟‚é—L‚è—l‚¾‚ء‚½پB‚·‚ׂؤ‚ج•”‰®‚ةڈô‚ً•~‚—]—T‚à–³‚پA‘م‚ي‚è‚ةگV•·ژ†‚ً•~‚¢‚½پBƒ`ƒJ‚ة‚حˆس’n‚ھ‚ ‚ء‚½پB‚«‚؟‚ٌ‚ئژط‹à‚ً•شچد‚·‚é‚ـ‚إ‚حپAوز‘ٍ‚حڈo—ˆ‚ب‚©‚ء‚½پB‚µ‚خ‚ç‚گH”ï‚àگط‚è‚آ‚كپA‚½‚‚ي‚ٌ‚ةپA‚²”ر‚ئ‚¢‚¤پA‚آ‚ـ‚µ‚¢گ¶ٹˆ‚ھ‘±‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB
پ@‚±‚ٌ‚بڈَ‘ش‚إپA‚â‚ء‚ئ‚جژv‚¢‚إ–³—‚µ‚ب‚ھ‚ç‰ئ‚ًŒڑ‚ؤ’¼‚µ‚½‚ج‚إپA— ‚ة•¨’uڈ¬‰®‚ًŒڑ‚ؤ‚é—]—T‚ب‚ا‘S‚‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@Œأ‚¢‰ئ‚جژ‚ة‚حپA‚©‚³‚خ‚éپué\“ھ‚ًچى‚铹‹ïپv‚حپA“ٌٹK‚ج•”‰®‚ة’u‚¢‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚¢‚´گV’z‚µ‚ؤ‚ف‚é‚ئپA‚»‚ê‚ً’u‚ڈêڈٹ‚ھŒ©‚آ‚©‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپi‚à‚¤é\“ھ‰®‚ًژ«‚ك‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ج‚¾‚©‚çپA“ٌ“x‚ئژg‚¤‚±‚ئ‚ح‚ب‚¢‚¾‚낤پcپBڈêڈٹ‚خ‚©‚è‚ئ‚ء‚ؤ‚©‚³‚خ‚é‚ج‚إژ×–‚‚ة‚ب‚邾‚¯‚¾پcپBپj‚ئژv‚ء‚½پBپu‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌپA‚±‚ج“¹‹ïپA‚à‚¤ژg‚ي‚ب‚¢‚ٌ‚ب‚çپAŒ —ک‚ًڈ÷‚ء‚½“X‚ة‚ ‚°‚½‚ç‚ا‚¤‚إ‚·‚©پHپBپvپu‚¢‚âپA–ꂳ‚ٌ‚ھ‘هژ–‚ةژg‚ء‚ؤ‚«‚½“¹‹ï‚â‚©‚çپAژج‚ؤ‚½‚ç‚¢‚©‚ٌ‚خ‚¢پIپBپvپ@ƒ[ƒ“‚ح‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚àژج‚ؤگط‚ê‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@ƒ`ƒJ‚حپAŒئ‚جŒ¾‚¤’ت‚è‚ة‚·‚邵‚©‚ب‚©‚ء‚½پB‚¾‚ھ‰½ڈˆ‚ة‚à’u‚«ڈêڈٹ‚ھŒ©‚آ‚©‚ç‚ب‚‚ؤپAژd•û‚ب‚ƒWƒپƒWƒپ‚µ‚½ڈ°‰؛‚ة“ü‚ê‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB
پ@ƒ`ƒJ‚حپA‚ج‚肨‚ةپAé\“ھ‚ج“¹‹ï‚ًڈ°‚ج‰؛‚ة‰^‚ش‚و‚¤‚ةŒ¾‚¢‚آ‚¯‚½پB‚ج‚肨‚حپA•ê‚جŒ¾‚¢‚آ‚¯‚ا‚¨‚è‚ةپA‚»‚ê‚ç‚ً•ْ‚肱‚ق‚و‚¤‚ة‰ں‚µچ‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@
پ@‚±‚¤‚µ‚ؤپAچ،ˆن‰ئ‚ج‰ئ•َ‚حپA‚»‚ج‚ـ‚ـڑ؛‚ً‚©‚ش‚ء‚½ڈَ‘ش‚إپA‰½”N‚àپA–³‘¢‚³‚ة’u‚©‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پBپ@ƒWƒپƒWƒپ‚µ‚½ڈ°‰؛‚ة’u‚¢‚½‚ج‚إپA‚½‚؟‚ـ‚؟•…گI‚ھژn‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB‹C‚ھ•t‚‚ئچH‹ï” ‚ة“ü‚ê‚ؤ‚¢‚½é\“ھ‚ة‰ں‚·ڈؤ‚«‚¢‚ٌ‚ب‚ا‚àپA‚·‚ء‚©‚èژK‚ر‚ئڑ؛‚ة‚ـ‚ف‚ê‚ؤ‚¢‚½پBپ@
پ@
پ@‚»‚ٌ‚ب’†‚إپA‰ئ‘°‚âژq‹ں‚½‚؟‚حپAڈ°‰؛‚ة–°‚铹‹ï‚ھ‰½‚ًˆس–،‚·‚é‚ج‚©پA‘S‚‹C‚ھ•t‚©‚ب‚¢‚ـ‚ـ•é‚炵‚ؤ‚¢‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚حپA‚±‚جپu–°‚ê‚铹‹ïپv‚ھپAڈêڈٹ‚خ‚©‚èژو‚éپAژ×–‚‚إ–ً‚ة—§‚½‚ب‚¢ƒKƒ‰ƒNƒ^‚ة‚µ‚©Œ©‚¦‚ب‚©‚ء‚½پBپi‚ا‚¤‚¹پA“ٌ“x‚ئژg‚¤‚±‚ئ‚ح‚ب‚¢‚ج‚¾پcپBپj‚ئپAژv‚¢‚ب‚ھ‚çپA–Y‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¨‚¤‚ئ‚µ‚½پB
پ@‚±‚جژ‚©‚çپA‚±‚جپA–°‚ê‚éڈ°‰؛‚ج“¹‹ï‚ةپA‚ئ‚è‚آ‚¢‚½‰…”O‚ھپAگأ‚©‚ة“®‚«ڈo‚µژn‚ك‚½پBپ@‚ ‚éٹ¦‚¢“~‚ج“ْپA––‚ءژq‚جپu‚ـ‚±‚ئپv‚جڈم‚ةپAژv‚¢‚ھ‚¯‚ب‚¢ن…“ï‚ھڈP‚ء‚ؤ—ˆ‚½پBپ@‚±‚جژ–Œج‚حپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚ج–½‚ً’D‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚©‚ةŒ©‚¦‚½پB‚¾‚ھپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA”]‚ة‘ه‚«‚بƒ_ƒپپ[ƒW‚ًژَ‚¯‚½‚ھپAگl’m‚ꂸڈلٹQ‚ًژc‚µ‚½‚ـ‚ـپAٹïگص“I‚ةڈ•‚©‚ء‚½پB
پ@‚±‚¤‚µ‚ؤپAچ،ˆن‰ئ‚ة‚ئ‚è‚آ‚¢‚½‰…”O‚حپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚جچ°‚àپA••ˆَ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤ژ–Œڈ‚ً‹N‚±‚·‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پBپ@‚»‚جŒم‚àپAژô‚ي‚ꂽ‰ئ‚ج‚و‚¤‚ةپAژü‚è‚©‚çژںپX‚ئپAژژ—û‚ھڈP‚ء‚ؤ—ˆ‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚é‚ھپAƒ`ƒJ‚حپA‚»‚جŒ´ˆِ‚ئˆس–،‚ة‹C‚ھ•t‚—]—T‚ب‚ا–³‚پA‰ئ‚ج•شچد‹à‚ئپAگ¶ٹˆ‹ê‚ئ‚ج“¬‚¢‚ة–¾‚¯•é‚ê‚é‚ج‚ھپAگ¸ˆê”t‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ@
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’D‚¤—×گlپB
پ@چ،ˆن‰ئ‚ج‚·‚®ژخ‚ك‘O‚ة‚حپAŒ¢چD‚«‚جکV•v•w‚ھ‰c‚قژG‰ف‰®‚ج“X‚ھ‚ ‚ء‚½پBپ@‚¾‚ھ•sژv‹c‚ئپA‚»‚ج“X‚إ”ƒ‚¢•¨‚ً‚·‚é•ê‚جژp‚ًپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚ح‚P“x‚àŒ©‚½‚±‚ئ‚ھ‚ب‚©‚ء‚½پBپ@‚ا‚ٌ‚ب‚ة‹}‚¬‚جژ‚إ‚àپA‚ي‚´‚ي‚´‰“‚¢“X‚ج‚ظ‚¤‚ة•à‚¢‚ؤ‚¢‚ء‚½پB”ƒ‚¢•¨‚©‚ç‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‘نڈٹ‚ـ‚إ—ˆ‚½ژپAپu‚ ‚ءپA‚µ‚à‚¤‚½پA‚ ‚ꔃ‚¤‚ج–Y‚ꂽپIپBپv‚ئŒ¾‚¤‚ئ‚·‚®‚ـ‚½ˆّ‚«•ش‚µ‚½پB
پ@
پ@پi‹ك‚‚إ”ƒ‚¦‚خ‚¢‚¢‚ج‚ةپcپBپj‚ئپA•پ’i‚©‚çژv‚ء‚ؤ‚¢‚½پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‘‹‚©‚猩‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚â‚ح‚è‘O‚ة‚ ‚é“X‚ًƒ`ƒ‰ƒb‚ئˆê•ث‚µ‚½‚ـ‚ـپA‰“‚¢‚ظ‚¤‚ج“X‚ة‹}‚¬‘«‚إ–ك‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پBپ@‚µ‚خ‚ç‚‚½‚ء‚ؤپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA•sژv‹c‚ةژv‚ء‚ؤپA‚»‚ج——R‚ً•ê‚ة•·‚¢‚ؤŒ©‚½پB‚·‚é‚ئƒ`ƒJ‚حپAٹُ‚ـ‚ي‚µ‚¢‰ك‹ژ‚ًژv‚¢ڈo‚µ‚½‚ج‚©پA‹}‚ة“{‚ء‚½‚و‚¤‚ةŒ¾‚ء‚½پBپu‚»‚±‚ج“X‚ح‰ک‚©‚ئ‚وپ[پBپvپu‚¦‚ءپHپA‚ب‚ٌ‚إپ[
پcپHپBپvپu‚¤پ[‚ٌپcپBپvƒ`ƒJ‚حپAکb‚µ‚ؤ‚¢‚¢‚©‚ا‚¤‚©پA‚؟‚ه‚ء‚ئ‚µ‚خ‚ç‚پA‚½‚ك‚ç‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپAˆس‚ًŒˆ‚µ‚½‚و‚¤‚ةکb‚µڈo‚µ‚½پB
پ@
پ@پuˆب‘O‚ح‚ثپA‹ك‚‚ؤ•ض—ک‚¾‚©‚çپA‚و‚”ƒ‚¢•¨‚ً‚µ‚ؤپA’ –ت‚ة•t‚¯‚ؤ–ل‚ء‚ؤ‚½‚ئ‚وپBپvپu‚¤پ[‚ٌپcپBپvپu‚خ‚ء‚ؤ‚ٌپA‚ ‚éژپAŒژ––‚ةژx•¥‚¢‚ةچs‚ء‚½‚çپA”ƒ‚ء‚½ٹo‚¦‚ج–³‚¢‚à‚ج‚ھپA’ –ت‚ة‚¢‚ء‚د‚¢•t‚¯‚ç‚ê‚ؤپA‚¦‚ç‚¢چ‚‚¢‹àٹz‚ًگ؟‹پ‚³‚ꂽ‚¯‚ٌ‚ثپA‚¤‚؟‚ح‚»‚ٌ‚ب•sگ³‚ھپAگâ‘خپA‹–‚¹‚ٌ‚â‚ء‚½‚¯‚ٌپA‚»‚جژ‚ةپA“X‚جگl‚ئپA‚¨‚¨ƒQƒ“ƒJ‚µ‚½‚ئ‚وپcپBپvپ@ƒ`ƒJ‚حپA‚»‚جژ‚جگ¬‚èچs‚«‚ًڈع‚µ‚کb‚µ‚½پBپ@ƒ`ƒJ‚حپAˆêƒ–Œژ‘O‚ةژ©•ھ‚ج”ƒ‚ء‚½•¨‚ھ‰½‚إ‚ ‚ء‚½‚©پA–Y‚ê‚锤‚ح–³‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@پu‚¨‚©‚µ‚©‚إ‚·‚ثپB‚±‚ٌ‚ب‚à‚ج”ƒ‚ء‚½ٹo‚¦‚ح‚ب‚¢‚إ‚·‚وپBپv‚ئپAژw“E‚µ‚ؤ‚àپA“X‚جگl‚حپAپu“ْ‚ة‚؟‚ھ‰ك‚¬‚ئ‚é‚©‚çپAژ©•ھ‚إ”ƒ‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½‚ج‚ة–Y‚ê‚ئ‚ç‚ء‚µ‚ل‚é‚ئ‚â‚ëپcپBپv‚ئپA‚¢‚¢‰ءŒ¸‚ب‚±‚ئ‚ًŒ¾‚¢’ت‚µ‚ؤپAگâ‘خ‚ة’ –ت‚ج‹Lچع‚ًŒë–‚‰»‚µ‚½‚±‚ئ‚ً”F‚ك‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@ˆêŒ©پA•¨گأ‚©‚إ—D‚µ‚Œ©‚¦‚éƒ`ƒJ‚حپAˆ«ˆس‚ًژ‚ء‚½گl‚ھ‰½‚©•t‚¯‚¢‚낤‚ئ‚µ‚½ژ‚ة‚حپA‰¸‚â‚©‚ةپA‚³‚è‹C–³‚’چˆس‚µ‚½پB‚»‚ê‚إ‚à‘ٹژè‚ھ‘S‚ژس‚ç‚ب‚¢‚إ‹ڈ’¼‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ئپAگâ‘خ‚ة‹–‚¹‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚¾‚ء‚½پB‘د‚¦‚ؤ‚¢‚½ٹ¬”E‘ـ‚ج•R‚ھگط‚ꂽڈuٹشپA”é‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½Œƒ‚µ‚¢گ«ٹi‚إ“O’ê“I‚ةچR‹c‚·‚é‚ج‚¾‚ء‚½پBƒ`ƒJ‚ً‚ب‚ك‚ؤ‚©‚©‚ء‚½گl‚حپA‚»‚ج‚ ‚ـ‚è‚جŒƒ‚µ‚¢”½Œ‚‚ة–تگH‚ç‚ء‚ؤپA‰½‚àŒ¾‚¦‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@‚»‚ê‚©‚ç‚ئ‚¢‚¤‚à‚جپA•ê‚ح‚ا‚ٌ‚بژ–‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚à‚»‚ج“X‚إˆêگط”ƒ‚¢•¨‚ً‚µ‚ب‚‚ب‚ء‚½پBپ@Œ–‰ـ‚µ‚ؤ‚©‚çپA‚»‚ج“X‚جگl‚àپA‚¢‚آ‚à‚ي‚´‚ي‚´‰“‚‚ج“X‚ة”ƒ‚¢•¨‚ً‚µ‚ؤ‰ئ‚ة‹A‚ء‚ؤ‚‚éپAƒ`ƒJ‚ج‹B‘R‚ئ‚µ‚½ژp‚ًŒ©‚é“x‚ةپA‰ü‚ك‚ؤژ©•ھ‚ج‚µ‚½چsˆ×‚ً’p‚¶‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@ژس‚é‹@‰ï‚ً–³‚‚µ‚½‚ـ‚ـپA‰i‚¢ٹش—âگيڈَ‘ش‚ھ‘±‚¢‚ؤ‚¢‚½پBپiƒ`ƒJ‚³‚ٌ‚ةڈ‚¢‚ً‚·‚éژ‚ھ‚¢‚آ‚©—ˆ‚ب‚¢‚¾‚낤‚©پcپHپBپj‚ئ‚¢‚¤گ\‚µ–َ‚ب‚¢‹Cژ‚؟‚ة‚ب‚èپAƒKƒ‰ƒX‰z‚µ‚ةŒ©‚ؤ‚¢‚½پBپ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚ح‚»‚جژپA•ê‚ج’†‚ةپiˆê“xŒˆ‚ك‚½‚çپA‚½‚ئ‚¦‚ا‚ٌ‚ب‚ة•s•ض‚ب‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚àٹر‚«’ت‚·پBپjگl•ہ‚فٹO‚ꂽ‹‚¢ˆسژu‚ئپA•s‹ü‚جˆس’n‚ھ‰B‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ًٹ´‚¶ژو‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
پ@
پ@
پ@پ@پ@گأ‚©‚بگ¶‚«•¨پB
پ@پuٹO•ضڈٹپv‚ج‘‹‚جŒ„ٹش‚©‚çپA‰¹‚à—§‚ؤ‚¸‚ةگN“ü‚·‚éگ¶‚«•¨‚ھ‚¢‚½پB‘ه‚ج•”‰®‚ةگأ‚©‚ة‰؛‚肽پB”–ˆأ‚¢”آ’£‚è‚ج‰؛‚ً”`‚‚ئپA‹ڈگS’n‚ج—ا‚³‚»‚¤‚ب‹َٹش‚ًŒ©‚آ‚¯‚ؤپAƒXƒ‹ƒXƒ‹‚ئ‚·‚ׂé‚و‚¤‚ةچ~‚肽پB•ضٹي‚جƒJƒپ‚ج‰،‚ج‚ذ‚ٌ‚â‚肵‚½’n–ت‚ة‘ج‚ً‹x‚ك‚½پB
پ@‚±‚ê‚حپA‚ـ‚¾پu‰ن‚ھ‰ئپv‚ج— ’ë‚ةپuٹO•ضڈٹپv‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA‰ئ‘°‚ج‚ف‚ٌ‚ب‚ھپAŒC‚ً—ڑ‚¢‚½‚ـ‚ـپAژg‚ء‚ؤ‚¢‚½چ ‚جکb‚إ‚ ‚éپB‚ ‚é“ْپA•ê‚ھپA‘c•ê‚جƒ[ƒ“‚ةپA‰½‚â‚çڈ¬گ؛‚إکb‚©‚¯‚ؤ‘ٹ’k‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپu‚ب‚ٌ‚¾‚낤پHپBپv‚ئ‹°‚é‹°‚é‹ك‚أ‚¢‚ؤپA—ׂج‰¦‚ج‰A‚©‚çپA‚»‚¨پ[‚ء‚ئ•·‚¢‚ؤ‚ف‚½پB
پ@پu‚ ‚çپ[پA‚»‚¤‚بپA‚»‚ç‚ پAژq‹ں’B‚ھ‘هژ–‚بڈٹ‚ًٹڑ‚ـ‚ê‚إ‚à‚µ‚½‚çپA‚¨‚¨‚²‚ئ‚ة‚ب‚é‚خ‚¢پBپvپu‚¦‚¦پBپvپu‚خ‚ء‚ؤ‚ٌ‚ھپAƒIƒŒ‚ح’·‚¢•¨‚حپA‘ه‚ج‹êژè‚خ‚¢پBƒ`ƒJ‚³‚ٌپB‚ ‚ٌ‚½پA‚·‚ـ‚ٌ‚¯‚اپA‰½‚ئ‚©‚µ‚؟‚ل‚ç‚ٌ‚ثپ[پBپvپu‚ح‚ پA‚¤‚؟‚ھ‰½‚ئ‚©‚¹‚ٌ‚ئپA‚¢‚©‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚ثپ[پBپvپu‘ه•د‚â‚낤‚¯‚ا‚بپ[پA—ٹ‚ٌ‚¾‚خ‚¢پBپvپu‚ح‚¢پA‚¤‚؟‚ھ‚â‚è‚ـ‚·‚وپBپv•ê‚حپu‚³‚ؤپ[پA‚³‚ ‚³‚ پBپv‚ئèُ‚‚ئپA‰½‚©‚ًŒˆˆس‚µ‚ؤ— Œû‚©‚çڈo‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@‰½‚ج‚±‚ئ‚â‚çپA‚³‚ء‚د‚è”»‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA‚µ‚خ‚ç‚‚µ‚ؤپAپu‚ـ‚±‚ئپv‚ھ— ’ë‚ةڈo‚ؤ‚ف‚é‚ئپA‰½‚â‚畱“¬‚µ‚ؤ‚¢‚é•ê‚ھ‚¢‚½پBŒم‚ë‚©‚çپA‚»‚ج—lژq‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚é‚ئپA•ضڈٹ‚ج‰؛‚ةگ±‚ف‚آ‚¢‚½گ¶‚«•¨‚ًپA‘¾‚ك‚ج–ط‚جژ}‚ً—D‚µ‚چ·‚µگL‚ׂؤپAˆع‚ء‚ؤ‚‚é‚و‚¤‚ة‚ئپA—U‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپu‚³‚ پ[پA‚¨‚¢‚إپ[پBپv
پ@‚µ‚خ‚ç‚‚·‚é‚ئپAژ艂¦‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚©پAپu‚وپ[‚µپA‚و‚µپBپv‚ئ‚¢‚¤گ؛‚ھ‚µ‚½پB‰½‚©‚جگ¶‚«•¨‚ھپAƒXƒ‹ƒXƒ‹پv‚ئژ}‚ةٹھ‚«‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚½پBپu‚¨پ[پA‚¢‚¢ژq‚ثپ[پBپv‚ئŒ¾‚¢‚ب‚ھ‚çپAژ}‚ًژ‚؟ڈم‚°‚½پB—§‚؟ڈم‚ھ‚é‚ئپAگأ‚©‚ةگU‚èŒü‚¢‚ؤپAژ茳‚جژ}‚ةٹھ‚«‚آ‚پA‘ه‚«‚بگ¶‚«•¨‚ًپu‚ـ‚±‚ئپv‚ةŒ©‚¹‚½پB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚ھپA— ‚ج”à‚ج‘O‚©‚猩‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‘ه‚«‚بƒjƒVƒLƒwƒr‚ھپAƒNƒlƒNƒl‚ئ“®‚¢‚ؤ‚¢‚½پBپu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚»‚ج‹گ‘ج‚جژp‚ًŒ©‚½ڈuٹشپAپu‚¤‚ي‚ءپ[پIپBپv‚ئ‹©‚ٌ‚إپA‚ئ‚ء‚³‚ة‰ئ‚ج’†‚ة“¦‚°چ‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@پuƒtƒbپAƒtƒbƒtƒbپBپv‚ئپA•ê‚حڈخ‚¢‚ب‚ھ‚çپA•½کa“I‚ةٹ댯‚ًژو‚èڈœ‚پA‚¨‚¨ژdژ–‚ًپA‚â‚èگ‹‚°‚½’Bگ¬ٹ´‚ة–‚؟‚ؤ‚¢‚ؤپA‚ن‚ء‚‚è‚ئچک‚ًچ~‚낵‚ؤپAƒwƒr‚ج—چ‚ٌ‚¾پu–ط‚جژ}پv‚ً’n–ت‚ةگأ‚©‚ة’u‚¢‚½پB
پ@‚±‚جƒwƒr‚حپA‚ئ‚ؤ‚à‚¨‚ئ‚ب‚µ‚¢گ«ٹi‚إپA‚ـ‚é‚إ•ê‚ج‹Cژ‚؟‚ة‰‚¦‚é‚©‚ج‚و‚¤‚ةپA—D‚µ‚کb‚µ‚©‚¯‚ؤڈ•‚¯‚ؤ‚‚ê‚éگlٹش‚جگ؛‚ةڈ]ڈ‡‚ةڈ]‚ء‚½پB
پ@‚»‚جŒمپA•ê‚حپAƒwƒr‚ً•z‚ج•—کC•~‘ـ‚ة—D‚µ‚“ü‚ê‚ؤپAپu’‰—ى“ƒپv‚ج‰،‚جپu”’ژضگ_ژذپv‚جگخ‚جٹK’i‚ـ‚إ•à‚¢‚ؤپA‚»‚ج—ر‚ج’†‚ةپA‚»‚ء‚ئ•ش‚µ‚ؤ‚ ‚°‚½پB
پ@•ê‚جپAژل‚¢چ ‚جˆَڈغ‚حپA‚ف‚ٌ‚ب‚ھŒ™‚ھ‚ء‚ؤ”ً‚¯‚éپA‚ا‚ٌ‚ب‚ة“‚¢–â‘è‚àپAŒˆ‚µ‚ؤ“¦‚°‚½‚肹‚¸‚ةپA‹°‚ꂸ‚ة—§‚؟Œü‚©‚ء‚ؤپA‰½‚ھ‰½‚إ‚àپA•K‚¸‰ًŒˆ‚µ‚ؤ‚¢‚پAژہ‚ةç—‚µ‚¢پuٹïگص‚ج—حپv‚ً—^‚¦‚ç‚ê‚ؤ‰ئ‚ةŒ»‚ꂽپAپu“Vڈ—پv‚ج‚و‚¤‚ةژv‚¦‚½پB
پ@’j‚إ‚àڈo—ˆ‚ب‚¢ژ–‚ًپAژwˆê–{‚àگG‚ꂸ‚ةپAˆê‘ج‚ا‚ٌ‚ب‚â‚è•û‚ًژg‚ء‚½‚ج‚¾‚낤‚©پHپBپu”O—حپv‚©‰½‚©‚ج—ح‚ھ‚ ‚é‚ئ‚µ‚©ژv‚¦‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@•پ’ت‚ب‚çپAژè‚ءژو‚è‚خ‚â‚پAƒwƒr‚ًژو‚èڈœ‚‚ب‚çپAژè‚إ“ھ‚ً‰ں‚³‚¦‚آ‚¯‚é‚و‚¤‚ة•ك‚ـ‚¦‚ؤپAˆّ‚ء’£‚èڈo‚µ‚ؤڈم‚°‚é•û–@‚ًژو‚é‚ئژv‚¤‚ھپA•ê‚ح‘S‚ˆل‚ء‚½‚â‚è‚©‚½‚¾‚ء‚½پBƒwƒr‚ج—lژq‚ً‚µ‚خ‚ç‚پA‚¶‚ء‚ئٹدژ@‚µ‚ؤپAپu‚ث‚¦پA‹³‚¦‚ؤپB‚ب‚؛‚±‚±‚ةڈZ‚ف‚آ‚¢‚½‚جپHپBپv‚ئپAƒwƒr‚ة–â‚¢‚©‚¯‚ؤ‚¢‚½پB
|
|
|
 |
|
ƒjƒVƒLƒwƒr |
پ@‚·‚é‚ئپAƒwƒr‚جژ–ڈî‚ھ‰½‚ئ‚ب‚“`‚ي‚ء‚ؤ‚«‚½پBپu‘‹‚©‚ç“ü‚ء‚½‚à‚ج‚جپAŒٹ‚ة—ژ‚؟‚ؤ‚µ‚ـ‚¢پAڈم‚ھ‚ê‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB”²‚¯ڈo‚¹‚é‚و‚¤‚ةڈ•‚¯‚ؤ‰؛‚³‚¢پBپv‚ئپAƒwƒr‚ج–ع‚ح‘i‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@•ê‚حپAپu‚ ‚ پA‚»‚¤‚¾‚ء‚½‚جپBپv‚ئèُ‚‚ئپA‘¾‚ك‚ج–ط‚جژ}‚ً’T‚µ‚ؤ‚«‚ؤپAگأ‚©‚ةچ~‚낵‚ؤپAژخ‚ك‚ة—§‚ؤ‚©‚¯‚ؤ‚ ‚°‚½پBپu‚³‚ پ[پA‚¨‚¢‚إپ[پBپv‚·‚é‚ئƒwƒr‚ح“ھ‚ًڈم‚°‚ؤپAگأ‚©‚ةپAژ}‚ةٹھ‚«‚آ‚‚و‚¤‚ة“o‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚¾‚ء‚½پBپu‚وپ[‚µپA‚و‚µ‚و‚µپBپvپ@ƒwƒr‚حپuƒXƒ‹ƒXƒ‹پv‚ئژ}‚ة‘ج‚ًٹھ‚«‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚½پBپu‚ پ[پA‚¢‚¢ژq‚ثپ[پBپvپ@•ê‚حپA‚·‚©‚³‚¸پAگأ‚©‚ة–ط‚جژ}‚ًژ‚؟ڈم‚°‚ؤپA—ژ‚ئ‚³‚ب‚¢‚و‚¤‚ةپAٹO‚ةˆع“®‚µ‚½پB
|
|
|
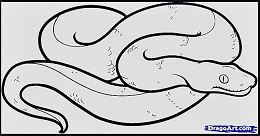 |
|
ƒjƒVƒLƒwƒr |
پ@•ê‚حپAƒwƒr‚ئ“¬‚¤پu“¬‘ˆ–{”\پv‚و‚è‚àپA‚¶‚¢‚ء‚ئ‘ٹژè‚جژ–ڈî‚ًچl‚¦‚ؤپAپu‚ا‚¤‚·‚ê‚خپAˆê”ش‚¢‚¢‚ج‚©پHپBپv‚جپu“ڑ‚¦پBپv‚ًŒ©‚آ‚¯‚é‚ـ‚إپAژٹش‚ً‚©‚¯‚ؤپAپuچإ‘P‚ج•û–@پv‚ً“ث‚«‹l‚ك‚ؤ‚¢‚پA’´گl“I‚بپu”E‘د—حپv‚àپA—^‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚±‚جکb‚حپA“y’n‚ج‹«ٹE–â‘è‚ھ‹N‚±‚é‘O‚جپA‰½‚àŒx‰ْ‚¹‚¸‚ةپA‰¸‚â‚©‚ب‹Cژ‚؟‚إ•é‚炵‚ؤ‚¢‚½چ ‚جپA‚ـ‚¾گS‚ة‚ن‚ئ‚è‚â—D‚µ‚³‚ھ‚ ‚ء‚½پA‹ك—ׂجگl’B‚ج‘Pˆس‚ھپAگM‚¶‚ç‚ꂽپA•ê‚جپAژل‚¢چ ‚جپA‚ظ‚ج‚ع‚ج‚µ‚½پA‚ب‚²‚â‚©‚بگج‚جکb‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@Œ–‰ـŒ{پAپ@ƒVƒƒƒ‚پB
پ@پuچ،ˆن‰ئپv‚ج—ׂحپAپuڈd“cپv‚ئ‚¢‚¤پu‰®•~پv‚ھ“ٌŒ¬‚ ‚ء‚ؤپAپu–{‰ئپv‚ئپu•ھ‰ئپv‚¾‚ء‚½‚炵‚پAگج‚©‚çپAŒZ‚ئ–…‚ھ‚·‚®‹ك‚‚ة•é‚炵پA’·”NپAŒZ‚ئ–…‚ھ’‡—ا‚پAڈZ‚ٌ‚إ‚¢‚½‚炵‚¢پB
پ@‚¾‚ھپAپu–{‰ئپv‚ج‘§ژq‚جپu’·’jپv‚ھپAپu‚¢‚ي‚½‰®پv‚ج•S‰ف“X‚ة‹خ‚ك‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚ش‚é‚¢‚جپu“q”ژچD‚«پv‚إپA— ’ë‚ة‚ح“–ژپA—¬چs‚ء‚ؤ‚¢‚½پAپuŒRŒ{پv‚ئ‚©Œ¾‚ي‚ê‚éپuŒ–‰ـŒ{پv‚جƒIƒX‚جƒVƒƒƒ‚‚ً‰½ڈ\‚د‚àژ”‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚»‚ج’†‚©‚çپAŒ©چ‚ف‚ج‚ ‚éپAچإ‹‚جŒ{‚ًژ艖‚ة‚©‚¯‚ؤˆç‚ؤ‚ ‚°‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚جŒiگF‚حپAŒ{‚ج—‘‚ً•ھ‚¯‚ؤ’¸‚‚و‚¤‚بپA‚ج‚ا‚©‚ب•µˆح‹C‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB’n–ت‚ة‚حپAŒ¯‚µ‚¢Œˆ“¬‚جŒŒ‚ھ—¬‚ê‚ؤ‚¢‚éپA—JںT‚ب‹َٹش‚إ‚ ‚ء‚½پB
|
|
|
 |
|
Œ–‰ـŒ{پAپ@ƒVƒƒƒ‚پB |
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚àپAڈ¬‚³‚¢چ پA‚»‚ج“¬‚ي‚¹•û‚ًŒ©‚½ژ–‚ھ‚ ‚éپB‚Qƒپپ[ƒgƒ‹‚جˆح‚¢‚ج’†‚ةپAƒIƒX‚جƒVƒƒƒ‚‚ً•ْ‚ء‚ؤ“¬‚ي‚¹‚é‚ج‚¾‚ھپAپu“¬‘ˆ–{”\پv‚ھ‚ ‚é‚ج‚إپA‚·‚®‚ةلة‚فچ‡‚¢پA“ث‚ء‚آ‚«چ‡‚¢‚ھژn‚ـ‚ء‚½پB‰s‚¢‘«‚ج’ـ‚إپAڈR‚èچ‡‚¢پAŒŒ‚ف‚ا‚ë‚ة‚ب‚é‚ـ‚إپA‚ئ‚±‚ئ‚ٌ‚ـ‚إپAŒƒ‚µ‚“¬‚ي‚¹‚ؤٹy‚µ‚ٌ‚إ‚¢‚½پB
پ@“ْ—j“ْ‚ة‚ب‚é‚ئپA—ׂج’ë‚ھ‘›‚ھ‚µ‚‚ب‚é‚ج‚إپA‰ن‚ھ‰ئ‚ج‰ئ‘°‚ج‚ف‚ٌ‚ب‚ھپAپu‰½‚ھژn‚ـ‚ء‚½‚ج‚©پHپBپv‚ئپA‘‹‚©‚ç”`‚¢‚½پB—ׂج‘§ژq‚ج’‡ٹش‚ھپAچٍ‚ًˆح‚ٌ‚إ“ٌ‰H‚جƒIƒX‚جƒVƒƒƒ‚‚ً•ْ‚آ‚ئپA‘ٹژè‚ًلة‚ف‚آ‚¯پA‚½‚؟‚ـ‚؟Œƒ‚µ‚¢“¬‚¢‚ھژn‚ـ‚ء‚½پB”ك‚µ‚¢پu“¬‘ˆ–{”\پv‚ً—ک—p‚³‚ê‚ؤپAƒVƒƒƒ‚’B‚ةپAŒ–‰ـ‚ًپA‚¯‚µ‚©‚¯‚ؤ‚¢‚½پB
پ@“–ژپAƒJƒ~ƒ\ƒٹ‚ج‚و‚¤‚ب‰s‚¢پuگn•¨پv‚ً‘«‚ة•t‚¯‚³‚¹‚ؤپA“¬‚ي‚¹‚铹‹ï‚ھ”„‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپA—F’B‚ةŒ©‚¹‚ؤپAƒVƒƒƒ‚‚ج‘«‚ة•t‚¯‚ؤ“¬‚ي‚¹‚½پBپu‚¨‚¨پ[پBپv‚ئٹ½گ؛‚ھڈم‚ھ‚ء‚½‚ھپAپu‚ ‚ پA‚ ‚ پ[پBپv‚ئپA‹ء‚‚و‚¤‚بژ–‘ش‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB“–‚½‚è‚ا‚±‚ë‚ھˆ«‚©‚ء‚½‚ج‚©پA‘ٹژè‚جژٌ‚©‚猌‚ھ•¬‚«ڈo‚µ‚½پB‚ ‚؟‚±‚؟‚ة‘NŒŒ‚ھ”ٍ‚رژU‚èپA‚¯‚½‚½‚ـ‚µ‚¢–آ‚«گ؛‚إپAژcچ“‹ة‚ـ‚铬‚¢‚حڈI‚ء‚½پB
|
|
|
 |
|
Œ–‰ـŒ{پAپ@ƒVƒƒƒ‚پB |
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚حپA‚»‚جŒُŒi‚ًˆê“xپA‹ك‚‚إŒ©‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB‚»‚êˆب—ˆپAپu“¬Œ{پv‚ھ‹êژè‚إپA–ع‚ً”w‚¯‚ؤ‘‹‚©‚ç‚·‚®‚ة—£‚ꂽپB‚¾‚ھپAŒZ‚âژo’B‚حپAپu“¬Œ{پv‚ة‹»–،‚ھ‚ ‚é‚ج‚©پA‹¹‚ً‚ئ‚«‚ك‚©‚¹‚ؤپA‚è‚م‚¤‚¯‚آ‚ج’ةپX‚µ‚¢“¬‚¢‚ھڈI‚ي‚é‚ـ‚إپA‚¢‚آ‚ـ‚إ‚àŒ©‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚±‚ج—E‚ـ‚µ‚¢“¬‚¢‚جŒُŒi‚حپA‰ئ‘°‚جگS‚ةپAپu“¬‘ˆگSپv‚ئ‚¢‚¤پA‘ه‚«‚ب‰e‹؟‚ً—^‚¦‚ؤ‚¢‚پBŒZ‚حپAŒ•“¹‚âپA‹َژè‚ًڈK‚¢پAƒXƒ|پ[ƒcƒ}ƒ“‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚«پA‚¢‚¶‚ك‚ء‚±‚ً‹t‚ة’@‚«‚ج‚ك‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ظ‚اپA‹‚ç—‚µ‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پBŒZ‚àپAژo‚½‚؟‚àپA‚±‚جپu“¬‘ˆگSپv‚ھپA”ç“÷‚ة‚àپA—گ–\‚إپA‘هژG”c‚بگ«ٹi‚ھ‹‚‚ب‚è‰ك‚¬‚ؤپA‚â‚ھ‚ؤپAڈ«—ˆ‚ةژ©‚ç‚ج‰^–½‚ً”j–إ‚ةŒü‚©‚ي‚¹‚ؤ‚¢‚پBپi‰ً–¾•ز‚إڈع‚µ‚ڈq‚ׂéپBپj
|
|
|
 |
|
Œ–‰ـŒ{پAپ@ƒVƒƒƒ‚پB |
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گو‹ى‚¯‚éژoپB
پ@’·ڈ—‚جگMژq‚حپA•sژv‹c‚بگ«ٹi‚إ‚ ‚ء‚½پB•×‹‚ح‚ ‚ـ‚èڈo—ˆ‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA‚»‚ج•ھپA–ˆ“ْ’N‚و‚è‚à’©‘پ‚ٹwچZ‚ةچs‚«پAˆê“ْ‚à‹x‚ـ‚¸‚ة’ت‚¢‘±‚¯پuٹF‹خڈـپv‚ً–ل‚ء‚½پBپ@’†ٹwچZ‚ً‘²‹ئ‚·‚éچ ‚ة‚ب‚é‚ئپA‚ ‚©“_‚ًچج‚é‚ئ—ژ‘و‚·‚é‚ئ‚©‚جکb‚ً•·‚‚ئپAگiٹw‚جٹَ–]‚ًژ‚ؤ‚ب‚‚ب‚ء‚½پB’S”C‚جگوگ¶‚ةپu‚¤‚؟‚حگiٹw‚ب‚ٌ‚©‚µ‚ب‚¢‚إ‚¨ژè“`‚¢‚³‚ٌ‚جژdژ–‚ً‚µ‚½‚¢‚إ‚·پBپv‚ئŒ¾‚¢ڈo‚µ‚½پB
پ@
پ@‚»‚جکb‚ً•·‚¢‚½پA‚¨ژ›‚جکaڈ®‚³‚ٌ‚حپAپu‚ظپ[پAˆê•—•د‚ي‚ء‚½–ت”’‚¢ژq‚¾پBپv‚ئ‹»–،‚ًژ‚ء‚½پB‚µ‚خ‚ç‚‚·‚é‚ئپA”ژ‘½‚ة‚ ‚éپu“Œڈئ‚¶پv‚ئ‚¢‚¤‚¨ژ›‚ج‚¨ژè“`‚¢‚³‚ٌ‚جژdژ–‚ًڈذ‰î‚µ‚ؤ‚‚ꂽپBپ@گMژq‚ح—¦گو‚µ‚ؤ‚»‚ج‚¨ژ›‚ةڈZ‚فچ‚ف‚جڈ—’†‚ئ‚µ‚ؤ“‚‚±‚ئ‚ةŒˆ‚ـ‚ء‚½پB
پ@
پ@گجپAڈ—’†•ٍŒِ‚ج‘ه•د‚³‚ً‘جŒ±‚µ‚ؤ‚¢‚½ƒ`ƒJ‚حپAڈAگE‘O‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚àپA‚ج‚ٌ‚ر‚èچ\‚¦‚ؤ‚¢‚éگMژq‚ةپA‘¼گl‚ج‰ئ‚ةژd‚¦‚éڈ—’†‚ج—§ڈê‚ئپAچإ’لŒہ•K—v‚ئ‚ب‚é‚إ‚ ‚낤پA‘هگط‚بگSٹ|‚¯پA•ضڈٹ‘|ڈœ‚â‘نڈٹ‚إ‚جƒRƒc‚ً‹³‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@گMژq‚حپA‚¨ژ›‚ج‰ئ‘°‚جگl‚½‚؟‚ةژd‚¦‚ب‚ھ‚çپAگlٹش‚ئ‚µ‚ؤ‚جگS‚جڈC—{‚ًگد‚قپAچإ—ا‚ج‹@‰ï‚ً“¾‚½پB
پ@
پ@ڈ¬‚³‚¢چ ‚©‚ç’j‚جژq‚ً‚¢‚¶‚ك‚ؤ‹ƒ‚©‚¹‚½‚èپA‚¨‚ئ‚±‚ـ‚³‚è‚إŒûŒ–‰ـ‚خ‚©‚肵‚ؤ‚¢‚½‹Cگ«‚جچr‚¢ژo‚¾‚ء‚½‚ھپA‚¨ژ›‚جڈZ‚فچ‚ف‚جڈ—’†‚ئ‚µ‚ؤ“‚‚¤‚؟‚ةپA’h‰ئ‚جگl’B‚ة‚àپA‚³‚è‚°‚ب‚چs‚«“ح‚¢‚½‹C”z‚è‚ً‚·‚邱‚ئ‚ًٹw‚ٌ‚إ‚¢‚ء‚½پB‚ـ‚ئ‚à‚بگlٹش‚ة‚ب‚éˆ×‚جگâچD‚ج‚¢‚¢ڈCچsڈê‚ً—^‚¦‚ç‚ꂽپB
پ@گMژq‚حپAژ©•ھ‚ج—ٍ“™ٹ´‚ً‚ذ‚ء‚‚è•ش‚·–ˆؤ‚ً‘M‚‚ئپAگl‚ئˆل‚¤“ث”ٍ‚بچs“®‚ًژو‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚½پB‚»‚ج‚±‚ئ‚إڈي‚ةپu‚ـ‚±‚ئپv‚ج‘O‚ًگو‚ة•à‚¢‚ؤپAڈd—v‚ب‚«‚ء‚©‚¯چى‚è‚ً‚·‚éٹï–‚بڈˆ‚ھ‚ ‚ء‚½پBپ@گV•·”z’B‚àپA“چ‚ج–ط‚àپAژ›‚ض‚ج•ٍŒِ‚àپA‘هگط‚بڈCچs‚جڈغ’¥‚©‚ةŒ©‚¦‚½پB
پ@پu‚ـ‚±‚ئپv‚جژg–½‚ة—ا‚ژ—‚½پA“V‚جڈ€”ُ‚µ‚½“ء•ت‚جŒP—ûڈê‚ةگi‚قپuگ¸گi‚ج“¹پv‚ب‚ج‚¾‚ھپAŒم‚إ”»–¾‚·‚é‚ھپAژہ‚حچI–‚ةژüˆح‚جژز‚ً‹\‚«کf‚ي‚·پA‘S‚‚ج‹t‚³‚ـ‚ج“¹‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@‚â‚ھ‚ؤگMژq‚حپA‰½‚à’m‚炸‚ةپAڈ\”N‚ش‚è‚ة–ك‚éŒZ‚ةپuŒُ‚ج‰ئŒPپv‚ً“`‚¦‚éڈd—v‚بˆت’u‚ة‚¢‚é‚ئ‚ح‹C‚أ‚©‚ب‚¢‚ـ‚ـپA”½ڈب‚à‹³ŒP‚à‚ب‚¢‚ـ‚ـپA‰ن‚ھ“¹‚ً‚آ‚«گi‚ٌ‚إ‚¢‚ء‚½پBپ@پiڈعچׂحپ@ژQپA‚ج‹پ“¹•ز‚إڈq‚ׂ½‚¢پcپBپj
پuŒُ‚ج“¹‚ً”ُ‚¦‚وپIپBپv
“َپA“¬‘ˆ•زپBپ@پ@‘و‚R•”پB
‡BپAƒ`ƒJپAŒƒ“¬ژ‘مپB
‚PکbپB
‰ًگàپAپ@‚PپBپ@‚QپAپ@‚RپAپ@‚SپAپ@‚TپA
‚PکbپBپ@پ@‚¨‚ي‚èپB
پ@
‚آ‚أ‚پB
ژ‚ة‘M‚«‚جŒ¾—t‚ھژ„‚ة—ص‚ٌ‚¾پBپAپu‚ ‚ب‚½‚ج
گe‘°‚ة“ن‚ً‚©‚¯پA ‚½‚ئ‚¦‚ًŒê‚ء‚ؤ Œ¾‚¦پcپBپvپA
|
پuŒُ‚ج“¹‚ً”ُ‚¦‚وپIپBپv |
|
“َپA“¬‘ˆ•زپBپ@پ@پ@‘و‚R•”پB |
|
‡BپAƒ`ƒJپAŒƒ“¬ژ‘مپB |
‚PکbپB |
|
‚PکbپBپ@پ@‚¨‚ي‚èپB |
|
‰ًگàپAپ@‚PپBپ@‚QپAپ@‚RپAپ@‚SپAپ@‚TپA |
|