-------------------------------------------------
赤い龍。
「広田」が、数冊の「漫画本」を持って、見舞いに来てくれた。本の間に、小さな「赤い本」が挟まっていた。「漫画」は、たちまち読んでしまい、時間を持て余すと、「赤い本」に、つい、目を通してしまった。
その本は、社会の仕組みに反発する力と、やたら「妄想」を駆り立てる、不思議な書物だった。「まこと」は、悪い癖で、その中の「言葉」を、何回も繰り返していた。頭の中に、急速に、「革命思想」が入っていった。

省略。
退院して、半年経った。「まこと」は、いつの間にか、同志として取り込まれ、活動していた。同志たちが、九州の各地の支部から、ぞくぞくと集まって来た。今まで孤独に過ごして来た「まこと」が、集団の中で、一つになって行動していく事に、始めて心地よい感覚を覚えた。
それから次第にデモやチラシを貼る活動に、日々明け暮れるようになった。 社会や世の中全てが、矛盾に満ちた意地の悪い存在に見えた。
会社の経営者や、知的生産に携わる人が、労働者の上前をハネる、汚くずるい存在に見え、(こんな世の中なんて、ぶち壊してやりたい…。)と、とてつもなく激しい、「危険な衝動」に駆られていた。
ある日、会社の門に集中的に貼ったビラから、社内に「左翼」がいることを感づかれ、突然、「まこと」は、退社を宣告されてしまった。
やがて、連絡を受けた母が、驚いて寮に現われた。「革命思想」に洗脳され、かたくなに退社を拒む、闘争的な我が子の姿があった。入ったばかりの、中卒の新社員たちも引きずり込んで、悪い影響を与えてしまったことを聞いた。
「迷惑をお掛けして申し訳ありません。」 「チカ」は、入社する時に、お世話になった人達に、何度も頭を下げて謝った。 「チカ」は、強制的に荷物をまとめさせて、逃げるように「我が子」を引き取っていった。 「まこと」にとって、母の表情は、今までに見たことがないほど、険しく悲しげに沈んでいた。
妻の話を聞いた、父の「まさき」は、「まこと」を前に座らせ、何とか洗脳を解こうと説得したが、もはや無駄だった。「「まこと」!、このバカ野郎!、お前のような、社会の秩序を乱す「不平分子」は、昔なら、銃殺刑にされるところだぞ!。」 「チカ」は、そばで、髪を振り乱し、目を真っ赤にして泣いていた。

激しく叱られる「まこと」を、不憫に思いながら、二階で聞いていた「ゼン」が、堪えかねて、階段を降りて来た。大きな声で怒鳴る父親に、「「まさき!」、そげん、きつう、「まこと」ば、叱らんで良かやないか!。」
「なん言いよるな。ばあちゃん。、あんたが、「まこと」ば、甘やかすから、こげん風になったっちゃろもん!。」 父が言い返した。 「ゼン」は、寄ってたかって、みんなから責められる「まこと」を、かばいながら、「ほら、「まこと」、逃げろ。逃げろ!。」「まこと」を、立たせて二階に逃がしてあげた。
「ゼン」は、昔のように、二つ並べて布団を敷いていた。「危険なアカ」になってしまった孫を、横に寝かせてから、しばらく、「言い訳」じみた、「まこと」の話を聞いていた。「うーん、…そうじゃろうかねー…。」
天井を見ながら答えていたが、思想的な事など、「ゼン」に判る筈が無かった。家族の全員が、これ程、悲しんだことは無かった。
何日か過ぎて、父の友人の「松本のおじさん」が、何とか、「まこと」を、説得しようと現われた。だが、たとえ、誰が来ても、人の話を素直に聞くゆとりなど無かった。取りつかれたように、「暴力革命の必然性」を話し出していた。 恐るべきことを、平気で口にした時、おじさんは、耐えかねて、「まこと」の頬を「パンッ!。」と叩いた。
そのとき、「まこと」は、人間として、決して言ってはならない事を言ったことが判った。それでも、「「目的」の為には手段を選ばぬ。」という、排他的な、悪魔の思想が、とりついていて、(世の中を変えるには、資本家を銃で倒すしか、他に方法は無いんだ、仕方ないじゃないか…。)と、心の中でつぶやいていた。
-------------------------------------------------
転換期。
この時から両親の、「まこと」に対する信頼と期待は、完全に無くなった。(こんな人間を社会に出すと迷惑をかける、…。)「チカ」は、姉のシマの息子が鉄工所をやっているのを思い出し、そこに「まこと」を連れて行って、そこで働かせることにした。
従兄弟の「のぶゆき」は、山下製作所という小さな鉄工所を経営していた。「まこと」はそこで古い旋盤を与えられ、しばらくは真面目に機械の部品を削っていた。
「まこと」は、(家族たちに二度と心配かけないように、同志のことはもう忘れよう…。)と、決心し、真面目に実家から新しい職場に通っていた。 「まこと」が、出かけた後、家に左翼らしき人からの電話があり、「まこと」の行方を聞き出そうとしたが、「チカ」は、その度、「さあ、何処に行ったか判りませんが…。」と、とぼけた。
それから、何事もなく半年程が過ぎた。ある日の休日、「まこと」は、久しぶりに外出した。ぼんやりと、天神の商店街を歩いている時、駅の街頭に立つ奇妙な青年達の群れに、心が奪われた。(彼らは、左翼ではない、何者だろうか…?。)
興味を覚え、人ごみの陰から、彼らの様子を見つめた。(彼らは、自分の人生を変える、何かを持っているかも知れない…。)と、直感的に思った。 また、新たな問題をひき起こして、これ以上、家族たちに心配をかけたくなかった。だが、どうしても彼らが気になって、不思議と、駅の前の広場をたびたび、歩くようになった。
初 恋。
ある日の夕方、いつもの駅の階段を上がろうとした時、横からツカツカと、魅力的な女性が近寄って、声をかけて来た。 スラリと背の高い、美しい女性は、「真理教会」の、伝道師の「なおこ」という女性だった。

彼女は、頭をペコリと下げた。「ちょっと、アンケートを取らせ下さい。…聖書に関心有りますか?。」(んー…。)戸惑っている「まこと」に、次々と色々な質問した。
「最後に今あなたの抱えている、あらゆる問題を解決できる、『新しい真理』という講義があるとしたら、聞いてみたいと思いますか?。」と問いかけてきた時、「まこと」は、咄嗟に「、はい。」と答えて、そのまま、すぐに講習会に行くことに決めてしまっていた。

その日、伝道所に連れて行かれて、簡単な講義を受けた。 いきなり、「左翼思想は悪魔の思想だ!。」ということを教えられた。確かに、「銃で資本家を倒し、暴力で労働者の平等社会を目指す共産主義」よりも、「愛の力で、世界を平和に導こうとする、新しい真理」のほうが、はるかに優れていることに納得し、またたく間に「無神論」から「有神論」に急転化していった。
彼女に逢った事で、それまで引きずっていた唯物思想の洗脳から、突然こんなにも簡単に解放されていくとは思いもしなかった。 今まで花を美しく思ったりする情緒も無かったが、自然を造った存在を教えられた時、青い空や白い雲が、人間の感性に呼応するように創られた、神の美しい贈り物に見えて来たのだった。ただ人間の心だけが汚れて見えた。(人間は、果たして堕落しているのだろうか…?。)

神秘性を秘めた、伝道師の「なおこ」が、真理の言葉を語る時、透き通ったピンクの唇が、艶めかしく動くのをぼんやりと見ながら、いけないことを想像している自分を叱った。
「まこと」は、「理想の女性」に出逢った「喜び」と、近寄りがたい「聖い世界」が、複雑に絡んで、夜も昼も、胸が一杯になった。自分の思いが、伝えられない、もどかしさを感じ、「なおこ」の似顔絵を描いて、壁に貼って、ぼんやりと見ている日々が続いた。
「まこと」は、恋愛の情を持って「なおこ」に近づいていったが、「なおこ」は、常に「伝道師」としての、高い次元で対応した。「まこと」は、いつしか「なおこ」と結ばれれる「夢」ばかりを見るようになっていた。
ある日、たまらなくなって、教会の女性に、恋愛の事について聞いた。だが、「教会での恋愛は、絶対禁止されています。」と、言われて、失望してしまった。
-------------------------------------------------
姉、「かづえ」。
やがて、「まこと」は、「アパートを借りて、そこから通勤したい。」と言いだした。だが、「チカ」は、(息子はまた左翼の人間と関わるのではないか…?。)と、心配だった。「もう大丈夫だよ。「共産主義」は、間違っている事が判ったから…。」「チカ」は、そう言う「息子」の言葉を信じて、一人暮らしを、許すことにした。
こうして、「まこと」は、それから毎日、堅粕のアパートから、自転車で、従兄弟の経営する、「山下鉄工所」に通うようになった。日曜日になると、部屋の窓から見える、「ガタガタ」と行き交う電車を一日中、ぼんやりと見て過ごしていた。
次の日曜日、姉の「かづえ」が訪ねて来た。「かづえ」は、近くの「和裁学校の寮」に住み込みで習いに来ていた。「「まこと」、この前ね、左翼の女性が「まこと」の行き先を尋ねて来たわよ。」
「ああ、そう…。」「その女性がね、お前の弱いところを、色々と言って批判したからね、私、ついカッとなって『関係ないでしょ!。弟のことを、あなたから、そんなに言われる筋合いは無いわ!』と、言い返してやったわ。」
「かづえ」は、一見おとなしい女性に見えたが、激しい性格が潜んでいた。 「まこと」は、既にもう、「反共の立場」に立っていた。家族の心配の種になるし、もう彼らとは一切関わりを持ちたくなかった。「うん、それでいいよ。」「まこと」は、姉に答えた。
しばらくすると、「まこと」は、「かづえ」に『新しい真理』の話をしていた。 左翼から、離れたばかりの弟は、既に、次の「新たな価値観」に取り憑かれ、僅かの間に「神の存在論」の話をしていた。
そんな弟にあきれたのか、「「まこと」!、あんたは、もう次のものに影響されてるの!。それに、そんな断定的に、決めつけたような教えを、人に押しつけるんじゃないよ!。」 弟の話す言葉を、いきなり遮り、強く叱りつけた。
-------------------------------------------------
天使の誘惑。
伝道師の「なおこ」からの手紙が、頻繁に来ていた。その中に、「まこと」の心を強く打つ、聖句が書いてあった。 「私の子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に責められる時、弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れる全ての子を鞭打たれるのである、…。」
この聖句が、自分の為に書かれた、特別の言葉に思え、すっかり感銘した「まこと」は、悪い癖で、またもや何回も、この文章を唱えて繰り返していた。
その、神の訓練が、この組織に入って受ける、訓練であることを直感した時、(僕は、この教会に入信しなければならない…。)と、強い衝動が走った。そして、その予感通り、「まこと」は、この組織と関わり、献身する状況に追い込まれていくのだった。

「まこと」を伝道した、「なおこ」という美しい女性は、髪を短めに切り、いつもこざっぱりした身なりをしていた。探し求めていた、素晴しい「理想の女性」、「神の道」を説く天使のような彼女に、時々会えることが、何よりの喜びになった。
いつしか「まこと」は、恋におちて、(スラリとした彼女をもし抱くことが出来れば、どんなに幸せだろうか…。)と、毎夜、妄想を抱いて熱く悶えた。
眩しいほどの、聖い世界を持つ女性に対して、肉欲の思いが湧いて来るのがとても醜く、いけない事のように思えた。
やがて彼女によって、人生の目的を教えられ、堕落した人間を救おうとされる「神の使命」のために一生懸命に生きる姿を、最も尊い価値観として見るようになっていく。
そしていつしか(「なおこ」と人生を共にしたい…。)と、思うようになっていった。 「なおこ」の手紙には、「「まことさん」といつか、一諸にやれる日を楽しみにしています。」と書いてあった。
だが、集団生活が苦手な「まこと」は、人が大勢集まる組織に、献身する気持ちなど、すぐにはなれなかった。
職場の方には、「なおこ」からの電話が、よく掛かって来ていた。「まこと」を預かった従兄弟の「のぶゆき」は、(また誰かに誘われてるな…。)と、心配しながら受話器を手渡した。
「修練会に参加してほしい。」という誘いだった。「まこと」は、横目で、社長の「のぶゆき」の目線を、気にしながら断った。「今、仕事が忙しいから、とても行けません。」
「今井さんは、何の為に働いているの?。仕事よりも、人間として知らなければならない、大切なことがあるでしょう。それをぜひ聞いて欲しいの…。」「なおこ」が、余りにも、根気強く言うので、「まこと」は、とうとう断われなくなった。電話を切ると、「まこと」は、「すみません、一週間だけ休みを貰えませんか?。」と頼んだ。「のぶゆき」は、渋々許可した。
「まこと」は、修練会に参加し、『新しい真理』の講義を一通り聞いた。朝から晩まで、「詰め込み式」に語られる講義だった。
そして、一週間の「修練会」が終わると、何事も無かったように、また会社に戻って働いていた。
「「のぶゆき」さん、、しばらく勤労青年として入信してやらせてくれませんか?。」「まこと」は、帰って来るなり社長に相談した。
「どうせやるなら、中に入って、思いっきりやったらいい。そうすれば、どんなものか、はっきり判るよ。」「え、…?。」「とにかく、二ヶ月間やってみて、その結果を報告してくれ…。」と、独断で、勝手に期間を決めて、「まこと」に約束をさせた。
-------------------------------------------------
○氷の心。
次の日、「まこと」は、色々と迷った挙げ句、(やっぱり働きながら教会に通っていこう。)と決め、相談しようと教会を訪ねた。ところが、その日、新任の「団長」が、たまたま来ていた。話をしているうちに、「今は、そんな時代じゃあ無いよ!すぐ献身しなさい。」と、有無を言わせず、強引に献身することを、決められてしまった。
しばらくして、「なおこ」が現われた。自分が全く知らない内に、「まこと」が献身する話になったことを知って「なおこ」は、驚いた。(私に何の相談もなく…。)「まこと」に対しても不満があり、横から強引に決めた団長に対しても、腹立たしく思った。
「「なおこ」ちゃん」、「今井くん」を、みんなのいる場所に、一緒に連れて行きなさい。」「え、…はい…。」返事しながらも「なおこ」は、何か他に用事があったのか、不満そうな顔をした。
こうして二人は、夜のバスに乗ったが、何故か気まずい、沈黙の時間が続いた。(越権行為で、まずかったかな…?。) 「まこと」は、色々と考え過ぎて、胸が痛くなった。「なおこ」は、怒ったのか、着くまで、ほとんど何も喋らなかった。
「まこと」は、献身してから、「なおこ」と一緒に活動をするうち、彼女が自分の思い描いていた「優しい心をもった理想の女性」ではないことを、次第に感じていった。
「なおこ」は、「教会の教義」を堅く信じて、ただひたすら忠実に、その教え通りに、厳しく従おうとする人だった。幼い信者たちを、導く責任を一人で、背負い込んで、一生懸命に実績を出そうと、頑張る人だったが、「まこと」には、(彼女の心には、人間としての、本当の思いやりや、愛情が欠けている。)ように写った。
「まこと」は、次第に「なおこ」と、心が通わなくなっていった。「なおこ」は、組織の命令に徹底して忠実で、実績を追求するあまり、真面目に取り組まない、「まこと」を、激しく批判するようになった。
(こんな、いい加減な人、伝道しなければよかった…。) 「まこと」にとって、あれほど、憧れの女性に見えた人が、その、「冷酷な本性」を見せた時、(ここは自分の安らぐ場所でない…。)と悟った。人間愛を忘れて、実績ばかりを追い求める、組織の非情さに苦しくなって、次第に疑問を感じていった。
はや、半年過ぎた。だが、「二ヶ月経ったら報告する事。」という「社長」との約束は、すっかり忘れてしまっていた。「まこと」は、いったん何か始めると、何もかも忘れてしまう処があった。
-------------------------------------------------
祖母の死。
「ゼン」は、八十歳まで、ほとんど病気知らずだったが、「まこと」が、左翼に洗脳された頃から、次第に元気が無くなっていった。そして、今度は宗教にかぶれた「まこと」を、みんなが寄ってたかってけなして、「できそこないめ!。」と、馬鹿にするので、「ゼン」は、これ以上「まこと」のことを擁護することができず、次第に言葉少なくなった。
どんなことがあっても、「ゼン」だけは、最後までかばっていたが、家族のみんなに、理解して貰えないもどかしい思いが膨らみ、腹の中に苦いものがあふれていった。次第に、「ゼン」の腹には、黒い影が差していた。体調が悪くなり、お腹が少し膨れるようになった。「まこと」が、教会に入って一年過ぎた頃、「ゼン」は、畑仕事も出来なくなった。
ある日、「ゼン」は、自分の余命が、あと幾ばくもない事を悟り、ある重大な覚悟を決めていった。そして、どうにか、やっとその準備が整い終わった時、急激に力が抜けていった。 もう、立っているだけで、つらくなり、やっとの思いで病院に行くことにした。
診察の結果、「即、入院」という事になり、すぐ大手術を施されたが、それから、急激に容態が悪化していった。
「チカ」と「かづえ」が、交代で、「ゼン」の付き添いに通っていた。「おれは、今まで「チカ」さんに好きなことばかりさせて貰って来て、ほんに幸せもんぞ、…。もうなんにも思い残す事は無かー。」 付き添いに来ていた「かづえ」に、「ゼン」は、しみじみと話すのだった。
ある日、「チカ」は、着替えを持って行ってやろう。と思って、二階の姑のタンスを開けた。だが、あれほどたくさんあった着物が、一枚もなく、空っぽであった。驚いて他の引き出しも、次々に開けていった。
そして、最後の引き出しに、ポツンと一つだけ、風呂敷に包まれたものが現われた。胸騒ぎを感じて、急いで結びをほどくと、そこには、喪服を着た「ゼン」の写真と、白い「死装束」が、きれいにたたんで入れてあった。
「ゼン」は、自分自身の死期が近いのを、既に予感して、何か「願」をかけるように、きれいに身辺整理をしていたのだ。「チカ」は、姑の「ゼン」の、死を迎える準備と覚悟に驚いてしまった。
やがて、「まこと」のもとに、「祖母が危篤。」という知らせがあった。他の市に、派遣されていた「まこと」は、かなり時間が経ってから、その知らせを聞き、慌てて見舞いに行った。 だが、「ゼン」は、既に抗ガン剤を打たれて、激しい痛みで、体を「ガタガタ」と痙攣させて、苦しみもがいていた。
「ゼン」は、親族のみんなに見守られながら、何かを託すように、「チカ」の名前を呼びながら亡くなっていった。「「チカ」さん、…後のこと頼みましたばい…。」
お通夜の夜、姉の「かづえ」が、遺体にすがり、「ばあちゃん!、ばあちゃん!。」と激しく泣いていた。 「まこと」は身を切られるように悲しかったが、自分のせいで祖母が心を痛め、急速に体を病んでいった気がしていた。
冷たくなった「ゼン」の遺体を見ながら、(ばあちゃん、ごめんよ、ごめんよ…。)と、心の中でつぶやいていた。自分が祖母を死に追いつめたのに泣くわけにはいかなかった。(泣いちゃいけない!泣くもんか…。)「まこと」は、平静を装い、涙をじっとこらえた。
横で、静かに立っている弟に気がつき、「かづえ」は、涙を拭きながら聞いた。「「まこと」は悲しくないの?。」「…人間は、みんな、…いつか死んで行くのさ、…。」「何よ!。「まこと」が、ばあちゃんに一番可愛がって貰っていたくせに!。」「かづえ」は、「まこと」を激しくなじった。

「まこと」は、信仰するようになってから、(人間は、死んで肉身を脱いで、魂は霊界に行くもの…。)と、思い、肉身の別れが永遠の別れとは思わなくなっていた。 「ゼン」の魂は、いつも自分の心に語りかけ、見守ってくれている感覚があった。そこに在るのは、「ゼン」の「抜け殻」だけだった。
(ごめんよ、ごめんよ、おばあちゃん!。今、何処にいるの…?。) 「まこと」は、目を閉じて、祖母の魂が何処にいるのか捜した。 その時、「ゼン」の霊が、「まこと」を包み込んだ気配がした。脳裏に、「ゼン」の顔が現われた。
(「まこと」…よかよか、泣かんでよか。、おれの事はもう、いいけん、自分の道をゆきなさい…。いつも、見守ってあげるけんね。ばあちゃんは、もう地上では、お前のことを守れないことが判ったよ。これからは、霊界から、いつでも何処でも、飛んでいって、守ってあげるからね…。)心にそう語りかけると、「まこと」を包み込むように、背中に消えていった。
翌朝、「ゼン」の遺体は、死化粧が施され、生前大切にしていた物と一緒に、棺に入れられた。やがて、棺は火葬場に運ばれ、火が点けられた。みんなは、控え室に移動したが、「まこと」は、外に出て、煙突から上がる煙をしばらく見ていた。だが、急に何かを感じて、一人だけ元の場所に戻って来た。
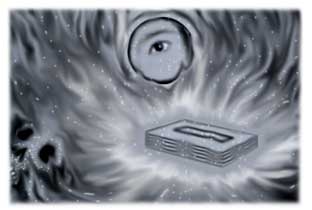
覗き穴から、ゴーと燃える、棺の中を覗くと、下の方に「お経の本」がチラリと見えた。「お経」の周りだけ炎がよけて燃えていた。 見えない力が、「お経」から出ているのを、「まこと」は、不思議な思いでしばらく見ていた。
一時間後、焼けた骨が出て来たが、あれだけの強い炎の中でも、「経本」の周りが、少し焦げただけで、「お経」の文字は、しっかりと燃えずに残っていた。みんな「不思議だ…。何かの念が入っていたとやろうか?。」と、話した。
「まこと」は一人、祖母の事を考えていた。あまりにもあっけなく亡くなった「ゼン」の、死に際の見事さに何かを感じた。まるで、幼い主君に、最後まで忠誠を尽くして逝った、武士の見事な心得のようなものを見た思いがしていた。
-------------------------------------------------
東 京。
「まこと」が、教会に入って二年目、急に「東京」への人事移動の話が持ち上がって来た。(これは、いい機会が出来たぞ…。) 「まこと」は、密かにそう思った。というのも、「東京」に行ったまま帰らない、兄の「のりお」の消息を探すためにも、(いずれ、「東京」に行かなければ…。)と、思っていたからだった。
「渋谷支部」に、行くことに決まったので、新たな「東京」の環境に移るのを機会に、そのまま、この組織から静かに抜け出す計画を立てた。 かすかな不安と希望を、胸に抱きながら、「東京」ゆきの汽車に乗った。
-------------------------------------------------
浮浪者。
初めて見た「東京」は、やたらに人が多く、ビルが果てしなく立ち並ぶ「大都会」だった。

省略。
密かに教会を抜け出した「まこと」は、渋谷、池袋、新宿、と、ゆく当てもなく、転々と移動した。ポケットには、わずか五百円しかなかった。パン屋さんで、十円で袋一杯の「パンの耳」を買って、近くのビルの屋上でかじった。サンドイッチの、「卵」が少し付いていて、有り難かった。(さて、これからどうしようか…。)
夕方になると、雨が降って来た。 「まこと」は、近くのビルの屋上の、階段の所で「寝袋」に入って野宿した。 ま夜中に、眠っている「まこと」の足を、ポンポンと叩く人がいた。顔を出すと、二人の警察官が見下ろしていた。住人の誰かが、「不審な者が寝ている。死体かも知れない。」と、怖がって、通報したらしい。
そのまま、「派出所」に連れていかれ、持ち物や、身元などを調べられた。 「寝袋」の他には、「教義の本」と「数枚の写真」だけだった。 本籍地を調べあげると、「家に連絡していいかね。」と、若い警官が聞いた。「家には電話しないでください!。」 「まこと」は、母が心配することを恐れた。
「うーむ、…教会の青年なら、真面目な青年に違いない…。何か、深い事情があって抜け出したのだろう、…。」と、年配の警官が心配して言った。「実は、…教会に疑問を感じて、抜け出す決意をしたんです。」 「まこと」は、正直に、ありのままを話した。
「君、このままじゃ、薄汚れて、浮浪者になってしまうよ。「アルバイトニュース」でも買って、すぐ職を探して働きなさい。」 警官は「まこと」に五千円を渡して解放してくれた。(もっともだ…。)「まこと」は、言われた通り、すぐ駅の売店で、「アルバイトニュース」を買った。
パラパラとめくると、「寮付き」の比較的大きいホテルを見つけた。すぐに、その足で面接に行き、「即決」でその寮に入ることになった。
-------------------------------------------------
十年の空白。
昼間はウエイター、夜は喫茶店のカウンター、と毎日忙しく働いた。チーフに中華料理の作り方を教えて貰い、いつしか簡単な料理ぐらいは作れるようになった。
寮には、九州出身の学生達が何人かいて、次第に仲良くなり、色々なことを、話したり遊んだりして、楽しい二年間が、あっという間に過ぎていった。教会の事は、すっかり忘れてしまおうとしていた。 流される自分を感じて来た時、(今のうちに何かを身に付けなきゃ…。)と、次第にあせりを感じていった。「まこと」は、久しぶりに実家に年賀状を出した。
それから何日かして、姉の「かづえ」から、突然電話があった。「行方不明になっていた兄貴が、東京にいることが判ったよ。」 しばらくして、当の兄貴本人からの電話が入った。世田谷の方で独立し、自営しているとのことだった。
「まこと」は、十年ぶりに「兄」に逢って、ただただ、懐かしかった。小学生の頃に別れたきりだった。
広い東京で、血のつながった兄と弟が、薄暗いバス停前で再会した。大きかった兄貴の体が、以外に小さく見えた。●
しばらくして「まこと」はホテルを辞め、兄のいる街の方に引っ越した。兄の仕事を手伝ったりしたが、次第に十年の空白がいかに大きいかを感じていった。血を分けた兄弟なのに、判り合えない他人のような冷たい関係があった。
心の通わない悲しさの中で、仕事を手伝いながらも失望していった。(自分に合う仕事ではない、自分の安住する場所でない、…。)と感じると、やがて行くのをやめた。
東京に来て、はや三年が流れた。自分に向く職業が判らず、相変わらず会社を転々としていた。 何処に行っても長続きせず、金がなくて、キャベツとインスタントラーメンばかり食べていた。
いつしか家賃も払えなくなり、再び食事付きの職を探そうと、なけなしのお金でアルバイトニュースを買った。偶然にも下町の方に「住み込みの厨房の調理師見習い募集」の広告に目が止まった。「まこと」はすぐそこに面接に行った。
-------------------------------------------------
仕事と恋愛。
小さな弁当屋だったが、「まこと」は寮に入って住み込みで働くことにした。人員が足らなかったのか、その日からすぐ包丁を持たせてくれた。毎日、野菜や魚などを切ったり焼いたり、大量の下ごしらえする調理場の仕事は忙しかった。
だが、食材を扱う手触りが何とも言えない快感だった。手が空くと弁当箱にご飯をよそう「盛りつけ」の仕事を手伝った。そこでのテキパキと段取りをする訓練は、仕事に対する心構えと「食材」を手で触れて処理していく楽しさを充分に味合うことができた。今までに感じたことのない不思議な充実感があった。
いつしか「のろまの「まこと」」が「スピードの「まこと」」と呼ばれるようになっていた。

ご飯盛りを手伝うようになった時、そこに長年勤めていた「ひろこ」という一回り年上の女性と向かい合って、初めて言葉を交わした。彼女は「まこと」が入社してきてから、だんだんと慣れていく様子を少し離れた所から、ずうーっと静かに見ていたのだった。
「まこと」はすばやい速さで、ご飯を盛りながらも、冗談半分で「今度飲みに行こうか、…」と誘って、そのまま忘れていた。
それから何か月か経った。「ねえ、あんた、一体いつになったら私を飲みに連れて行ってくれるんだよー!」彼女はしびれを切らしたように、ウインクして催促して来た。「まこと」は彼女が本気で待っていたことを知って慌てた。
初めてのデートはスナックだった。ほんのりと酔いがまわった頃。「自分には、ある使命があって、いつか時が来たら、帰らなければならないんだ」「へえー、…」だが彼女はその意味が何のことか判らなかった。「まこと」は「ひろこ」の中に、だんだんと母親のようなぬくもりを覚えていった。今まで生きて来て、初めて人間同士の暖かさと安らぎを感じていた。
「ひろこ」は母親と二人暮らしだった。彼女は、「まこと」の中に底知れぬ深い孤独な影を感じとっていた。遠慮がちの「まこと」を、ある日、自分の家に連れて来て、昔から居た弟のように自然に導き入れてくれた。その日を境に、砂漠のようだった「まこと」の心を癒す愛の水が潤い、バラ色に輝く夢のような日々に変わっていった。
ある日、職場のおばさんが「二人の相性はピッタリだよ」と言った。男勝りの「ひろこ」と内気でおとなしい「まこと」は確かに心が引かれ合っていた。
しばらくして「まこと」は弁当屋を辞めた。アパートを借りて、駅前の「喫茶店」に勤めるようになった。コーヒーやサンドイッチを作るカウンターの仕事は結構忙しかった。 午前中はめまぐるしく忙しかったが、午後は客足がパッタリと止まった。何とかお客の目を引きそうなポスターを工夫して描いている内に、文字や絵を書くことがとても面白いことに気が付いた。
(自分のやりたかった仕事はこれだ、…この仕事こそ自分の「天職」だ、…。)そう直感した「まこと」は本格的にレタリングの通信教育を習い始めた。時間を忘れて文字やイラストを書く夜が毎日続いた。筆を持って熱中している時、充実した時間が流れていた。
東京に来て「ひろこ」に出会ったことと、自分の天職を見つけたこと。この二つが、「大きな恵と収穫」だった。味気ない人間関係を彷徨って来た「まこと」が、「ひろこ」との出会いによって、ようやく生きる勇気と自信を取り戻そうとしていた。
-------------------------------------------------
安らぎの家。
仕事が終わり、部屋でぼんやりしている処へ、急に「ひろこ」が現われた。「「まこと」くん、晩ご飯を食べにいらっしゃい」「え、いや、いいよ、…」「うちのお母さんが料理作って待ってるんだからさ、さあ早くおいで!」遠慮する「まこと」を押し切るように連れ出した。

母親のような「ひろこ」の暖かい手が「まこと」の手を強く握り、暗闇の道を姉弟のように歩いていった。彼女の家に向かう道の途中には、昔、関東大震災の時、朝鮮人の大量虐殺のあった広場があった。薄気味悪い道が、この日だけはロマンチックだった。
十五分ほど歩いて、「ひろこ」の家に入ると懐かしい夕げの香りがした。奥の座敷には、ご馳走が準備してあり、「ひろこ」は新しい座布団を持って来て「まこと」を座らせた。 「まこと」は緊張して正座して待った。「「まこと」くん、正座なんかしねーで、さあ、足を崩して座んねーしょ」「ひろこ」の母親の真子が鍋を抱えながらやって来て言った。 真子は、東北のなまりがなかなか取れないままだったが、娘はいつの間にかすっかり東京人となっていた。

弁当屋を辞めてから、久しくまともなご飯を食べてなかった。「まこと」は、母と娘の二人に優しくもてなされ、感謝しながらご馳走を頂いた。 涙が出る程、人の情が有り難かった。
「まこと」はすっかりご馳走になり、お礼を言って帰ろうとした。「あんだの夕食は、毎日うちで用意するかんない、仕事が終わったらうちさ必ず寄って、ちゃんと食べてから帰んなんしいよ」「え…はい」東北出身の真子のほのぼのした口調が、緊張していた「まこと」の心を解きほぐしていた。
それからだった。癖がついて、ほとんど彼女の家でご飯を食べるのが習慣となった。帰ろうとすると「今日は遅いから、はー、泊まっていぐどいいー」と布団を敷いてくれた。
その行為に甘えていくうち、毎日泊まるようになり、すっかりこの宮崎家の家族の一員になっていった。血のつながった親や兄弟より、あかの他人の家庭の中のほうが、ずーっと心が安らいでいる自分が不思議だった。
-------------------------------------------------
居候の兄。
母から手紙が来た。「「のりお」の電話が不通になり、連絡が取れないので心配です。調べてください」母の手紙は「まこと」宛てに来た初めての手紙だったが、兄の心配ばかりで、「まこと」のことはひとつも書いてなかった。
母の気持ちは兄の「のりお」に向かっているのが判った。「まこと」はかすかに嫉妬を感じたが、打ち消すようにすぐ「のりお」のアパートに向かった。
部屋のドアを叩いた。電気が点いているのに返事が無かった。「兄貴!僕だよ」「おお!「まこと」か」あわててドアを開けた。訳を聞いてみると(何百万という借金を抱えて、会社が倒産した。)と話した。 「のりお」はてっきり(借金取りが来た、…。)と勘違いして、息を潜めて居留守を使っていたのだった。
「そんなに困ってるなら僕の部屋に引っ越したらいい」「まこと」は勧めた。「自分には家族同然にして泊めてくれる処があるから、遠慮しないで、一人で気兼ね無く落ち着くまで僕の部屋にいたらいいよ」「おお、そうか、…」

二、三日して「のりお」は荷物をまとめて「まこと」の部屋に転がり込んで来たものの、どうやら金がなくて食費にも困っている兄を気遣って、「まこと」は「ひろこ」に相談してみた。
次の日から「ひろこ」が一つ多めに弁当を持って帰って来てくれることになった。「まこと」は毎日その弁当を持って行った。 弁当を渡してすぐ帰ろうとすると「おい!、たまには泊まっていけ」と言った。だが、「まこと」は一日でも「ひろこ」と離れてはいられなかった。
「ひろこ」のいない空間の中では安らぎを感じられず、たちまち全身の力が無くなっていくのだった。「いや帰らないと、彼女が心配するから、…」「ふーん、よく毎日泊めてくれるもんだなー」「のりお」は半分あきれて言った。
「まこと」は「ひろこ」と真子といる時、祖母の生きていた、あの頃の空間に戻っているような気がしていた。「まこと」は(この束の間の憩いの時間が、長くない。)ことを本能で直感していた。
やがて襲ってくる艱難の時に耐えられるだけの「心の支え」と「安らぎの時間」が、ほんのわずかの間だけ自分に与えられていることを予感していたのだった。
-------------------------------------------------
父の危篤。
「かづえ」から手紙が来た。「父の命はもうあまり長くないので、早目に帰ってくるように」との手紙だった。「のりお」は相変わらず仕事にも就けず、借金取りから逃げるために、ひっそり隠れるように暮らしていた。
「兄貴、先に田舎に帰って親父をみてくれないかなー。その方が僕も安心だから、…」「まこと」は兄に飛行機代を渡して、すぐ帰るように促した。「のりお」はしばらく迷っていたが、意を決して東京の未練をふり切って、福岡に帰っていった。
闇夜の力
「のりお」が福岡に帰ってしばらく過ぎた。
仕事が終わって、亀戸の駅前を自転車を押して帰る途中だった。 離れた前方にふと目をやると、駅の街頭に見覚えのある姿があった。
懐かしい「伝道師の「なおこ」」だった。アンケート板を胸に抱いて、こちらの人ごみの方に視線を向けて立っていた。(こんなところで「なおこ」さんに会うなんて、…。)不思議な出会いを感じながら、懐かしさでしばらく茫然と立ちすくんだまま彼女の姿を見ていた。

やがて「なおこ」の視線が自分の方に向いた。「まこと」は慌てて彼女からの視線をそらし、顔を伏せて歩いた。何故か瞬間的に険しい「茨」のような闇に吸い込まれる恐怖がよぎったのだった。
「まこと」は、咄嗟に脇道に入って急ぎ足で家に向かった。 しばらく走ったあと、(視線をそらして去った自分の姿を、ひょっとして「なおこ」が気が付いたのではないか、…。)と頭によぎり負債感が湧いて来た。
逃げていく「まこと」の後姿に気がつき、後を急いで追う「なおこ」が、「まこと」に裏切られた悲しみに、がく然と落ち込む姿が頭に浮かんだ。目前に自分のアパートが見えていたが、急に思い直して立ち止まった。
(やっぱり声をかけよう、…。)くるりと向きを変えると、今来た道を急いで引き返して「なおこ」を探しに戻った。だが駅前には彼女の姿はもう既にそこには無かった。
彼女を裏切った大きな負債感が、それから毎日のように「まこと」を責め立てるようになった。 (何があっても、今の幸せな生活を捨てたくない、…。)と心に言い聞かせた。だがそれを許さない恐ろしい闇の力が襲って来るようになった。(全てを捨てよ、…。)暗闇から声ならぬ声が聞こえて来るのだった。
-------------------------------------------------
愛情と使命。
「ひろこ」はひと回りも年上で、男勝りで気丈な女性だった。「福岡に帰らなければならない」と「まこと」が別れを切り出しても、「何よー、心にもないことを言うんじゃないよ!」と本気にせず、特に取り乱したりはしなかった。
だが、「まこと」の帰り仕度が次第に整っていくにつれ、その決意が本気であることを知ってあせり出した。「ひろこ」はいつしか憂鬱で寂しそうな表情に変わっていった。
そして遂に別れの前日になった。無口になった彼女が悲しそうにふとつぶやいた。「私ってなんで、いつも別れる運命の人にしか出会わないんだろう、…」「え、…」 その時、「まこと」の脳裏に、彼女の若い頃の話が、ふっと頭に浮かんで来た。それは、「ひろこ」が若い娘の頃の話だった。
-------------------------------------------------
--------- 、回 想 ---------
「ひろこ」は、東北の方で肺結核にかかり入院していた。 その頃、同じ病棟にいた、画家を目指していた青年と出会い、いつしかお互いに愛し合うようになった。二人は結婚の約束までしていたが、ある日その青年は、遺書もなく突然自殺した。 抱えた悩みを彼女にも打ち明けないまま、静かに命を断ってしまった。 (どうして私に何にも言わずに一人で死んでしまったの、…?。) それ以来、彼女はずっとその死んだ恋人のことを思い続けて独身を通してきた。 彼女の夢枕には、死んだ人の幻が毎晩のように現われ続けていた。だが「まこと」が現われたとき、幻は突然フッと消えた、…という。
「ひろこ」は以前、この不思議な話を打ち明けてくれたことがあった。(彼女は、死んだ恋人が「まこと」の肉体を借りて目前に現われたと思い込んだのだろうか?。)以前、「まこと」は彼女の家の押し入れの奥にしまってあったアルバムを偶然見つけたことがあった。めくって見ると、その中には「まこと」に良く似た男の人の写真があった。それを見た時、急に胸が切なくなった。「「ひろこ」さん、この人誰なの?」「あ、ダメよ!、それはもう過去の人だから見るんじゃないの、バカ!」「ひろこ」はアルバムを慌てて取り上げ、元に戻して戸棚を「バタン」と閉めた。
「まこと」は(こんなに内気で、生きることに不器用な自分を、なぜ溺愛してくれるのか、…。)今まで不思議でならなかったのだが、その理由が今ようやく判った気がした。(彼女は僕の中にその人の面影を見いだして、償いをするかのように一生懸命に身代わりに尽くしてくれていたのかも知れない、…。)
「まこと」は自分自身、女性に愛される資格も魅力も何もない男だと判っていた。だからこそ、こんなにも一方的に人から愛される自分が、何か許されないほどの罪を犯しているような気持ちになることがあった。この状況は勿体ないほどに都合よく、又とても有り難かった。
たとえ仮の代償行為だったっていい、このまま、ずーと「ひろこ」に甘えていつまでも愛され続けていたかった。(不幸な彼女のためにもそうしたい。)と思った。
だがその一方的に与えられた情愛に終止符を打つ、見えない大きな力が近づいていた。(もともと僕は人に愛される資格などないんだ。このまま、いつまでも人の情けに甘え続けていてはいけない、…。)心の中にもう一人の自分の声が聞こえて来た。
(「まこと」、自分の道を行け、…全てを捨てよ、…!。) 「まこと」は忘れていた昔の誓いを思い出したような気がした。それが更に「まこと」を追いつめていった。(天の要求する道は、かくも厳しい選択を強いるものなのか…。)
離れた組織の教義がまだ「まこと」の心を支配していた。地獄に落ちて行く恐ろしい恐怖感が襲っていた。(だが、まだ見ぬ将来のことより、今、愛する人とこのまま暮らし続けたい、…。)と打ち消すように何度も何度も祈った。だが「暗闇の力」は「まこと」のわがままな願いなど容赦なく打ち壊していった。
とてつもなく大きな闇の力の前には、どうあがいても勝てはしなかった。(二度と会えないかも知れない、…こんなに愛しく大切な人の情を切ってでも行かねばならない道があるのですか、…?。)毎日毎日、悩み続ける苦しい日が続いた。

ある夜、「まこと」は「ひろこ」のいる暖かい部屋をそっと抜け出し「フラフラ」と夜道を彷徨っていた。気がつくと、いつしか朝鮮人達が虐殺された空き地に吸い込まれ、真っ暗な闇の中に一人で立っていた。恨みの霊が「ウヨウヨ」と漂っている不気味な場所だった。
(どうすればいいのですか、…?。)闇の主体に祈りながら、迷いを吹き飛ばす明快な答えを求め続けた。 何時間過ぎただろうか、(「まこと」よ、行きなさい、…)闇の主の声が心に聞こえ、頭の中に何か一筋の光が光った。
その声は「まこと」の迷いを一瞬で消した。(宿命の道を行け、…。)と示した「闇の声」を聞いたとき、「まこと」は二度と逢えない大切な宝を捨て、冷たい非情の人間になっていく道を、この一瞬に決めてしまっていた。
この事で、やがて「ひろこ」を裏切った苦しみに、生涯、後悔し続けることになっていく。(あの闇の声は、一体何だったのだろうか、…?。) この取り返しのつかない選択は、天の壮大な摂理を進める上で、避けて通れない宿命であった。このとき聞こえてきた「暗闇の声の正体と謎」は、遥かずっと後になってから、すべての意味が判ってくる。
「まこと」は、「ひろこ」が「よくやったね」と言ってくれる日が必ず来ると信じて、果てしなく続く「暗黒の道」をその後も歩いて行く。たったひとりで乗り越えなければならない「孤独の犬」を演じていくことを、不思議な直感で決めてしまっていたのだった。 
|